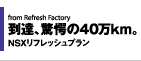 |
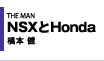 |
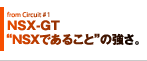 |
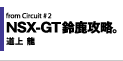 |
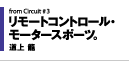 |
 |

いきなり世界の最高峰レースへ挑んだマン島TTレース、そしてF1。そのチャレンジ精神は、「やるからには世界の頂点に立つ」というHondaの熱き勝利への情熱に端を発している。そして、インディカー・シリーズ、ル・マン24時間レースなど、Hondaはすべからく“勝つため”にレースに挑んできた。 しかし、レースで勝ち続けるのは難しい。いいドライバー、速いマシン、いいマネージメントのできるチームという、優れた総合力が存在して初めて勝利を得ることができる。 |
“オール・ホンダ”。それは、Hondaが独立したレース専門の会社を持たないところにも表れている。時代にさきがける技術を生み出すというHondaのポリシーは、レースの現場においても存分に発揮される。事実、NSX-GTプロジェクトリーダーである白井は、CVCCエンジンの研究開発に携わったのち、F1エンジン開発にも参画した経験の持ち主。低公害エンジン、極限のパワーを絞り出すF1エンジンの開発に関するノウハウは、NSX-GTが目標とする“リストリクターで吸気を制限されても、高出力と優れたトルク性能を発揮できるエンジン”の開発に活かされた。
開発を統括する本田技術研究所、車体の開発を担当する童夢、エンジンのチューニングを担当するM-TEC。そのリソースとノウハウがすべてかみ合い、ドライバーやチームのポテンシャルを十二分に引き出すことができたからこそ、2007年のドライバーズランキングの上位4位までをNSX-GTが独占するという結果に結びついたと言えるだろう。 |
|||
積み重ねた経験とこだわりの技術で挑み、結果として“勝てるマシン”にたどりつく。それが、勝利に向かうただ一本の道となる。エンジンをはじめ、排気管やトランスミッションなど、重量物を可能な限り車体の重心に近づけ、かつ低い位置に載せる。ボディは軽く強靭に。エンジンは、パワーと扱いやすさはもちろんのこと、信頼性をも兼ね備えなければならない。はるかなる限界性能と優れたコントロール性を両立するシャシー。最大限のダウンフォースを得ながら、ドラッグを削り込んだエアロダイナミクス。この理想に、実際のレースでどれだけ近づくことができるのかが勝負を分ける。 SUPER GTでは、ベースとなるモデルの素質もものを言う。むろん、NSX-GTのベースとなるのは、世界を驚愕させたスーパースポーツカーNSXだ。レーシングマシンのベースモデルとしてふさわしいことは、言うまでもない。 NSXは1990年に生まれたHondaのフラッグシップスポーツであり、2005年に生産を終えるまで、15年にわたり走り続けた名機である。NSX-GTは、1997年の参戦開始以来、自然吸気エンジンを中心に、優れたドライバビリティとミッドシップレイアウトを活かした高いコーナリング性能を最大の武器としてきた。 参戦当初からNSX-GTプロジェクトに関わっており、NSXの強さを知り尽くしている童夢レーシングチームの中村 卓哉監督は、レギュレーションが大きく変わった今も、その強さの源は“NSXであること”だと語った。 |
「あとから『やっぱり足りないものがあったから付け足そう』というのでは、バランスの取れたパッケージングにはなりませんから」、と中村監督。手描きのデッサンに、あらゆるコンポーネントの配置を含め、アイデアを埋め込んでいく。そしてフレーム、サスペンション、エンジン、電気系統、安全装備…。それらがすべて機能的に、かつ美しく収まるようにレイアウトするのだ。レーシングマシンは、サーキットを走るためのすべての機能を含めた、トータルのバランスが何よりも大切だからだ。 ベーシックな部分に手を加えていこうとすればするほど、ベースとなったマシンの素性が活きてくる。たとえば、タイヤの性能を引き出すための重量配分であれば、軽量なアルミモノコックボディがその設計に自由度を与えてくれる。空力性能には、“スーパースポーツ”と呼ぶに相応しい、シルエットそのものが貢献。レーシングカー全体のパッケージングということを考えたとき、“NSXであること”は大きな武器となりうる。思い切った設計を許容する、懐の深さがあるのだ。 |
|||
 |