
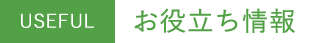 お役立ち情報 March.10.2023
お役立ち情報 March.10.2023 愛犬が食べている草は大丈夫?
草食の理由と危険な植物
愛犬が公園や庭に生えている草を食べた後に、嘔吐をしていませんか。嘔吐は様々な病気の症状としてもよく見られるため、飼い主さんは心配ですよね。犬が草を食べるのは、ストレスや消化不良の解消など、いくつかの理由があります。しかし、草の中には食べると中毒を起こすものや、除草剤、寄生虫などの問題もあるため注意をしなければいけません。
犬が草を食べる主な理由

犬が同じ草を好んで食べる場合や、草に噛みつくことに夢中になる場合など、食べ方や草の種類も様々です。犬が草を食べる様子から、草を食べる大まかな理由が予想できますので、ご紹介します。
ストレスを解消するため
散歩中やおでかけ先で、突然飼い主さんを無視して夢中で草を食べ始める行動は、生活で何かストレスを感じているのかもしれません。犬は寂しさや運動不足を感じたり、生活環境の変化でストレスを感じた時にも、いきなり草を食べ始めることがあります。
また、散歩中に飼い主さんとのコミュニケーションが足りなかったり、ドッグランでほかの犬とうまく遊べず暇になったりした時も同様です。まだ散歩から家に帰りたくない時など、時間稼ぎのために草を食べるといった説もあります。
ビタミンや繊維質を摂取するため
栄養が偏っている、フードの量が足りない、カロリーが不足している場合にも犬が草を食べることがあります。普段の食事で不足しているビタミンやミネラル、繊維質を補給するために犬が本能的に草を食べるといったケースです。
消化不良や空腹を解消するため
犬は消化不良や食べ過ぎ、車酔いなど、胃腸の不調を感じた時にも草を食べます。胃腸の調子の悪さを改善するために草を食べ、胃をチクチクと刺激して消化できない食べ物を吐き、胃腸の負担を軽くして調子を整えます。
また、空腹時など、栄養の不足を本能的に感じた時に、何かをお腹に入れたいと思って食べている場合もあります。
楽しい・好きだから
愛犬が同じような場所で似たような草を噛んだり食べたりしている時は、その草の味を好んで口にしているケースも考えられます。
また、草をくわえて噛み切ることを楽しく感じている時もあります。遊び感覚で草を食べていることもあるため、その場合は体調不良などの問題はありません。草の種類や除草剤が撒かれていないかどうかを確認して、危険がない場所であれば無理に止めずに遊ばせても大丈夫です。
愛犬の身近にある草は大丈夫?
食べてはいけない植物たち

この写真のように花と一緒に記念撮影をしたり、玄関や部屋に花を飾ったりする場合にも、誤って危険な草を口にしないように注意が必要です。犬が食べることで中毒を起こす危険な草には、以下の種類があります。
中毒を起こす危険な草
- ●ツツジ科全般(葉・花):中毒症状・多量摂取による死亡
- ●ユリ科全般:嘔吐・けいれん・狂乱・昏睡
- ●アサガオの種子:嘔吐・下痢・血圧低下
- ●アジサイの葉・つぼみ:嘔吐・めまい・意識障害
- ●スイセンの球根:下痢・嘔吐・中枢神経麻痺・血圧低下
- ●アロエの内部乳液部分:下痢・嘔吐・胃腸障害
ほかにも、様々な毒性のある植物が公園や花壇、道端などに生えています。愛犬が草を食べる時には、毒性のある草に興味を持たないように避けて通ることが大切です。危険な草は犬の防衛本能から食べないことも多いですが、遊んでいるうちに誤って口にしたり、庭に植えてある球根を掘り起こして食べてしまったりするケースもあります。
万が一食べてしまった場合は、愛犬に異変が起きていなくても、できるだけ早く動物病院へ連れて行きましょう。その際、口にした植物の持参と、いつ、どのくらい食べた可能性があるのかを獣医師に伝えましょう。
毎年春は危険な時期でもあります。多数の草花が生え始め、やわらかい新芽や葉に愛犬が興味を持つこともあるでしょう。危険な草と知らずに食べて体調を悪くしたり命を危険にさらしたりする事故も発生しやすいため、より注意が必要です。
危険なのは草だけじゃない!
草に付いているものにも注意

草の種類だけでなく除草剤、昆虫や寄生虫などにも注意しましょう。草には除草剤や農薬が散布されている場合があります。もし除草剤が付いている草を食べてしまった場合には、嘔吐・下痢・けいれん・痛み・かゆみなどの症状が現れます。摂取した除草剤の量が多いと命にかかわる場合もあるため、愛犬が草を食べる場所には十分な注意が必要です。
公園などに除草剤を撒く場合には、住民への告知や張り紙などがされます。愛犬が除草剤を口にしないように、散歩で通る場所に除草剤が撒かれていないか常にチェックすることが大切です。
また、草むらには寄生虫や危険な虫やヘビも潜んでいます。ノミやマダニについては、『どこにいる?犬に寄生する「ノミ」の見つけ方、正しい取り方、症状を解説』を参考にしてください。
また、愛犬が草を食べているわけではないのに、長時間草の中に顔を突っ込んでいる時は、昆虫や爬虫類がいるのかもしれません。ヘビやクモ、ムカデなど毒を持っている生き物もいるため注意しましょう。
草を食べることを
やめさせたい場合の対処法

愛犬が草を食べることが好きな場合には、ペットショップなどで販売している犬が食べられる草を準備するのがおすすめです。自宅で育てた安全な草を食べさせることができます。
ただし、過剰に食べてしまうと胃腸に負担を掛けてしまうため、食べすぎには注意が必要です。また、ストレスや栄養不足、胃腸の不具合などが原因で草を食べている場合には、早めに体調を確認するため動物病院で診てもらいましょう。
愛犬が空腹を感じて草を食べている場合には、野菜を茹でておやつとして与えてみるなど、散歩の時に空腹を感じさせないといった工夫もしてみましょう。犬が食べられる野菜については「犬が食べても良い野菜・ダメな野菜。気になる栄養素や正しい与え方」を参考にしてみてください。
ストレスから草を食べている場合には、飼い主さんが愛犬と一緒に遊ぶ時間を増やすなどの方法で草を食べる癖を改善できます。
また、しつけによって草を食べさせないようにする方法もあります。飼い主さんの「ダメ」の指示が通るようにしたり、落ちている食べ物に興味を持たせなくしたりと愛犬の性格に合わせて対策をとりましょう。
愛犬の生活範囲に注意すべき
草・植物がないか確認しましょう
ストレスや栄養不足、消化不良などの理由で犬が草を食べることがあります。外に生えている草には、食べてはいけない草や除草剤が散布されている草もあるため、気を付けなければいけません。できるだけ外で草を食べないように、普段から対策を取っておくことも大切です。
また、散歩コースや公園、おでかけ先だけではなく、自宅にもこのような植物がないか確認しましょう。
クルマでおでかけをした際に、ドッグランや散歩休憩、到着した先で草を食べる場合には、車酔いをしている可能性がありますので、車酔いをしない対策もしてみましょう。詳しくは「犬が車酔いをする3つの原因とは?症状と対策を知り楽しくドライブをしよう!」をご覧ください。

ヤマザキ動物看護大学 助教
[ 修士(獣医保健看護学)・ペット栄養管理士・CRT ]
/動物臨床栄養学研究室
修士(獣医保健看護学)を取得後、ヤマザキ動物看護大学にて動物看護学の臨床的な実習を中心に担当をする。動物臨床栄養学の教育・研究では、犬の手作り食レシピの作成や犬・猫の肥満の改善をテーマに行っている。
※このコンテンツは、2023年3月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。