 |
|
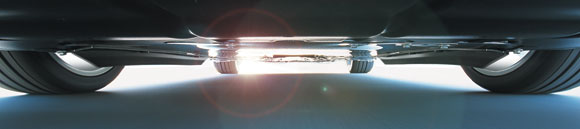
|
||||||
| 空力における揚力を負に、すなわち クルマを路面に押さえ付けるマイナスリフトの実現。 それを前提に、専用タイヤの開発を含めサスペンションのハード チューニングを行い、エンジンの回転フィールを磨き上げるなど 徹底した開発を行ったNSX-R。 その走りの威力はいかなるものか。開発スタッフの主張をまとめてみた。 |
|
| 理論と検証。風洞と実走テストの果てしなきリフレイン。NSXを育て上げてきたHondaの走りのエキスパートが、全身全霊を賭けた情熱のセッティングを行う。それがNSX-Rだ。 「鷹栖テストコースの2コーナーを立ち上がり、下ったところで200km/h出たのはこのクルマがはじめて。そこからフルブレーキすると、強烈な路面の凹凸により、はじめの頃はクルマが跳ねました。だからABSが作動し過ぎて制動距離が伸びてしまいます。いつも一緒にテストを行っているブレーキ屋さんに、そんな極限状態でも効くブレーキをつくって欲しいと無理難題を投げ、解決してもらったのです」 チーフテスターの大久保は、低くハスキーな声で諭すように話した。「今まであそこで200km/h出たクルマはありません。速さを感じましたね」と。 空力パーツとサスペンション、タイヤ、ブレーキ、ボディ剛性にいたるまでの徹底的なバランス取り。各専門スタッフが一同に介し、統合的な視点からテストを繰り返す。タイヤの性能をサスペンションの状態によって変え、またタイヤの仕上がりによってサスペンションにふたたび手を加える。場合によってはボディ剛性までコントロールし、冒頭にあったようにABSのセッティング変更さえ厭わない。これこそ、NSXを知り尽した開発者による高次元の統合的なチューニングである。単に空力パーツを追加し、サスをセッティングしただけでは得られない至福がNSX-Rに宿るのは、当然といえば当然のことだろう。 |
| 「はじめの頃、テスト車に空力パーツだけをつけて、鈴鹿を走ってみたのです。そうしたら、タイプRで想定しているレーシングスピードまで持っていこうとするとどうにもバランスが悪かった。ダウンフォースをやると、またセッティングはゼロスタートになるんだなと実感しましたね」 今回のNSX-Rの開発で、現場を取り仕切ったのは、開発責任者の上原とともにアルミボディやアルミサスペンションの先行研究のときからNSXに携わってきた塚本である。 塚本はまさに上原と一心同体。NSXを立ち上げ、1992年のNSX-Rの開発では、これでもかというほど硬派な割りきりを主張。以来、NSXに携わり続け、1999年にはやはり上原とともにS2000の開発に従事する。担当は車体評価のまとめ役。表情こそ柔和だが、走りに対する信念はかたい。 その塚本がNSX-Rでめざしたのは、サーキットで速く走るという明確な意志を持ったドライバーを感動させる研ぎ澄まされた性能。その狙いは、1992年のNSX-Rのときと変わりない。何しろ、初代のRのあのサスペンションの硬さを要求したのは、彼本人である。「ちょっと硬いじゃないか」という意見にも、「そう思う人が乗るクルマではない」とにべもなく答えたという。目的意識は明確。純粋なる情熱の持ち主である。 |
| 初期のテスト車に、ボディ、サスペンションとも固める方向のセッティングを加え、北海道・鷹栖テストコースに持ち込み、本格的な開発テストがスタートした。 風洞実験、高速テストコースでの実走、理論的な検証からも前後重量配分に等しいバランスのマイナスリフトを付与されたテスト車での走り込みである。 ほぼ方向性が固まった空力パーツを装着し、サスペンションやタイヤ、ボディ剛性などに手を加えながら走りを煮詰めるのだ。もちろん、走りをよくするために空力パーツにも手を加える。その、鷹栖での限界走行でいい性能を出したセッティングが、どういう空力値を出しているか風洞で検証。再度仕様を変えた空力パーツでまた鷹栖の限界走行を行うということの繰り返しだ。 まさに一歩一歩。鷹栖と栃木の間を、NSX-Rに賭けた情熱が飛び交い、走りが研ぎ澄まされていった。 |
|
||||||||||||||||||
| |NSX Press28の目次へ|NSX Pressの目次へ| |
| NSX Press vol.28 2002年5月発行 | |