 |
|
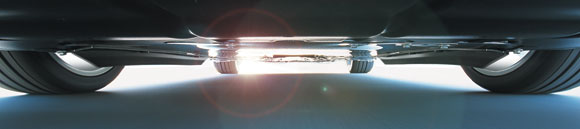
|
||||||
| 高速で路面に吸い付き、コーナリングをしても“車体がズレない”ほどの優れたスタビリティを獲得したNSX-R。筑波のようなテクニカルサーキットのハンドリングも痛快である。この新たなるNSX-Rで鈴鹿を走ったらどうなのだろうか。エキスパートテスターの大久保を中心にそのフィーリングを伺ってみた。 |
| 第1コーナー。ここが一番違いますね。ブレーキングもターンインも段違いの安定感です。テストのために、わざとシフトミスしたときの挙動を試してみるのですが、そういうミス操作をしても急激に滑りだすことはありません。それから、急激にアクセルを抜くような、タックイン的な操作をしてもリアが出ません。これを体験したらきっと驚きますよ。(大久保) ここが今回の空力操安で一番情熱を注いだポイントでもあります。ここでたとえば前を走るクルマが何らかのミスやトラブルで急激に速度を落としたとします。後ろを走っている方がよほどのスペシャリストでない限り、ターンインした大切な瞬間であっても思わずアクセルを抜いてしまうと思うんです。従来なら、それでスピンに至ってたかも知れません。しかし、今回のNSX-Rなら、穏やかに巻き込む感覚です。これならコントロールできます。(新家) |
| S字コーナー。フロントが逃げる感じもなく、リアもしっかり抑えられている。安心してコントロールしていけます。リズムよく決まった時の感動の高さが違うと思います。(大久保) 入力通りクルマが正確に反応してくれる感じです。つまりオン・ザ・レール感覚のリニアな操作フィールをS字で体験できると思います。(新家) |
| ダンロップコーナー。この駆け上がりの高速左コーナーで、わずかにアクセルを戻したりして、クルマを横に向けるオーナーを何人か見かけました。でも今度のNSX-Rなら、ここはもうひたすらビターッですね。安心感が違います。安定領域で走る感じです。(塚本) |
| ヘアピンコーナー。ここは回頭性を高めたセッティングが活きますね。適正な荷重移動を行い、ステアリングを切り込むと、スッと気持ちよく曲がり、リアもきちんと追従してくれます。ここからの立ち上がり加速は、3.2リッターのNSX-Rならではですね。(塚本) ヘアピン後。ここの駆け上がりの右高速コーナーで、テストにおいて全開で5速まで入ったのは、このNSX-Rだけですね。それくらい安心して踏み込んでいける感じです。そして、ブレーキの安心感が大きい。スプーンへの進入はできるだけ横Gを消したいのですが、どうしても少し残ってしまいます。その状態でも安定してブレーキングできるので5速まで入れられるわけです。鷹栖で難題を克服しましたからブレーキは。“ブレーキ屋さんありがとう”という感じです(笑)。(大久保) |
| スプーンコーナー。リアが意図的にやらないと出ないくらい。ものすごく安定しています。試しにわざと滑らせてみてもすごく穏やか。2つめの切り増すところも常に舵が効いている感じで安心感があります。(大久保) スプーンは2つめの、ステアリングを切り増すコーナーの安定性にかなり照準を合わせました。この世界的にも難易度の高いコーナーを、ドライバーのスキルが高いことが前提ですが、攻めても修正舵なしでいけますね。(新家) |
| 130R。ブレーキングしてターンインを開始してクリアするまで、常に安定しています。弱アンダーをキープしてくれ、より安心して走れます。(大久保) |
| 総評。鈴鹿という世界的にもテクニカルで高速なサーキットを攻めても、スタビリティが高いので疲れない。これが一番大きいと思います。その分、走り終わった後の充実感も高まります。あと、周回を重ねても、ブレーキ、タイヤともに性能低下しにくいのがいいですね。 |
 |
大久保によると、初代のNSX-Rよりも鈴鹿で4〜5秒ラップタイムを縮められるということです。もちろん、このタイムはドライバーのスキルあってのことですが、これだけ差を築ければレースではまったくバトルにならないくらいのレベルですね。 しつこいようですが、速さも、優れたスタビリティも、洗練されたドライバビリティもまったく違うレベルのクルマと感じることができます。マイナスリフト獲得によって生まれ変わったNSX-R。この感動をぜひみなさんにもお感じいただきたいですね。(塚本) |
|
|
||||||||||||||||||
| |NSX Press28の目次へ|NSX Pressの目次へ| |
| NSX Press vol.28 2002年5月発行 | |