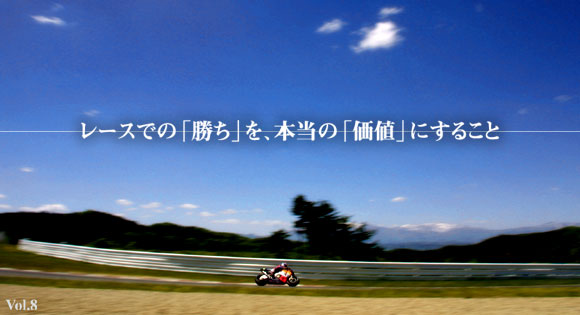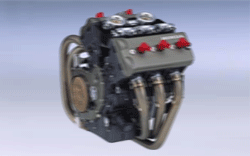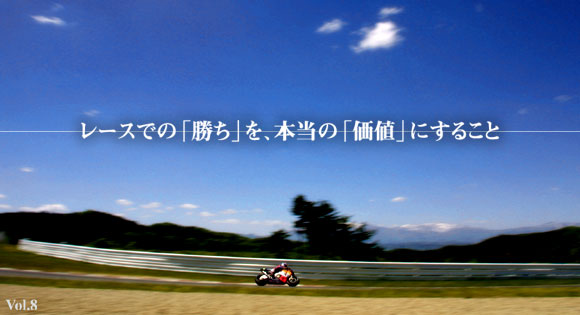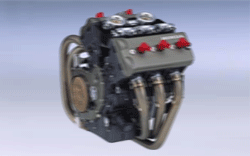|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| 開発初期のイメージイラスト。何10枚ものスケッチにスタッフ全員の熱い想いが込められ、プロジェクトは次第に具体的なカタチとなっていった |
|
 |
成功裏に2002年シーズンを終えたRC211Vプロジェクトは、現在2003年に向けてさらなる開発と研鑽の時を迎えている。このオフこそ、来るべきシーズンを決定づけるもっとも重要な時期であるのは言うまでもない。
「2002年にMotoGPが始まる前、私たちはそれ以前の1年間をまるまるRC211Vの開発にかけました。いや、具体的なブツの開発と言うより、MotoGPで勝てるマシンとはなんぞや?を考え抜いたと言った方が正しいかもしれない。とにかく検討して検討して検討しつくした。レーシングマシンとは何か?、レースとは何か?、速いバイクとは何か?、そういった事を考えて考えて考え抜いた。こうした時間があったからこそ、RC211Vがあの姿で産まれたんです。
走り始めは他より遅かったですよね。でも全然焦ったりしなかった。だって、考えた量が違うぞっていう圧倒的な自信が私たちにはあったから。もうここまで考えたんだから、カタチにして大丈夫っていう自信に基づいてモノが出来上がってきたわけです。 |
 |
|
エンジンをV5に決めたのが2000年の9月でした。そして初めてそのエンジンを回したのが2000年の仕事納めの日12月28日。一般のサーキットでのシェイクダウンが2001年の4月10日、菅生でしたね。この時点で、自信が確信になったというか、考え抜いた内容が間違っていなかったという確認がとれたわけです。もう、この時点でMotoGPが始まって欲しいくらいでしたよ。僕たちの考え抜いたMotoGPマシンを見てくれ!って」
Honda社内の開発担当者たちにとって、まったく新しいグランプリマシンの開発に携わることは、ごくまれな経験でもある。レースごとに新機種が送り込まれた…と言われる60年代のレース活動は特別であるとして、79年のNR、83年のNS、そして84年からのNSRと、機種で言えばグランプリ最高峰のマシンはそれほど多くの種類を数えるわけではない。特に84年からのNSRは、20年近くにわたって基本スタイルを変えずに熟成を続けたマシンでもある。 |
|
 |
| 2001年4月10日、菅生。RC211Vが初めて一般の前に姿をあらわした記念すべき瞬間。それはまさに、新しい時代がスタートした瞬間でもあった |
|
 |
|
「まったく新しいモノを創る…そこにはやっぱり、もの凄いエネルギーが集まるんです。だって、バイクが好きでレースが好きで開発を仕事にしてるといっても、まったく新しいグランプリマシンを創る仕事なんて、滅多に回ってくるもんじゃない。自分がその仕事についている時期に、新生MotoGPが産まれる。その巡り合わせは、もう神様に感謝したいぐらい幸せなことです。
そうなると、これはもう半端な気持ちじゃないわけです。やりたい事が山ほど出てくる。アイディアのデパート状態ですよ。そうやって考えて考えて考え抜く。MotoGPだけじゃなく、バイクの基本から考え抜く。そうした時間が1年間あったということなんです」 |
|
 |
| 新生MotoGP、そしてまったくのニューマシンRC211Vの開発に関わったスタッフの情熱とエネルギーの総和が、2002年の好成績を産み出した |
|
 |
 |
 |
|
 |
| セパンのテストで、RC211Vをモトクロッサーの様に自在に乗りこなすハイデン。まさにライダーの思いどおりになる超高性能が発揮される瞬間 |
|
 |
そして彼らが導き出した答えは、ごく自然な言葉に集約される事になる。
「ライダーが乗ってレースするんだから、結局は人が扱う道具なんだから、使いやすい、コントロールしやすいモノでなくてはいけない…それが答えなんです。ライダーが欲しいと思う性能はすべてある。ライダーが欲しくないモノはすべて排除する。つまりそういう事なんです。決して数値に置き換えられるモノではない、とても曖昧な目標なんですけどね。
そして『誰かスペシャル』ではないマシンづくり。誰が乗っても速く走れる。それが『本当に速いマシン』なんだと思います。この点は、2002年シーズンの後半に複数のライダーがRC211Vに乗って、充分にそれを実証してくれたと思います。
だから、2003年は凄いことになるでしょうね。ロッシの速さは、今のところずば抜けているかもしれない。でも、さらに多くのライダーがRC211Vに乗ることになって、彼の独走を許すようなレースはなくなるに違いない。レース全体も絶対に面白くなるはずです。そこで初めて、RC211Vの本来の性能や価値を皆さんに楽しんでいただける事になると思っています」 |
 |
|
そして開発陣は、RC211Vの存在にさらなる意味を込めている。
「簡単に言えば、RC211Vで得た技術は、皆さんの手元に届くと思います!っていう事なんです。これは、いきなりV5エンジンの市販バイクが出ます…とか、そういう事ではなくて、それは、もしかしたらスクーターのどこかに生きているかもしれない。もちろんスーパースポーツに具現化されるかもしれない。オフロードに応用されるかもしれない。ビジネスモデルがより良くなるのかもしれない。RC211Vの開発の中で培われた『技術』が必ず一般の市販車に活かされる…という事なんです。
RC211Vのレースでの『勝ち』を、Hondaのバイクに乗る皆さん全員の『価値』にしてこそ、初めてRC211Vの存在が評価されると考えているんです」
グランプリの最高峰MotoGPのチャンピオンマシンであるRC211Vが、一般市販車にもたらす無限の影響と技術的フィードバック。そこには想像を超えたリレーションシップが存在することになる。 |
|
 |
| GPマシンから得られる技術要素は無限の拡がりをもつ。さらにレースは、その限りない厳しさの中で究極の人材育成という大きな意義をもたらす |
 |
 |
| RC211Vの傍らに立つ河島喜好現最高顧問。河島が1959年のマン島でチーム監督を務めた時代から、GPマシンと市販車は常に密接な関係にあった |
|
 |
|
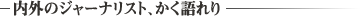 |
|
|
 |
|
さて、RC211Vと一般市販車のリレーションシップはいかなるカタチで具現化されるのか。それは今後の大きな楽しみとしていただくとして、RC211Vとはそもそもどの様なレーシングマシンであるのか。 |
|
|
 |
|
本稿では前回、チャンピオンを獲得したロッシを筆頭とするMotoGPにおけるRC211Vライダーの声を掲載した。これはまさにグランプリ最高峰のライダーによるインプレッションとなるが、今回は内外のジャーナリストによる試乗インプレッションを通して、RC211Vをより一般的な視点から理解していただこうと思う。
もちろん、個々のライダーにレース最前線のように充分なセットアップをおこなったわけではないし、マシンのキャラクターを存分に味わっていただくだけの試乗時間がなかったことを前提に、以下の試乗インプレッションをお読みいただきたい。グランプリライダーとはまた違った視点で解説されるRC211Vに、Hondaモーターサイクルの夢と未来が凝縮されていることに間違いはない。
■ヨーロッパのジャーナリスト試乗会におけるコメント
■日本のジャーナリスト試乗会におけるコメント |
|
 |
| ロッシ、宇川、加藤、バロスによるRC211Vインプレッションは、前回「Vol.7」に掲載。それぞれ違った捉え方と、全体的な共通点が興味深く読みとれる |
|
 |
 |
 |
|
 |
| 2003年1月、Hondaはセパンでのテストを開始。ロッシ、ハイデン、加藤、ジベルノー、宇川、玉田、そして伊藤真一が各種のテストを行った |
|
 |
現在、RC211Vは2003年のレースシーズンを目指して研鑽の日々を積み重ねている。さらなる進化の主たる方向として「制御の応用」をあげることが出来るだろう。2002年モデルで実用化と実戦化を果たした各種の制御技術を、Hondaは2003年モデルで第二のステージへと導こうとしている。
人が扱う道具としての使いやすさ。誰にでもコントロールしやすい超高性能。バイクが持つ可能性の究極を追い求める具体的な存在として、RC211VはMotoGPとバイクそのものの先頭を走り続けている。
Hondaは、自らを鍛え、そしてグランプリとモーターサイクルそのものの未来を切り開くため、誰よりも果敢に挑戦を続ける。Hondaがもし、世界最高峰のモーターサイクルメーカーと呼ばれるなら、それは世界一の「挑み続けるスピリット」を持った集団であるからに他ならない。 |