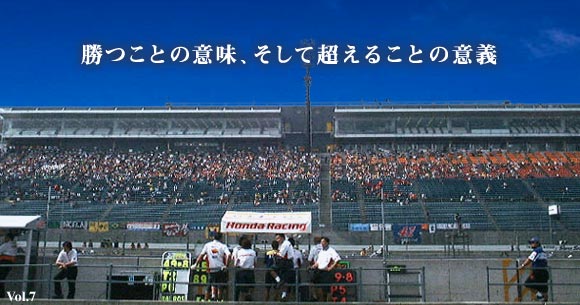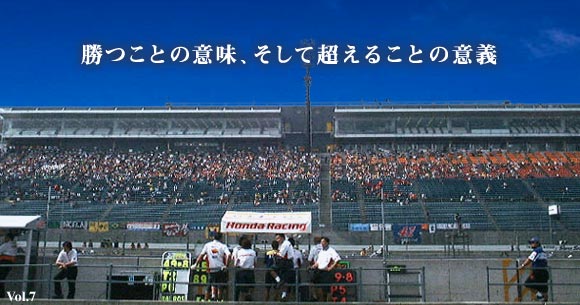|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
参戦初年度のRC211Vを駆り、2002年MotoGPクラスのタイトルを決定したロッシ。そしてHondaはパシフィックGP/もてぎでMotoGPクラスのコンストラクターズタイトルを獲得し、RC211Vは圧倒的強さで当初の目標を達成する成績を残している。
しかし、RC211Vの開発を担ったプロジェクトリーダーは、こうも言う。
「確かにRC211Vは、素晴らしい性能を発揮しています。しかし、4ストロークRC211Vが、本当に2ストロークNSR500より優れているのか。NSR500を超えたのか、私たちはまだそれを証明出来てはいないんです。
|
|
 |
| 2002年の覇者ロッシ、南ア優勝の宇川、もてぎPPの大治郎…のRC211V三人衆 |
|
 |
|
ロッシは、2001年シーズンにNSR500でチャンピオンになりましたが、彼はこの時11勝をあげています。私たちは、彼が4ストロークRC211Vに乗って、その11勝を上回る成績をあげてこそ、はじめてRC211VがNSR500と同等あるいはそれ以上の性能を持ったと証明できるんです。その意味では、まだRC211VはNSR500を完全に凌いだとは言えない」
確かに、マシンの実力を『タイトルの獲得』というシーズン総体の基準で判断することは難しい。1シーズン中の優勝数/優勝率…これは、その年のマシンを客観的に計るひとつの要素となる。
|
|
 |
| ロッシは昨年に続きGP最高峰2連覇。500最後の年とMotoGP初年度の両方を制した |
|
 |
|
2002年のオーストラリアGPが終了した時点で、RC211Vは15戦中13勝で勝率86.7%。残り1戦を勝利したとしても16戦中14勝でその勝率は87.5%にすぎない。Hondaは500ccクラスにおいて、過去に1998年の14戦中13勝/勝率92.9%、さらには1997年の15戦全勝/勝率100%という数字をNSR500によってマークしている。
「ロッシが、2001年の自分の勝ち数を超えること。そしてシーズンの勝率でもRC211Vがこれまでの記録を超えること。これがあってはじめてRC211Vが『過去』を超えたことになると考えます」
もちろんこれに加えて、過去のラップタイム/レースタイムの更新が成されているか、マシントラブルの回数は…。デビューシーズンだから…などという甘い基準は、そこには存在しない。徹底的に『過去』を上回り未知の領域に踏み込むことが出来なければ、そこに『成功』の二文字はないとさえ、RC211Vの開発陣は言い切る。
シーズンの終盤、総合的な評価が下される時期をむかえた開発/運営スタッフは、一般的な評価に対してはるかに厳しい目でRC211Vをとらえている。
「Hondaは、ライバルに対して負けず嫌いなのではないんです。Hondaは、自分たちのしてきたことに負けるのが嫌なんです」
ほどなく、新生MotoGP初年度も幕を閉じる。予想を上回る戦闘力と成績を残したRC211Vとその開発陣は、すでに二年めに向かってさらなる飛躍を目指している。NSRを超えるRC211V、2002年のRC211Vを超える2003年のRC211V。その要求項目は、さらに高次元へと研ぎ澄まされていく。
|
|
 |
| 1997年は、ドゥーハン12勝、クリビーレ2勝、岡田1勝で15戦全勝を達成している |
|
 |
|
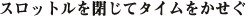 |
|
|
 |
|
「例えば鈴鹿のコースでいうと、スロットル全開の区間が25%、全開と全閉の中間のパーシャル区間が50%、そしてスロットル全閉が25%くらいなんです。
V5エンジンで、全開とパーシャルの区間でのアドバンテージを持てることはわかった。それでは、残り25%のスロットル全閉の区間でさらにタイムを稼ごう…と考えたわけです。それができれば、コース距離の100%でライバルを凌ぐことが出来る。
ライバルの皆さんも、減速区間のコントロール性の向上にやっきになっていると思います。簡単にいえば、エンジンブレーキをどうするか…ということですね。開発を担当した立場から言えば、このエンジンブレーキのコントロール性をもっと高いレベルにもっていってから実戦部隊に引き渡したかった…と感じています。
|
|
 |
| コースの1/4の全閉区間でのタイム向上…そこにタイム向上の大きな鍵がある |
|
 |
|
エンジンブレーキが効きすぎるとか、エンジンブレーキがかかることがいけないとか、そういうことではないんです。ライダーの要求にリニアに反応するコントロール性の追求…それが重要なんです。
かつてミック・ドゥーハンは『エンジンブレーキはゼロでいい。ブレーキングはボクが100%コントロールするから』と言ったことがあります。つまり彼らは、自分がすべてをコントロール出来るマシンを要求するんです。
スロットル全開で加速するのも、ブラックマークがつくようなハードブレーキも、全部自分のコントロール下でやりたい。自分のコントロール下でなら、マシンが真横を向いたって彼らは走りを楽しんでいる。『滑っている…のではなくて、滑らせている…』が、彼らの要求なんです
現状のRC211Vでも、ロッシなんかは派手なリヤスライドでコーナーに入っていく。同じようなスライド量でもコントロールできずに転んでしまうマシンもあるわけですが…まぁそれは余談として、そのスライドをもっともっとコントローラブルにしてやりたいわけです。
ライダーが自由自在に、モトクロッサーでも走らせてるみたいに、マシンがどっち向こうが平気、いつもコントロール下、何やっても楽しくてしょうがない…そんなマシンが理想なんです。
その点で、RC211Vのエンジンブレーキはまだそこまでのリニアリティを実現出来ていない…ということなんです」
|
|
 |
| ライダーは、従来より次元の高いエンジンブレーキのリニアリティを求めている |
|
 |
|
スロットルを閉じている時にタイムをかせぐ…この、一見矛盾する発想もまた、RC211Vが練り上げてきた独自のコンセプトの一端を明確にあらわしている部分だろう。
「エンジンブレーキに関しては、メカニズム的に、エレクトロニクス的に、そしてFI(燃料噴射)の部分でもリニアリティを上げる工夫をしているところです。
2003年は、さらに多くのライダーがシーズンを通してRC211Vに乗ることになる。これまでになかった要求もいろいろ出てくるでしょう。その点ではもっともっと忙しいシーズンになる。でも、それだけマシンの熟成は高い密度で進められることになる。
ロッシも、これまで以上に多くのライバルたちに厳しい戦いを挑まれるわけです。これまで100の力で勝ったレースがあったとしたら、来年のロッシは110とか120を出さなければいけなくなる。そうなればRC211Vに対する要求もさらに高くなるはずです。それが、ライダーにもマシンにも良いことなんです」
|
|
 |
| 2003年は、ロッシ/宇川に加えバロス/大治郎が通年でRC211Vを駆ることになる |
 |
 |
| そして来年最大の注目株ニッキー・ハイデン。ついにアメリカンがRC211Vを駆る |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
確かに、これまでRC211Vを駆ったライダーはそれぞれにRC211Vをとらえている。そしてその中で一貫した意見は、その「乗り易さ」に集約されている。 |
|
|
 |
|
「RC211Vのパワフルさ、アクセレレーションを含めた扱い易いエンジンキャラクターには満足している。特にハイスピードコーナーでのRC211Vは、ベリーファンだね。ボクをとても楽しませてくれている。
リヤのスライド特性は最初はなじめなかったけど、今はそれを楽しんでるよ。特にリヤを流しながらコーナーに突っ込んでいく区間は(もちろんきちんとセッティングがでている時の話しだけど…)一番エキサイティングで楽しい部分。パワーボートの感じにもちょっと似てるね。
ブレーキングにも大きな問題はない。コースによってはタイヤとのマッチングが難しい事もあるけれど、チームはそれをうまく克服する力を持っているからね
最初にテストで乗った時は、4ストのアドバンテージはすぐに理解したけど、2ストの方が刺激的だし好きだった。でも今では4ストの良い所悪い所や乗り方も理解できたし、NSRもRC-Vも、楽しさの種類こそ違うけど、同じくらい楽しいと思ってる。
RC211Vの一番好きな所は自由自在にマシンをコントロールできる扱い易いエンジン特性と、スライド特性。ちなみにNSRの方はピンポイントのコントロールを要求されるシビアさが、逆にチャレンジングで好きだったっていう部分もあるけどね。
いずれにしても、一緒にチャンピオンを獲ったマシンには、いつも特別な愛情を感じるんだ」=バレンティーノ・ロッシ |
|
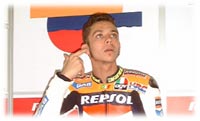 |
 |
|
「ミニバイクからNSR250に乗り換えた時よりも、NSRからRC211Vに乗り換えた時の方がインパクトがあった…それくらい強烈なマシンでしたね。
速い。とにかく速い。今まで乗ったどのマシンより、インパクトがある。加速と伸びに関して、これまでにあんなマシンはなかったでしょうね。
でも乗り易くて反応が分かり易いから、余計なところに神経を使わないでレースに集中出来る。それにしても、あの乗り易さはGPマシンとは思えないくらい。ナンバーつけて公道走っても充分に面白く、そしてとてつもなく速いでしょうね。もちろん全開には出来ないでしょうけど…。
特に大きな要望はないんですが、今は開け始めのパワーの出かたを緩やかにする方向でセッティングを進めています。」=宇川
徹
|
|
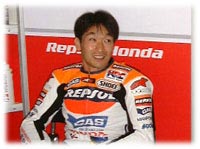 |
 |
|
「チェコ前にポジション合わせをしただけで、ポンと乗れちゃいました。いろいろいじるとこんがらがっちゃうから、なんにもいじらないでそのままレースしました。
乗って最初の印象はやっぱりエンジン。やっぱりパワーが全然出てるし、凄いトルクが下の方からある。でも扱い易いし、加速区間からストレートでは絶対アドバンテージがあるから、レースでは有利だと思う。
リヤサスの、ちょっと今までと違うフィーリングにはもう慣れたんだけど、まだポジションが完全に自分に合わせ切れてなくて、これからセットアップを詰めて行こうと思ってます。
進入でリヤが大きくスライドしてるのは、コントロールは出来てるんだけど、狙ってやってるのとはちょっと違う。人によっては乗れてくるとスライドなんかが大きくなる人もいるけど、ぼくは乗れてる乗れてないの基準は、タイムでしか考えない。自由に振り回せて気持ち良く乗れてても、タイムが伸びなければ、それは乗れてないってことだと思うから。
そういう意味で、ぼくが今まで乗った中でのベストバイクは、去年のNSR250。本当に全部を把握できて、全部自分でコントロールした動きをさせられてた。
でもRC211Vは、まだまだセットアップが詰まってない状態だし、しかもあれだけ凄いパワーや4ストのエンブレなんかを差し引くと、今でもかなりいいと思うし、すごく楽しみ。残りのレースとシーズンオフに問題点を克服して、2003年は開幕から勝ちを狙っていきます」=加藤
大治郎
|
|
 |
 |
|
「もてぎの金曜日に初めてRC211Vに乗って、すぐに90%の力を出せるマシンであることが分かった。そしてRC211Vに乗って二日目の土曜日に出したタイムが予選5番手。これには自分でも驚いている。
レースはもちろん初めてだったので、タイヤの全般的な耐久性や、タイヤがたれてきた時にどんな挙動を示すかを注意しながら走った部分があったんだ。バトルで100%を超えた時の経験があのマシンにはなかったし、本当のレースを走り抜くのは初めてだったからね。
でも、終盤ロッシに抜かれた時は、すべてを忘れて110%の走りになっていたね。そしてRC211Vもタイヤもはまったく問題がなかった。さらに、なんと最終ラップにファステストラップ(ワォ〜これにはビックリ!だ)を記録して、優勝さ。
RC211Vの戦闘力の高さと乗り易さは素晴らしいの一言。来シーズンはこれまで以上に、勝ちやタイトルにこだわったレースが展開出来ると思っている」=アレックス・バロス
|
|
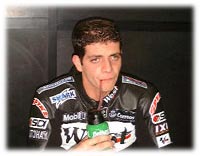 |
 |
|
すべてのライダーが口を揃える「パワフルであり、乗り易く、扱い易い」その点に、RC211Vのパフォーマンスは集約されている。それはつまり、ライダーが要求するモノをコントローラブルに100%発揮出来る能力であり、ライダーに神経を使わせずレースに集中出来ること、そしてまた走ることが楽しいマシンであることを指している。 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
しかし、レースの世界に絶対的な存在はない。シーズンが進むにつれてライバルたちも戦闘力を向上させていることは確かだ。HRCチーム監督の言葉は、シーズン終盤の戦局を冷徹に語っている。
「開幕から序盤戦…そうですね、第4戦のフランスGPくらいまで、RC211Vには完全なアドバンテージがあったと思います。しかし、その後ライバルもどんどん力をつけてきた。もてぎの時点では、まったく横一線、局面によってはライバルの方が優れている部分も出てきている。私たちはそう認識している。非常に緊迫した情況…それがいつわらざる本音です」
その言葉を裏付けるかのように、マレーシアGPでは今シーズン初めて、RC211Vがライバルに競り負けるという結果が残された。もてぎでコンストラクタータイトルを決定し、RC211Vが成功裏にシーズンを終えようとしていることは確かだが、開発と熟成の手が緩められることはない。
「歴戦の雄であるヤマハさんが、このまま終わるわけはない。それは充分に分かっています。2003年は、さらに多くのメーカーがMotoGPに参加してきます。でも、もちろんライバルの皆さんを意識しますが、それ以上に我々は自分たちを超えることに一所懸命です。
|
|
 |
| ライバルの猛追を背中に感じつつ、RC211Vのさらなる性能向上が進められている |
|
 |
 |
|
NSRを超えること。前のレースのRC211Vを超えること。2002年のRC211Vを超えるRC211Vを、2003年に送り出すこと。
つまり、勝てば勝つほど、チャレンジングでなければならない。Hondaは、自らをそう定義づけているんです」
2002年の膨大なレースデータを得た開発陣は、ほどなく『初めてのシーズンオフ』を迎えようとしている。つまりそれは、2002年のRC211Vを超えるマシンを作り上げるという、過酷極まりない作業がスタートすることを意味している。 |
|
 |
| Honda初代GP監督(現最高顧問)の河島喜好以来、挑戦の歴史は連綿と続いている |
|