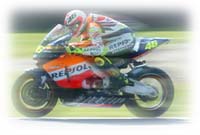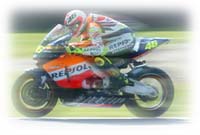|
「あらゆる部分でNSR500を否定すること…それがRC211Vだったのです」
否定する…という言葉が誤解を招く恐れがあるとするならば、あらゆる部分でNSR500を超越する概念を打ち立てること…それこそが、RC211Vの存在意義でもあった。
2ストロークならではの鋭角的にピーキーなエンジン特性に対抗する、コースの各所でライダーがシビアに要求するパワーを過不足無く発揮出来る能力を備えたエンジン。
コース1周の間にわずかな区間しか存在しない最高速付近より、コースの大半でライダーに自由度を与えコントローラブルなライディングを可能にするカウル形状。
サスペンションとしての基本性能はもちろん、理想的なフレーム剛性の設定に大きく影響するリアサスからの荷重分布を有利にするユニットプロリンクサス。
V型5気筒エンジンを「成功の起点」とする、これらのコンポーネントの組み合わせが、RC211V総体としての性能あるいは戦闘力を導き出す大きな要因となっていることは確実だ。
「自分たちが長年かかって完成させたNSR500という到達点をもやっつけようとするのですから、我々Hondaはなんて負けず嫌いなんだろうと思います。ライバルに負けたくない以前に、NSRに負けたくない。既存のモノに負けたくない。昨日の自分に負けたくない。手に負えない程の負けず嫌いです」
負けず嫌いは大抵の場合、相当な意地っ張りでもある。ただこれは、旧態に執着する頑固とは、かなり意味が違う。まず、過去を否定してみる。既存の概念に立ち向かってみる。そこにはかならず新しいアイディアや解決方法が生み出される。そしてその可能性に向かってがむしゃらに突き進む。
|