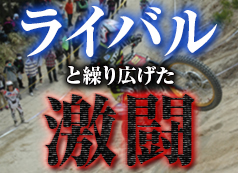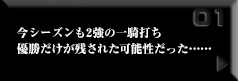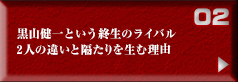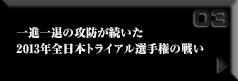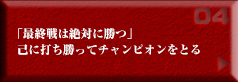モータースポーツ > 全日本トライアル選手権 > ライバルと繰り広げた激闘 > RIVAL STORY 02
黒山健一という終生のライバル
2人の違いと隔たりを生む理由
小川と黒山選手の2人は20年来のライバルであり、友人でもある。
1976年生まれの小川は、1989年に自転車トライアル世界選手権のミニメットクラス(13〜14歳クラス)でランキング5位、翌90年には同クラスで世界チャンピオンを獲得した。
一方の黒山選手は、1978年生まれ、87年と88年に自転車トライアル世界選手権のプッシンクラス(10歳以下)でチャンピオンを獲得し、89年と90年には11歳〜12歳クラスのチャンピオンとなった。
2人は黒山選手の父である一郎氏(1976年、81年の全日本トライアル選手権チャンピオン)が80年代後半に主宰した“ブラック団”の出身だ。ブラック団とは、トライアルの世界チャンピオンを獲得できるライダーを育成するため、期待できる才能を持った子どもたちを集めて、自転車トライアル世界選手権へ挑戦した伝説的な集団である。
このグループには2人のほかに、藤波貴久(Honda、2004年トライアル世界選手権チャンピオン)、野崎史高選手(ヤマハ、トライアル世界選手権のジュニアカップチャンピオン)、田中太一選手(2009年に活動休止)らが所属していた。このようなメンバーの中で最年長だった小川は“兄貴分”としてグループのまとめ役だったという。
「ブラック団では“勝つためにはどうすればいいか?”どころか、“生きるためにはどうすればいいか?”ということさえ学びました(笑)。自分にとってなによりも大きかったのは、ヨーロッパでバイクの世界選手権を直にいくつも観戦できたことです。世界のトップライダーたちを見て“自分もあんなふうになりたい!”という、強いモチベーションを育むことができました」
そして現在、このブラック団出身のライダーたちが約20年にわたって、日本のトライアル界の頂点に君臨し続けているのである。


小川友幸が国際A級(IA)に昇格以降の全日本トライアル選手権のランキングトップ3
| 西暦 | 1位 | 2位 | 3位 | 小川友幸を中心とした主な動向 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | P.クトゥリエ | 小川友幸 | 成田 匠 | 小川が国際A級(IA)に昇格 |
| 1994 | 成田 匠 | P.クトゥリエ | 藤波貴久 | |
| 1995 | 藤波貴久 | 成田 匠 | 田中善弘 | 小川は世界選手権参戦(ランキング18位)のため不出場 |
| 1996 | 黒山健一 | 三谷英明 | 田中善弘 | 小川は世界選手権参戦(ランキング15位)のため不出場 |
| 1997 | 黒山健一 | 小川友幸 | 成田 匠 | 小川が国際A級スーパークラス(IAS)参戦 |
| 1998 | 藤波貴久 | 黒山健一 | 小川友幸 | |
| 1999 | 藤波貴久 | 小川友幸 | 田中太一 | 黒山選手は8位 |
| 2000 | 藤波貴久 | 黒山健一 | 小川友幸 | |
| 2001 | 藤波貴久 | 黒山健一 | 小川友幸 | |
| 2002 | 黒山健一 | 小川友幸 | 渋谷 勲 | 小川がベータからHondaに乗り換える |
| 2003 | 黒山健一 | 小川友幸 | 田中太一 | |
| 2004 | 黒山健一 | 小川友幸 | 田中太一 | |
| 2005 | 黒山健一 | 田中太一 | 小川友幸 | Hondaの4ストロークRTL250Fがデビュー |
| 2006 | 黒山健一 | 小川友幸 | 田中太一 | |
| 2007 | 小川友幸 | 黒山健一 | 野崎史高 | |
| 2008 | 黒山健一 | 小川友幸 | 野崎史高 | |
| 2009 | 黒山健一 | 小川友幸 | 野崎史高 | |
| 2010 | 小川友幸 | 黒山健一 | 野崎史高 | |
| 2011 | 黒山健一 | 小川友幸 | 野崎史高 | |
| 2012 | 黒山健一 | 小川友幸 | 野崎史高 | |
| 2013 | 小川友幸 | 黒山健一 | 野崎史高 | Hondaの新型RTL250Fがデビュー |
世界で活躍する藤波に続くのが黒山選手と小川であり、上の表を見れば2人の実力は全日本でも飛び抜けていることが分かるだろう。同時に、2人は子どものころからともに生活し、競い合い、切磋琢磨してきた関係だけに、お互いの性格やライディングの長所や短所を知り尽くしている。
それゆえに、競技中に妙な駆け引きをする必要もなく、ストレートに勝負に打ち込める点で、2人の間では技術と心身による純粋な競い合いが成立しているといってもいい。そして、わずかなミスや取りこぼしがその勝敗を分けてきた。実際には2人の技術的な実力は拮抗していて、微妙である一方で、チャンピオンと2位という大きな差を生んできたのは、2人の置かれている環境と競技に対するマインドの違いだと考えられてきた。
小川は、HRCクラブ TEAM MITANIに所属し、HRCの開発テストにも携わっているが、専らトライアル世界選手権用のファクトリーマシンの開発テストが主体で、自らが全日本で乗るマシンは、市販のRTL250Fをプライベートでチューニングしたものである。
対する黒山選手はヤマハのファクトリーサポートであり、マシンは市販のスコルパTYS250Fにヤマハ本社で手を加えたものである。このマシンはDOHC5バルブエンジンを搭載しており、小川のマシンに対しパワー面でアドバンテージを持っているとだれもが認めるところだった。
ここ数年の全日本は、高回転の伸びが必要なパワーセクションが多い傾向にあるため、マシンにはパワフルな出力特性が求められている。この点で黒山選手が優位な状況であったと考えられる。
また小川は開発テスト以外にも、毎週のようにトライアルスクールの開催やイベント出演を行い、これらに時間を費やしており、全日本のための練習を行うための満足な時間は限られている。
逆に黒山選手は、一年を通じて競技に集中した生活を送っている。そのトレーニングは、まさにプロアスリートのレベルであるというから、小川と黒山選手の練習量の差は大きいはずだ。


冷静でクールなマインドを熱くかき立てたもの
2人はマインドからくる走りのスタイルも大きく異なる。
小川は、あまり口を出さず子どもの自主性に任せる父親の指導のもと、自分の思うように自由にライディングを追求してきたという。その結果、完成度の高い走り、芸術的なまでに美しいライディングを求める傾向が強く、勝負のかかったトライでもクリーンを狙ってあえて難易度の高いラインを走るとさえ評されている。
そのライディングは7度の世界チャンピオンになったジョルディ・タレスから「日本人ライダーの中で最もセンスがあり、世界でトップを狙える可能性がある」と絶賛されたほどだ。ただその反面、失敗すると成績が大きく乱れる可能性もあり、それが競技結果に大きな波がある原因の一つでもあった。
一方の黒山選手は、“トライアルの鬼”とさえ評された父親の指導のもと、徹底的にトライアルを仕込まれてきた。そして、“どんな状況でも勝つ”という、勝負に対する強い意欲を持っていて、足を着いてでも、体勢が乱れてでも、勝つために手段を選ばないタイプだ。
さらに黒山選手は、父と弟が大会中のサポートを務めているのも大きな強みと思われてきた。ただし、ここ2年間ほどは黒山選手の父親が現場を離れており(黒山選手が今シーズン2連敗したあとの第5戦から復帰)、この間に黒山選手のライディングスタイルが変わったとも言われている。
これに対して小川をサポートする役(マインダー)は、田中裕大が務めてきた。彼の存在があったことも「チャンピオン獲得に大きく貢献した」と関係者は口にする。小川も彼の存在を高く評価しており、「マインダーとして世界一だと思っています。走行ラインの指示と残り時間の読み上げがマインダーの主な役割ですが、彼と組んでからは一度もミスがありません」と言う。
ライダーとマインダーとの間は、互いの齟齬やマインダーのミスが原因で競技中に激しい言い争いになることも珍しくない中で、小川と田中の信頼関係は特筆すべき要素だ。このことが今年のチャンピオン争いに影響を与えたであろうし、今シーズンのサポート面における小川と黒山選手の対比では、小川が有利だった場面もあるはずだ。
このような背景から2人の微妙な差は生まれ、ケガや不測のトラブルがなければ“黒山選手有利”という下馬評がここ数年は定着していたのである。その流れを変え、小川が3年ぶりにチャンピオン獲得を実現できた決定的な要素は、第3戦から投入されたHondaのニューマシンである。
このマシンは世界選手権向けに小川自らが開発に携わったもので、特に新設計のエンジンは排気量拡大とツインプラグ化によって、ほぼ全回転域でのパワーアップと理想的な出力特性が実現されている。
「小川は冷静でクールな性格ゆえに状況判断に長けており、勝てないと判断すれば、あっさり身を引くようなところがある」と、昔から彼をよく知る者は言う。その小川をして「勝てる」と判断させ、例年になくモチベーションをかき立てたのが、Hondaのニューマシンなのだ。
「とにかく、全体的にパワーの底上げをしたフィーリングで、しかも軽い。これでマシンの差はなくなった。『勝ちにいける』と思っていました」と小川は言う。