|
 |
| 一般道、高速とトータル360kmほど走ったときの実燃費は10.12km/Lと、Lクラスミニバンとしてはかなり良好な数字を示した |
 |
|
 |
| こちらは4気筒2.4リッターエンジン。118kw[160PS]/5500rpm、218N・m[22.2kg・m]/4500rpmと、じつにトルクフル |
 |
|
発表会で展示されていたV6エンジンのカットモデル。実際にクランク、ピストン、カムシャフトが動いて、6気筒→3気筒→6気筒をわかりやすく説明していた |
 |
|
 |
| 全車★★★★低排出ガス車&平成22年度燃費基準+5%レベルをクリヤーして“グリーン税制”の優遇措置を受けることができる |
 |
|
 |
| 細かな部分ではあるが、フロントピラーやドアミラー、ボンネットフードの形状も、燃費の向上にひと役買う |
 |
|
 |
| コンパクトなエンジンで得られたショートノーズは、室内長の拡大や取り回しのよさなどに恩恵をもたらす |
 |
|
 |
さて、搭載されるパワーユニットであるが、V型6気筒 3.0リッター
i-VTECエンジンと直列4気筒 2.4リッター DOHC i-VTECエンジンの2種類が用意されている。なかでもV6エンジンは、6気筒燃焼と3気筒燃焼を切り替える画期的なシステム「可変シリンダーシステム」を採用。184kw[250PS]/6000rpm、309N・m[31.5kg・m]/5000rpmというハイパフォーマンスを発揮しながら、3.0リッタークラス・ミニバン、トップレベルの9.8km/L(10・15モード)「平成22年度燃費基準+5%レベル」という低燃費も両立している。
この可変シリンダーシステムは、ホンダが得意とするVTECの進化版ともいえる技術で、エンジンに求められるパワーをエンジンが判断するというもの。急減速やアイドリング、加速時には6気筒を作動させて高い動力性能を確保する一方で、暖加速やクルーズ、暖減速など、比較的低い出力で走行できる場合には、V6エンジンのリアバンク側3気筒を休止させるのだ。こうすることで大きなパワーを必要としない時にはエンジンは直列3気筒の1.5リッターエンジンとして燃費に貢献する走りをする。また、前後バンクにひとつずつ直下型キャタライザーを設置するだけでなく、床下にもキャタライザーを設置することで、3気筒燃焼から6気筒燃焼に切り替わった際にも確実な排出ガスの浄化を行なえることや、直下型キャタライザーそれぞれにリニアA/F(空燃比)センサーを配置してきめ細かな空燃比制御を行なうことで、国土交通省「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」認定を取得するといった環境への配慮も忘れていない。なお、このリニアA/Fセンサーは、現在絶好調のホンダF1エンジンでも採用しているテクノロジーのフィードバックだというから、ホンダDNAを感じずにはいられないだろう。同時に、このような優れた環境性能は4気筒エンジンも同様で、“グリーン税制”の優遇措置を受けることができる。環境にもやさしく、懐にもやさしいエンジンとは、嬉しい限りだ。
そのうえ、気筒休止中もイリジウムが採用された点火プラグはスパークし続け、プラグの温度低下を抑えつつ、空気のみでの点火による高電圧によるプラグ電極の磨耗を押さえているというのだが、これで、プラグのくすぶりによる燃焼不良、そこから引き起こされるエンジン不調が解消。そして乗り心地と、環境性能はもちろん、安全性能、快適性能など多くの項目について確保されることとなった。こうした環境性能についてもホンダならではといえるアイデアが盛り込まれ、トータルとしてクオリティの高さに結びつけるところはさすがだ。
しかし、エンジンは存在をパワーや環境性能でアピールするもので、鉄の塊としての存在はアピールされるべきではない。自動車パーツのなかで一番の重量物であるエンジンは、発揮するパワーはもちろん、重量が及ぼす影響も測られる必要がある。低重心に続く、走行性能向上の基本ふたつ目は、軽量化・コンパクト化である。補機類を同時に駆動させてエンジン全長を大幅に短縮させるサーペンタイン式ベルトを筆頭とした技術によって、軽量・コンパクト化は実現された。また、これらの技術は、フロントのショートノーズ化に大きく貢献し、キャビンの拡大に貢献するほか、クルマのデザイン自由度を増すなど、走行性能だけにとどまらない効果をもたらすことになった。迫力のフロントはここにも由来していることが判明した。
ここまでくると、もはやミニバンといって走りを捨てる、もしくは我慢するなんていうことは考えられないが、ホンダが「ミニバンのフラッグシップ」という点は確かだろうか。 |
 |
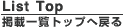 |
|