 |
| 〔1〕 |
主吸入弁からリーンな混合気、副吸入弁からは少量のリッチな混合気が吸入され、総合的にはリーンな空燃比となります。
アイドリングから、全負荷までの運転状況に応じて、主混合気と副混合気の量をそれぞれ加減します。その制御は両気化器の絞り弁をコントロールして行なわれます。 |
 |
| 〔2〕 |
圧縮工程の終りには
●点火栓付近には、濃い混合気
●副燃焼室の出口付近には、中間的な適度な濃さの混合気
●主燃焼室には、薄い混合気
が形成され、主燃焼室内はとくに強い乱れがない状態となっています。
この条件が、後続するスローな燃焼を行なうために必要です。 |
|
 |
 |
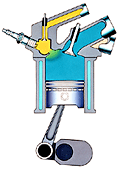 |
 |
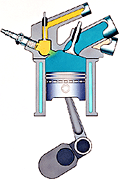 |
 |
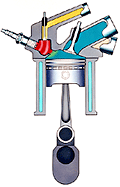 |
| 吸入行程 |
圧縮行程 |
点火 |
 |
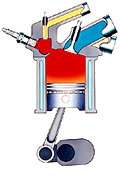 |
 |
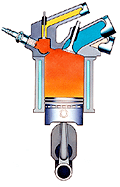 |
 |
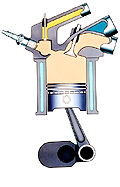 |
| 膨脹行程 |
下死点 |
排気行程 |
|
 |
 |
| 〔3〕 |
副燃焼室内の濃い混合気は点火栓の火花で確実に着火します。
この着火の状況は、通常エンジンの着火状況とまったく同様と考えています。
したがって、副燃焼室の点火に関して、特殊の点火栓、あるいは点火装置を用意する必要はありません。 |
 |
| 〔4〕 |
副燃焼室内で点火された燃焼ガスは、ただちに副燃焼室出口付近の中間的濃さの混合気に着火し、火焔面を拡大しながら、主燃焼室内の薄い混合気に燃焼を伝えるので、常に安定した燃焼が可能となるばかりでなく、主燃焼室内混合気はスローな燃焼が確保されます。
前にものべましたように、運転状況に応じて主副両気化器の紋弁開度が変ると、主副それぞれの吸入混合気量が変化し、本来、燃焼の条件も変ってくるわけですが、上述の副燃焼室出口付近の混合気が常に主燃焼室のスローで安定した燃焼を可能ならしめていると考えられます。 |
 |
| 〔5〕 |
かくして安定した緩慢な燃焼が続くと、燃焼ガスの燃焼最高温度は比較的低く抑えられるとともに、炭化水素などの燃焼に必要な高温に長期間保たれるので、NOxおよびHCの発生は極小に抑えられます。 |
 |
| 〔6〕 |
次に燃焼ガスは排気弁から排出されますがその場合比較的温度が高く、また過剰の空気がよく混合しているので排気系内でも残余の反応を持続します。この現象は通常エンジンでも余剰の空気が供給され、排出ガスの温度が充分高ければ一般に起こり得る現象です。 |
 |
| 〔7〕 |
排気熱(排気系における残余反応熱も含む)は適度に主副混合気のライザーを加熱しエンジンの急速ウォームアップを可能にしながら分配を良好にします。ライザー温度はフル運転時でも必要最高温度以内で作動するよう熱バランスがとられます。 |
|
 |
 |
| CVCCの燃焼原理 |
| 1. |
副燃焼室内の比較的リッチな混合気に通常の方法で点火します。 |
| 2. |
副室出口付近の中間的濃さの混合気に燃焼を伝えそのより大きい火焔で主室全体の薄い混合気を燃焼させます。 |
| 3. |
主燃焼室は薄い空燃比なのでCOの発生は極小に抑えられます。 |
| 4. |
1、2により達成された主室の緩慢な燃焼は、燃焼の最高温度をかなり低く抑えることを可能にしています。これがNOxを極小にするわけです。 |
| 5. |
エンジン内部で発生した熱エネルギーは有効にピストンに伝えられ動力に変換され、これは結果的に良好な燃費性能を与えています。 |
|
|
|
 |
 |
|