 |
| パワーウエイトレシオはともかく、何ゆえにホイールベースウエイトレシオをプロットするのかという疑問をまずは解決しておこう。ホイールベースウエイトレシオは、ハンドリングレスポンスの指標のために導入したと冒頭で触れた。つまり、ステアリングを切ったときの曲がりやすさ、シャキシャキ感のレベルである。シャキシャキ曲がって楽しいスポーツカーとは、ステアリング入力に対してクルマが敏捷であるだけでなく、安定していて剛性感も高い。そうしたスポーツカーにするには、クルマを重心まわりに水平に回す力を重量に対してより大きく高いレスポンスで発生させ、なおかつその回転運動、すなわちヨーイング(あるいはヨーとも呼んでいる)が素早く安定する性質を備えさせなければならない。前者のクルマを回す力をヨーモーメント、後者の代表的な性質をヨー共振周波数と呼んでいる。ヨーモーメントを効果的に働かせるには、回転重量(専門的にはヨー慣性モーメントと呼)が少ないことはもちろん、同じ力でもテコのように、回転力であるヨーモーメントの発生が大きく早くなるよう、力点と支点との距離(レバー)が長い方が有利である。クルマを曲げる力であるコーナリングフォースはタイヤで発生するから、レバーはクルマの重心とタイヤとの距離にあたる。この距離に関係するのがホイールベースであり、同種のクルマならホイールベースが長い方がレバーも長く有利である。また、先に触れたヨー共振周波数も、回転重量(正確にはその半径、すなわちヨー慣性半径)が小さく、レバーが大きいほど高くなることが知られていて、この周波数は高い方が一般にヨー運動の安定性が高く、上級ドライバーは操縦時の剛性感が高いと感じるようになる。 |
|
|
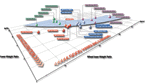
イラストをクリックすると、 通称”天の川チャート”が ご覧いただけます。 |
|
| ゴルフ好きの方なら、ゴルフクラブにも同様の振動数理論というのがあって、上級者は振動数の高いクラブの方が好ましいと感じるというのもご存じだろうと思う。このように、回転重量が小さく、レバーが長ければシャキシャキ感に有利であるから、回転重量をレバーで割ったレシオを見れば、そのクルマの曲がり易さを把握することができる。ただ、このような回転重量やレバー長などはカタログに載っていないため、これらに大体比例するとして、車重とホイールベースに着目し、そのレシオでハンドリングレスポンスの傾向を知る手がかりとしたのだ。しかしホイールベースウエイトレシオは、決してハンドリングのすべてを語るものではなくあくまでも指標である。タイヤの性能によってコーナリングフォースは違ってくるし、サスペンションやブッシュ類、ボディ剛性、あるいはトレッドによってクルマの旋回レスポンスは大きく異なるからである。その辺をご理解いただきながら天の川チャートをご覧いただきたい。データはカタログや広告などメーカー発表の値をもとにしてあり、プロットしたのは基本的に2ドア、2シーターのスポーツカーである。ただしポルシェなどのように、2シーターでないものもあるが、それらを除くと面白くないので仲間に入れてある。それから、ロータスエリーゼのようなネイキッドモデルや、フェラーリF40などのようにカーボンなどで武装したモデルは、かなり特殊なクルマであるため除いた。年代はNSXがデビューした90年と現在の99年近辺のモデル。ターボやスーパーチャージャーのものでも通常の量産車の範疇のスポーツカーであれば仲間に入れてある。 |
| |
|
|NSX Pressの目次へ|NSX Press Vol.24の目次へ| NSX Press vol.24 1999年10月発行 |