 |
| さて、プロットしてみると、実に見事な天の川があらわれた。グリーンのポイントでプロットしたBMWZ1を中心とするライトウエイトスポーツ群と、紫のポイントでプロットしたジャガーXKRを中心とするヘビーウエイトスポーツ群。そしてNSXなどの近辺に集うミドルウエイトスポーツ群。これらが、全体として右にゆったりと流れる天の川を形成している。そしてやはり、ミドルウエイトスポーツの領域に、今話題のフェラーリ360モデナやBMWMクーペ、マセラティ3200GTが来ている。そしてこれらブルーでプロットしたクルマが、ミドルウエイトの中でもヘビーウエイト寄り。やや重たいハンドリングのミドルヘビースポーツとでもいうべき領域を形成している。対して、NSXクーペとタイプS、NSXタイプR、そしてS2000などが、ハンドリングベストのミドルライトスポーツというにふさわしい領域を形成し、おまけにここにはホンダ車しかいないのが面白い。ハンドリングレスポンスがややずば抜けたインテグラタイプRを含めても、ホンダ独自の島がつくり上げられている。こうした結果は予想しなかったことで、もちろんこれがすべてではないにしろ、ホンダスポーツの一貫したスピリットを匂わせるではないか。そして、最新のスポーツカーをプロットしながらもなお、デビュー当時のNSXが確固としたポジションにあることに驚く。NSXタイプSは、ハンドリングでも加速の面でもそれをやや上回り、着実な進化を遂げている。仮にもし、馬力をもっと出すことができたなら、さらに群を抜く存在になれると思うと惜しい気もする。フェラーリ360モデナは、3.6リッターの自然吸気V8DOHCで400PS/8,500rpm、リッター当たり約111馬力のエンジンパワーが光り、パワーウエイトレシオではかなりいい位置につけている。 |
|
|
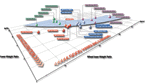
イラストをクリックすると、 通称”天の川チャート”が ご覧いただけます。 |
|
| ただ重量のためか、NSXを70mm上回るホイールベースを持ちながら、そのウエイトレシオはやや後退ぎみ。しかし、素晴らしいスポーツカーであることには間違いない。意外なのはランボルギーニディアブロで、V12の5.7リッターDOHCエンジンを擁しながらウエイトがそれほどでないため、BMWMクーペなどと近いハンドリングレスポンスをマークしている。ただし、それで同じ操る歓びが享受できるは限らないが。そして最後に、仮にF1マシンの最高出力を750馬力、車重を600kg、ホイールベースを2,800mmと仮定した場合の値を試算する。パワーウエイトレシオが0.8、ホイールベースウエイトレシオが0.21という驚異的な数字になる。下のグラフは見やすくするために横軸をカットしているため、F1の値をプロットすることはできない。しかし、そのポイントを想定すると、NSXクーペからタイプSを通り、NSXタイプRへと続くラインの延長線上に位置する。F1を究極の操る歓びに満ちたスポーツカーとすると、それはフェラーリやマセラティのいるミドルヘビーの延長線上ではなく、NSXをはじめホンダのスポーツカーが位置するミドルライトスポーツの延長線上にあるのだ。もう一度発売当初のNSXのカタログのページを繰っていただきたい。その天の川チャートには、一般のスポーツカー群から抜け出し、F1の方向をめざす矢印が書かれている。天の川チャートをあらためて検証してみて、それがまぎれもない事実であることがわかった。個々のクルマがDNAとして持っている、大きな進化の流れの方向を性急に変えることはできない。NSXの進化は、その原点が秀逸であるがゆえに、今後、ますます注目に値すべきスポーツカーになっていくに違いない。 |
| |
|
|NSX Pressの目次へ|NSX Press Vol.24の目次へ| NSX Press vol.24 1999年10月発行 |