レーシングカーは重量配分に相当するダウンフォース
を必要とする。ミッドシップのNSXは、フロントの重
量が軽いため前方のダウンフォースは出しやすい。し
かしその分リアは難しくなる。リアデッキが高いため
充分なウイング高が取りにくい。また、風も当たりに
くくダウンフォースを得にくい。
そこで浮上したのが床下の流れである。ここをつくり
込んでいくうちに、ダウンフォースはみるみる高まっ
たという。アクセサリーのフューエルアンダーカバー
は、たまたま床下の凹凸をなくし、グランドエフェク
ト向上に寄与した。
さらに奥氏は、エンジンを守る目的で独自にカバーを
設置。これも結果的に空力を向上させた。また、NSX
はもともと前面の投影面積が小さいため、ライバルよ
り空気抵抗的には断然有利。この点でもNSXのオリジ
ナルの設計の良さが大きく生きたのだ。
「それから、よく目を凝らしてフロントノーズを見て
ください。F1マシンのような吊り下げ型のウイングが
見えてくるでしょう。本当は、もっと派手にF1のよう
にしたかったんですが、あまりやり過ぎるとNSXのデ
ザインイメージを損ねますから、おとなしくまとめま
した」
なるほど見える、見える。ラジエターグリルとブレー
キ用のエアインテークを仕切る2本の支柱は、まさし
く翼端版をもつフロントウイングを吊り下げているで
はないか。面白い。レーシングカーにはやはりこうい
う“見どころ”があった方がいい。
ところでこのウイングは、すでに充分なフロントのダ
ウンフォースを増加させるための工夫ではなく、走行
中の変動を低減させるためのものだという。童夢なら
ではのユニークな空力デザインである。
その他にも、ホイールハウス内に渦巻く圧の高い空気
を逃がすためにオーバーフェンダーの形状を空力的に
突き詰めるなど、F1のテクノロジーを導入し、さまざ
まな空力的な処理が成されている。
―――しかし、エクステリアはきわめてシンプルであ
る。これを見るに、いたずらに“羽根”を増やすので
はなく、実質的な効果のみに集中し非常に高いレベル
でNSXGTマシンの空力が突き詰められていることが伺
い知れよう。
次ページに続く |
|
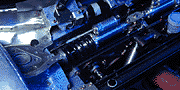
これがプッシュロッドタイプのダンパー(フロント)。タイプSのアルミモノコックをベースに、カーボンで仕上げたボディの剛性が想定していたよりも高かったため、サスペンションとタイヤは柔らかめに設定されたという。

社屋の右手、高野川のほとりにある童夢自作の風洞実験室内。ここで、NSX GTマシンの高度な空力デザインが煮詰められた。外から見えない、サスペンションアームの1本1本にまで空力が考え込まれているGTカーは他に例を見ないのではないだろうか。

童夢の奥氏が少々照れながら紹介したF1イメージの吊り下げ型ウイング。こうした空力パーツの一つひとつの仕上げまでが美しい。しかもシンプルで違和感がないため、NSXのこんなエアロバージョンが欲しいと思われるオーナーもいるのではないだろうか。
|