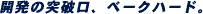
まず、耐食性を落としていた原因が解明された。既存の6000系合金に含まれる銅であった。しかし、銅を加えないと、今度は成形性と強度が極端に落ちてしまう。成形性とは、一度プレス型で成形した形状が、取り出し直後に戻る現象。通称スプリングバック。ひどくなると、プレスの時に材料に割れを生じることもある。
耐食性を上げるためにまず銅の添加をやめる。それで落ちる成形性を上げるために、マグネシウムとシリコンの添加量を調整していく。すると今度は強度が大幅ダウン。だからといって強度を上げるよう量を調整すると、再び成形性が大幅にダウン。八方塞がりである。
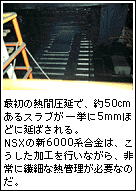 こうした研究がはじまったのは、'90年のNSXデビューに遡ることおよそ5年。当然ながら完成を見るのは直前であるから、実質4年にわたり模索の材料研究が行われたのだ。材料のみでこれほど長期にわたる研究は、ホンダでもかつてない経験だった。とにかく失敗の連続。大量の試験材料の山。通常、缶などをつくるときアルミメーカーが製造ラインに流すのは数十から数百トンレベルのインゴットだ。一方、NSXの材料開発の試験材で必要となるのは多くても500kgレベル。しかし、500kgの材料をつくるにも最低10トンのインゴットを流さなければならない。それも、添加する物質の管理、圧延などの加工にともなう熱処理などが微妙なため機械任せにはできない。材料がラインを流れていくのを見守るように、技術者がつきっきりになるのだ。 こうした研究がはじまったのは、'90年のNSXデビューに遡ることおよそ5年。当然ながら完成を見るのは直前であるから、実質4年にわたり模索の材料研究が行われたのだ。材料のみでこれほど長期にわたる研究は、ホンダでもかつてない経験だった。とにかく失敗の連続。大量の試験材料の山。通常、缶などをつくるときアルミメーカーが製造ラインに流すのは数十から数百トンレベルのインゴットだ。一方、NSXの材料開発の試験材で必要となるのは多くても500kgレベル。しかし、500kgの材料をつくるにも最低10トンのインゴットを流さなければならない。それも、添加する物質の管理、圧延などの加工にともなう熱処理などが微妙なため機械任せにはできない。材料がラインを流れていくのを見守るように、技術者がつきっきりになるのだ。
当然、他にも急ぎの仕事がある。数百トンレベルの仕事が肩を怒らせてラインを流れようとする。しかしNSXの試験材も急ぐ。限られた生産ラインを取り合うことになる。当然の帰結としてアルミメーカーの社内スタッフ同士による壮絶な喧嘩となる。相手は規模の大きさで押す。しかし、NSXのアルミ開発者も譲らない。何故なら、未来があるからだ。将来、省エネルギーを最優先したクルマが開発されるとき、ボディ材は「鉄からアルミへ…」となるかも知れない。そのとき、オールアルミボディを手がけたノウハウは強力にものをいうからだ。そして、さんざん苦労してつくった試験材があっさりNGになる。それが何年も続く。一時、“オールアルミボディは無理ではないか”との空気も流れた。しかしNSX開発チームはあきらめなかった。アルミメーカーもねばった。そんなとき、ひとつの突破口が見いだされた。
―――それは、「ベークハード」という概念である。
ベークハードとは読んで字の如し。ベークすなわち「焼き」により、ハードすなわち「硬化」させるのだ。つまり、クルマの焼き付け塗装の熱を積極的に利用して完成時の強度を大きく上げようという魂胆である。これであれば、塗装の前に加工するときは柔らかくて扱いやすい。一挙両得の手法なのだ。
アルミ合金にもともとあった概念だが、開発の難題を乗り越えるために積極的に利用されたことはなかった。この、ベークハード性を高めることにより、研究は急激に現実味を帯びてきた。
耐食性を上げるために銅を使わず、強度と成形性を高レベルに両立するマグネシウムとシリコンの微妙な調整。“シリコンリッチ”といわれる比率だが、当然その具体的内容は極秘である。そして、あわせてベークハード性を高く保つ結晶組織をつくる繊細な熱処理の実行。これで加工しやすくてプレス後も美しく、完成時の強度と耐食性が高い世界初の6000系が完成した。そして'90年。悲願のオールアルミボディでつくり上げられたNSXは、「超軽量」のリアルスポーツカーとして世界を圧倒した。伝統のスポーツカーメーカーのコンセプトさえ静かに揺るがしたのである。
|



