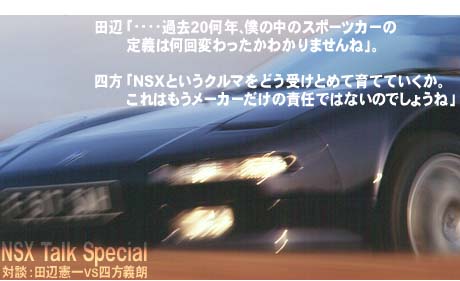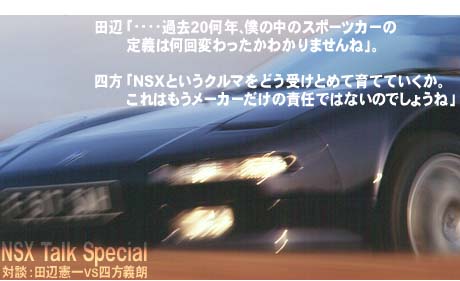|
田辺「これまでのオープンカーは、幌なんかつけて走ればギシギシと壊れそうな音がしましたね。スポーツカーなんだからこれは当たり前なんだと、ある種、我慢して乗っていた部分があるんだけど、NSXのオープントップの場合それが一切ない。これはNSXが快適性と走りの性能において妥協をしないという徹底した思想があったからできたことです。他にもNSXならでは、と思うこだわりがあります。たとえばルーフがパカッと取れて、それが後ろのエンジンルームの上にすっぽり収まってしまうんですよ。収めてしまうと、まったく外観に影響を及ぼさない。こういう芸の細かさは、他のオープンカーにないところ。しかもどこかのクルマのように屋根から雨が漏るなんてことは決してない(笑)」。
|
|
四方「それは面白い。オープン乗ってる他の連中に自慢できるな」。
|
|
田辺「たしかホンダがはじめてつくったクルマは、S500というオープンでしたよね。そのSシリーズのルーフレールにはディフレクター(風の整流板)がついていた。でもNSXには、そういう余分なものが一切付いてなくて、すっきりとデザインされている。だからといって風が入り込んでうるさいわけではない。そんなところが、近代的なオープンなんだなって思いましたね」。
|
|
四方「なるほどね・・・」
|
|
田辺「メカニズムでは、変速機のシステムなんかも新しいところ。センターコンソールにあるオートマチックのセレクターを3/Mというところに入れておくと、停止すると自然に1速に戻る。ステアリングの左側に、レバータイプのスイッチがあって、走り出してから自分の思うところでそのレバーを指で触れて、2速、3速、4速とシフトアップしていく。オートマチックなんだけれど、このモードにするとシフトチェンジのレスポンスも速くなって気分がいい。だから、これまでのATよりかなりスポーティな走りが楽しめるわけです。コーナーの入り口で連続シフトダウンなんかをして・・・」。
|
|
四方「何で、ステアリングの上にスイッチをつけなかったんですかね」。
|
|
田辺「あまりハンドルを回すことのないF-1だとそれでもいいんですが、実際に乗ってみればそのわけはすぐに分かります。確かにハンドルから手を離さなくていいから、一見便利そうなんだけど、F-1と違ってスポーツカーの場合はハンドルをぐるりと回すじゃないですか。そうすると、スイッチがどこにあるか分からなくなってしまうんですね。これはちょっとスポーツカーには向かない。ホンダも今回、初めてこの装置を開発するにあたっていろいろと試みたそうですが、今のものが正解だと思いますね」。
|
|
四方「なるほど・・・。そういわれてみればそうですね」。
|
|
田辺「他のメカニズムもいろいろ進化しているんですが、撮影していて、僕達も困ったんですよ。目に見えないから、その新しさをどうやって伝えればいいのか・・・。たとえばアクセルを踏みますね。有名スポーツカーなどで往々にしてトラブルの元になるミッドシップならではの長いアクセルケーブル。あれがないんです。全部、電線なのです。それでスロットルバルブはモーターで動く。いわゆる『ドライブ・バイ・ワイヤ』というやつです。F-1などでも使われている技術ですね。なんのためにそんなことをしたのか、という話にもなりますが、まずアクセルペダルの重さをリターンスプリングを交換するだけで自由に設定できるようになるし、トラクションコントロールなどにも組み込みやすくなっていくわけです。目には見えないし、普通の人には分からない領域の技術かも知れませんけど、優れた技術であることに違いはない」。
|
|
四方「そういう方向も、面白いと思います。NSXって、リアルスポーツっというイメージを打ち出しているけれども、さっき言ったようにスポーツカーは手にする人によっていろんな楽しみ方があっていいはずですからね。NSXにはRという方向性もあるけれど、超ラグジュアリー仕様があってもいい。確かに、クルマに手を入れて少しでも速く走ろう、というのはスポーツカーの一つの楽しみ方ではあるけれど、いろんなものが盛り込まれたクルマをそのまま脚代わりにのんびりと走る、ある種スポーツカーの本分を外した格好良さって必要ですよね。そのためには、僕はやはりオープンでしかもオートマチックっていうモデルが欲しかったんだ」。
|