
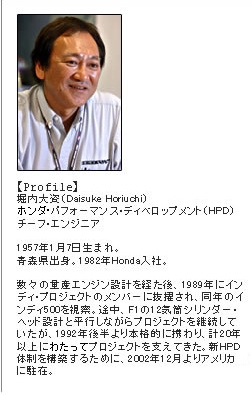
翌2007年から2009年までのインディ500でもエンジン・トラブルは皆無で、現在も記録を更新中です。他のレースにおいても2009年のミド・オハイオまで44レースにわたってトラブル・フリーだったのですが、残念ながら次のソノマで初めてジェネレータのハーネスがショート。この間に走行した全1021台のエンジン無故障の走行記録は、24万7574マイル(39万6118キロ)でストップしてしまいました。
この間、2006年はメタノールに10%のエタノールを混ぜて使用し、2007年からは100%エタノール(実際は98%で、誤飲防止用にガソリンが2%混ざっています)となったことで、それに合わせた改良も行っています。また、チームの負担をできるだけ減らすために、当初からエンジン交換のタイミングを1400マイルに設定し、テストも含めて年間のリビルト回数が10回程度になるようにしました。CARTの頃は500マイル持てばいいというエンジンだったので、格段の差ですね。
将来的にその距離を2000マイルまで延ばす予定で、リビルトの回数をさらに2〜3回減らしたいと考えています。そうすれば毎年チームからいただいているエンジン・リース料も、あと1〜2割は下げられるのではないでしょうか。このような経済状況だけに、我々も精一杯努力してチームや主催者に喜んでもらえるよう、ワンメイクならではの開発というのもあるのです。
 レース中HPDのエンジニアはチーム・スタッフの背後に控え、アクシデントに備えてファイアースーツを着用しています
レース中HPDのエンジニアはチーム・スタッフの背後に控え、アクシデントに備えてファイアースーツを着用しています
IRLのオフィシャルは近い将来に再び複数のメーカーが参戦できるよう準備を進めていて、次のインディ・エンジンがどうあるべきか、何度も議論を重ねてきました。そういった意味で、HPDのスタッフはまったく白紙の状態からエンジンを開発することができるわけで、これは滅多にない機会だと思います。重要なポイントはコストもそうですが、新しい環境技術も必須であり、果敢にチャレンジしなくてはなりません。
2003年から始まったアメリカにおけるHondaのレース・エンジン開発は、アメリカン・ル・マン・シリーズで自分たちが開発したエンジンとシャシーでチャンピオンを獲ることができ、やっと最初のサイクルが終わったと思います。はじめは図面の書き方に始まり、手取り足取りという状態でしたが、7年間でみな頼もしく育ってくれました。次の2サイクル目、次世代のインディ・エンジンの開発はアメリカ人のリーダーで始めることになりますが、それでこそ本当の現地化が実現すると言えるのでしょう。
 アメリカン・ル・マン最高峰のLMP1でチャンピオンとなった、我々が誇るオールHPD製エンジンです!
アメリカン・ル・マン最高峰のLMP1でチャンピオンとなった、我々が誇るオールHPD製エンジンです!