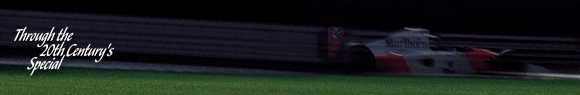| さて、第1期の活動休止から12年の時を経て、ホンダの本格レーシングエンジンが轟音を挙げたのは1980年のF2。ここから第2期F1活動が始まる。70年代に自動車産業界を襲った排気対策などのために、かくも長き不在の期間ができてしまったのだが、これをホンダF1活動の氷河期と考えるのは、実は正しくない。前述のように、この時代に開発された低公害エンジンの多くに、第1期F1活動で得られた経験が(技術でも取り組みの姿勢でも)盛り込まれていたように、今度は、これら市販車開発のノウハウが、新しいF1にも生かされることになったのだ。それに、たとえ表面的にはレース活動を休止したとはいえ、ホンダの技術者ともあろう者が、ただ休んでいるわけなどないではないか。課外活動などいろいろな形で国内レース用のエンジン開発を助けたように、水面下で活発なスタディが続けられていたのは言うまでもない。そんな経験と人材を集めてはじまった第2期F1活動は、おりしもターボによる高出力追求の真っ只中。ホンダばかりか、名だたるエンジンメーカーの誰にとっても、レースごとに未経験ゾーンに突入する、まさに技術のワンダーランドであった。その中でめきめき力をつけたホンダエンジンが独占的な強さを発揮するに至ったのは記憶に新しい。特にマクラーレンに搭載され、名手アラン・プロストとアイルトン・セナにステアリングが委ねられた1988年など、ほとんどの予選でフロントローを独占したばかりか、決勝でもシリーズ16戦中15勝という空前絶後の大記録を達成しているほどだ。しかし、こんな輝かしい成果も一朝一夕に得られたわけではない。頂点をきわめるまでには多くの苦闘があったのだが、今振り返れば、その過程にこそ新しいホンダF1活動の真価が潜んでいたように見える。1980年代のホンダといえば、第1期当時とは比較にならないほど成長した世界規模の大企業だ。そんな組織の中で、小回りが必要なレース活動ほど難しいものはない。しかも取り扱う対象がターボや複雑な電子制御ときている。そこでホンダは、リアルタイムにエンジンの状態を掴むデータテレメトリー・システムを採用した。ドライバーとエンジニアの対話に頼っていた職人芸から、完全に客観的な技術開発の世界へと、レーシングエンジンを解放したわけだ。この方法によれば、主観に左右されない正確なデータを、ピットクルーだけでなく本社の開発スタッフも同時に共有できる。F1に限らず、現在のモータースポーツ界では常識になった手法だが、いかにホンダが、あらゆる英知を結集してF1に取り組んでいたか、これだけでもわかるだろう。このような経緯を踏まえて、いよいよ2000年から、ホンダにとっての第3期F1活動がはじまろうとしている。当面は、このところめっきり地力をつけてきた無限ホンダの経験を生かして、しっかり上位に定着するエンジン作りに専念するのだろうが、さあ、楽しみなのはその先だ。いつもF1に新風を吹き込んできたホンダだけに、ただ他と似たようなやり方だけで満足するとは思えない。何らかの形で既成概念をひっくり返すような発想を打ち出してこそ、新しい世代がF1に飛び込んでいく意味もある。今の私たちが予想もしないような大ブレイクを期待しておこう。―――と、これまでのF1活動の持つ意味を振り返ってみただけで、おぼろげながら、そこにNSXの像が浮かんでくるのがわかる。そう、やはりキーワードは「一気に頂点をめざす」ということだ。いかに高性能や走る楽しみが大好きなホンダといえども、リアル・スポーツカーといえば60年代を風靡したS600/S800しか経験がなかった。なのに、あらためて手がけるとなった時、めざしたのはフェラーリやポルシェに代表される、世界最高水準のスーパースポーツだった。つまり、製品そのものの前に、コンセプトの芯がホンダイズムそのものだったのだ。そうでなければ、こんなに困難なクルマづくりなど、考えられもしなかったはず。総アルミニウム製のボディというのが、量産車で初めてではなかったにしても、ほとんど前例がなかったのは、それだけ難問が多いからにほかならない。一般には柔らかいと思われているアルミだが、クルマに使用されるジュラルミンと呼ばれる合金となると事情が違う。たとえばフェンダーのプレスにしても、いったん成形して型から外すと、少し元の形に戻ってしまったりするから始末が悪い。それぐらいなら、すでに扱い慣れた鋼板を採用するのが常識だろう。それを承知で特殊なプレス機ばかりか専用の変電設備まで導入し、NSX専従の工場まで建設してしまったところに、徹底的にやり抜くホンダならではの取り組みが明らかにあらわれている。これほどの困難を克服して、軽量アルミボディを実現したからこそ、NSXは単に排気量やパワーだけに頼らない軽快なフットワークを手に入れることができた。その後、世界のスーパースポーツが軒並みアルミの採用に走った裏にも、NSXの成功が大きく作用していたはずだ。もちろん、さすがのホンダとしても、ただNSXを作るだけのために、アルミボディ開発に挑んだわけではない。「これからは、こうなる。これからは、こうしなければならない」という先見性と信念がなければ、どんな挑戦も意味が薄れる。だから、NSXでの貴重な経験に基いて、新方式をふんだんに取り入れたハイブリッドカー、インサイトが開発されたのも、当然の流れだったかもしれない。そういう意味では、刻一刻と迫り来る次世代エネルギーの時代に向けて蒔かれた、大きな種の一つがNSXだったともいえるわけだ。そんな目で見ると、操って楽しいとか、緻密な改良でさらにレベルが上がったとか、それ自体の評価を超えて、NSX像が大きく見えてくる。つまりNSXを駆ることは、「明快な目標設定と妥協なき挑戦」のホンダイズムを着ることであり、その象徴としてのF1を肌で知ることでもあるのだ。
|