| |NSX Pressの目次へ|NSX Press Vol.24の目次へ| |
 |
| 「NSXのルーツはF1だ」というと唐突に聞こえるだろうが、どちらも同じ根から生えているのは確かだ。その根を「ホンダ・スピリット」と呼ぶ。 50年を超える歴史を貫くホンダのキーワードは「不退転の決意」。常識では考えられないほど高い目標を掲げ、何が何でもやりぬく徹底ぶりで、いつも世間を驚かせ、よろこばせ、時には呆れさせてきた。 高い目標といっても半端ではない。とにかく「一気に頂点をめざす」のがホンダの真骨頂。普通なら、とりあえず日本一になってから世界一を狙うのに、いつもホンダの眼中には世界一しかなかった。 技術開発でも事業展開でも、そんな例はいくらでもある。たとえば1960年代の初めに鈴鹿サーキットを建設したこと。まだモータースポーツなどまったく認知されていなかった当時の日本に国際級のサーキットを作ること自体、あまりにも意外すぎる発想だったはず。しかし完成当初から屈指のテクニカルコースとしての評価が高く、特に現在では、F1を開催する舞台の中で最もチャレンジングな性格のコースとして、多くのトップドライバーから太鼓判を押されている。 そして1970年代の初め、厳しい排気対策を求めるマスキー法の実施に対し、日米欧のメーカーがこぞって難色を示したのを尻目に、革新的なCVCC方式を開発して、いち早く適合第1号となったのもホンダだった。また、日本の産業界が世界での地位を高め始めた70年代に、他に先駆けて輸出先での現地生産に乗り出し、軌道に乗せたのもホンダ。今では本籍こそ日本ながら、生産だけでなく企画や研究開発まで世界各地で行う、多元ネットワーク企業に成長してしまったのは周知の通りだ。 そんな限界チャレンジの象徴が、ホンダならではのレース活動だろう。まだ海外への雄飛など雲をつかむような話だった1950年代に、一大決意のもとマン島TTレースを経て世界GPに撃って出た二輪がきっかけだが、最も華やかにホンダ・レース史を彩るのは、やはりF1だ。「一気に頂点をめざす」のに、これ以上のものはない。入門フォーミュラや底辺レースを飛び越して、まずF1ありきと目標を定めたあたり、いかにもホンダらしいではないか。 このF1活動を振り返ると、大きく第1期(1964〜68年)と第2期(1980〜92年)に分けられる。 1.5リッター時代の終盤から3リッター時代の初期を経験した第1期は、それこそ未知の領域への限りないチャレンジの連続だった。何しろ四輪車の経験がほとんどなかった当時、いきなりその最高峰のレースに挑んでしまったのだから、何もかも手さぐりだったのも無理はない。反面、それだけにすべてのしがらみと無関係だったため、既成概念のかけらも匂わないクルマ作りができたのも事実だった。 1964年、ニュルブルクリングでのドイツGPに、ホンダの実戦デビュー作RA270が姿を表した時の衝撃は、今でもF1界の語り種になっている。ミッドシップに横置きのV型12気筒エンジンというだけでもユニークだったのに、動力性能の点でも、並みいる先輩チームを凌ぐものがあった。当時の1.5リッターフォーミュラでは180〜200psが普通だったのに、最初からホンダV12は220psレベルと一段上を行っていたのだ。それを可能にしたのは二輪で培った超高回転技術。耳が痛くなるほど甲高いサウンドに、たちまち「ホンダ・ミュージック」のニックネームが付いたのも、この当時のことだった。 こんな常識破りのホンダイズムはその後3リッターフォーミュラにも受け継がれ、常にパワーで他を圧倒してきたばかりか、最終期には野心的な空冷F1エンジンまで開発し、このうえなく大きな波紋を投げかけたりもした。もちろん、そのすべてが大成功をおさめたわけではなく、たとえば二輪技術の展開だけでは小型軽量化が難しいなど、いくつかの問題もあるにはあった。しかし、これら限界追求の時代を経て、ホンダの技術者たちは多くを学んだ。たとえば微妙な燃焼のコントロールの場合、その後の高性能車の設計ばかりでなく、低燃費車や低公害エンジンに生かされたノウハウも数えきれないほどあった。 いや、学んだのは技術だけではない。レースという極限的な状況の中で、いかに現実的に考え、すばやく理想を追求するかを学んだ効果の方が、圧倒的に大きかったかもしれない。何事にも鋭いレスポンスを示し結果を出すホンダの社風は、こんな過程で磨き込まれてきたのだ。 これを一種の社員教育と位置付けるなら、最高峰でのレース活動は最も効率の良い方法とも言える。もちろんF1活動には巨額の費用も必要だが、他の方法で同じ結果を得ようとしたら、もっと費用や時間を要したかもしれないからだ。 |
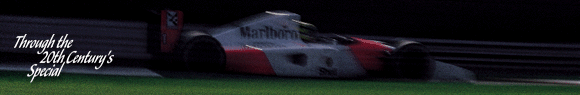 |
 |
|
|NSX Pressの目次へ|NSX Press Vol.24の目次へ| NSX Press vol.24 1999年10月発行 |