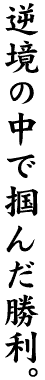 |
まず、新たな吸気制限によって吸気面積が7%も減少するためCB32型V6エンジンに対しては、出力低下を最小限に留めるようチューンが行われた。このチューンとは、充填効率の向上とフリクションロスの低減を髪の毛一本ずつでも進化させるといったものだ。回転を上げても小径のリストリクターによって空気が入らないためパワーアップにはつながらず、圧縮比アップによる熱効率の向上も、燃料が決まっているため制限される。
したがって、ボディのデザインを熟成し空気抵抗を低減して出力の低下分を補う工夫がなされた。
また、車重ハンディによってNSXの特長である優れた運動性能が阻害されないよう、ボディの空力特性を磨き上げてダウンフォースを増強すると共にサスペンション特性が見直された。さらに、ブレーキ及び駆動系を強化し加減速の負担に対する耐久性が高められた。これらの99年に向けた開発の成果は、シーズンオフのテスト走行でただちに確かめられている。98年の俊足に歯止めをかけるために加えられたハンディをものともせず、99年型NSXはこれまでのコースレコードを軽々と破ってしまったのである。
昨年、NSXはGT選手権の参加マシンのなかで「活躍が見たいクルマ」の人気No.1を獲得。NSXを走らせるチームの人気が高いのもうなずける。厳しい状況下でとにかく彼らは速いのだ。
そして、99年のシリーズが3月20日鈴鹿サーキットで開幕した。苦境をものともせず、念願の王座を目標に開幕からスパートを掛けようとするNSXは、ドライビングの難しい雨という状況のなか、その運動性能を武器にライバルに差をつけ、公式予選でTAKATA童夢NSXの脇阪寿一/金石勝智組がポールポジションを奪うと、決勝でスピンを喫しながらも他車を寄せつけない速さで開幕優勝を遂げたのだ。
|
 |
まさに逆境下の勝利である。TAKATA童夢NSXは、昨年何度も勝機を逸しての初勝利。倒れそうになるほどの働きで、逆境下に勝つマシンをつくりあげてきたデザイナーやエンジニア、メカニックの苦労を知っているからでもあるが、硬く拳を握り“よしっ”と叫びたくなるほどの感動であった。
清水選手の金メダルのときのように、「やればできる」のだという希望の炎がまたひとつ胸に満ちあふれた。この感動の勝利に、NSXの素性のよさが一役買っていたことに疑いはない。それに増して無限×童夢の不屈の精神に心からの拍手を送りたい。
思えば、ホンダはこうした「やればできる」という話題に事欠かない存在である。かつてのマン島TTレースも、F1への挑戦も、四輪参入時のS500の開発も、すべて当時としては無謀なる挑戦だった。NSXというスポーツカーも、280馬力の枠のなかで、世界第一級の運動性能を実現する無謀なるチャレンジによって生み出された珠玉のスポーツカーなのである。
なぜ、ここまで苦しい挑戦を行うのであろうか。そういった問いに、清水選手は未知の領域に入ることが最大の楽しみとシンプルに答えている。
彼は、オフシーズンのトレーニングの種類を毎年変える。同じトレーニングをしても筋肉が慣れてしまい新たな力を得ることができないからだ。たとえば、ある年は徹底して自転車をこぐ、といった具合。それも半端ではなく、1日に100kmこぎ続けたりする。もうダメだと思ってからさらにこぎ続けていくと、息ができないほどの苦しさと嘔吐、足の痛みが同時に襲いかかり、気が遠くなって目の前が真っ白になる。それを彼は“死点”と呼ぶ。死点まで自分を追い込むと、肉体も精神も一度破壊されて新たに再生される。その再生された肉体と精神力でコンマ数秒を削り取り、“より速く”をめざす。世界記録を更新したカルガリーでは、“氷上に光のライン”が見えたと彼はいった。
一線を超え、人間の能力の未知の領域に入ると、得もいわれぬ恍惚の世界がある。彼はその世界に入ることを楽しんでいるのだ。
つまり、彼らは未知の領域をめざす冒険家なのである。NSXに携わる面々も、極限まで自らを追い込むことで、きっと何かを見ているはずだ。彼らは、スポーツカーの世界に生きる冒険家なのである。
|
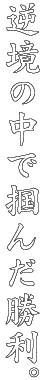 |
| No. |
エントラント |
マシン |
監督 |
ドライバー |
| 16 |
無限×童夢プロジェクト |
Castrol 無限 NSX |
熊倉淳一 |
中子 修/道上 龍 |
| 18 |
TAKATA 童夢 NSX |
脇阪寿一/金石勝智 |
| 64 |
Mobil 1 Nakajima Racing |
Mobil 1 NSX |
中嶋 悟 |
トム・コロネル/山西康司 |
| 100 |
チーム国光 with MOONCRAFT |
RAYBRIG NSX |
高橋国光 |
高橋国光/飯田 章 |

|NSX Pressの目次へ|NSX
Press Vol.23の目次へ|
NSX Press vol.23 1999年4月発行
|