 |
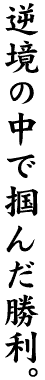 |
スポーツにおける困難な状況での勝利は、人々に熱い感動を与える。アメリカワールドカップ出場を目前にした日本代表チームに襲いかかった“ドーハの悲劇”も、相手側のイラクにしてみれば、後半ロスタイムの大逆転劇として、諦めかけていた母国のサポーターを熱狂させたことだろう。
日本もやられているばかりではなく、サッカーのオリンピック代表チームがブラジルのカナリア軍団にまさかの勝利を挙げたときは、生中継のあった朝から大声を上げて狂喜したのではないだろうか。
柔道の田村亮子選手があの小さい体で豪快な一本背負を打ち勝利するのも胸すくシーンであるし、負傷を押してオリンピックの金メダルをもぎ取った山下泰裕選手や古賀稔彦選手の表情に、何人もの日本人が泣かされたに違いない。
長野オリンピックのスピードスケートで見た、清水宏保選手の金メダルも凄かった。相手の半分ぐらいしかないと思える小さな体が、スタートの合図とともにぐんぐん加速し、みるみると相手を引き離す。姿勢が低く、速い。それもただの勝利ではなく、大会記録での圧倒的勝利。あのレースに見せた低い姿勢を身につけるのに、コンクリートの塊を背負って練習したという後日譚にも驚かされた。「やればできる」。希望という名の宝物をひとつ、勝利の感激にのせて人類に授けてくれたのである。
この清水選手の速さに、全日本GT選手権におけるNSXの速さが重なるのだ。
NSXがこのレースに本格的な挑戦を開始したのは、1997年のことだ。それ以前にも、かつてル・マン24時間レースに出場するため開発された車両で参加していたため、NSXは苦戦を強いられていた。そこで97年、無限と童夢という日本屈指のコンストラクターとともに新たに全日本GT選手権用NSXを開発し、シリーズへ本格参戦することを決めたのだ。
このとき開発陣は敢えてターボ過給を避け自然吸気エンジン搭載を決断した。
当然ライバル車の用いるターボ過給エンジンにパワーで対抗することは出来ない。しかし開発陣は綿密な解析の末、自然吸気エンジンでNSX本来の空力特性のよさと、低重心のピュアスポーツカーでこそ達成できる軽快な運動性能を引き出せば、総合性能でライバルに打ち勝つことができるはずだと結論を出したのである。
97年シーズン中盤に実戦へ投入されたNSXは、殺人的な短期スケジュールで開発されたこともあり、デビュー当初は初期トラブルに見舞われて苦戦した。しかし、翌98年シーズンには「いつ勝ってもおかしくない」と言われるまで進化を遂げた。
とにかくコーナーが速い。いっそうの低重心化と空力性能の進化で、脱兎のごとくコーナーを駆け抜けるのである。ストレートスピードも、立ち上がりのよさからひけを取らない。そして、ドライバーにしてみれば、NSXのGTマシンは極めて乗りやすいのである。その最大の理由は、自然吸気エンジンのドライバビリティのよさだ。予選で全戦ポールポジションを獲得することでもそのパフォーマンスの高さが伺い知れよう。
そして98年シリーズ第4戦、初優勝を遂げると、シーズン閉幕のオールスター戦まで勢いに乗って5連勝を飾った。シリーズ前半の出遅れが響いてチャンピオンこそ取り逃がしたものの、NSX独自の開発コンセプトの正しさは、5連勝という驚くべき戦果で証明されたのである。
|
 |
全日本GT選手権シリーズは、現在国内でファンを最も多く動員する人気レースである。その人気の要因は、身近な存在であるスポーティカーやスポーツカーのバトルであるからだ。極限のチューニングを受けて研ぎ澄まされたマシンは、そのクルマの愛好者にとってまさに夢。息をのむほどカッコよく、背筋が震えるほど最高のエキゾーストノートを放つ究極のマシンである。その夢のマシンが集まり繰り広げるレースは、クルマ好きにとって見逃せないレースなのである。そして、全日本GT独自のイコールコンディション・コントロールがレースの魅力をさらに高めている。
GTカーは、市販車両をもとに、チューニングを施すことで開発されたレーシングカーである。したがって、車両規則の中で自由な設計ができるフォーミュラカーと異なり、GTカーには本来のクルマの性能の個体差がついてまわる。
この宿命を乗り越え、かつレースをショーアップするため、全日本GT選手権では、吸気制限と車重を車両毎に規定することでイコールコンディションとすることをめざしている。さらに、レースの上位入賞車には最大120kgまでウェイトハンディを課していき、次のレースで4位以下に落ちた場合は軽減するという独自の規則を定めて、レースをよりエキサイティングなものとしている。その「イコールコンディション化」のための車両規則が今年、新たに改定された。
その結果、昨年5連勝を遂げたばかりか、予選、決勝とすべてのセッションでベストタイムを記録し圧倒的な性能を見せつけたNSXは、ただでさえ苦しい自然吸気で闘っているところに、さらに今年はより厳しい状況のなかで闘うことになったのだ。
まず吸気制限を行うリストリクター径が32.2mmから31.8mmへ縮小された。これは、ターボ勢と同じ径であり、他のレースでは考えられない措置である。ちなみに、99年ル・マンのGTSカテゴリーでは、自然吸気は3.5リッターの排気量でリストリクター径は35.3mm、ターボは同じ車重で2リッター/33.4mmである。
コンディションをイコールとするために、歴然とした差をつけている。それに加え、ミッドシップ車だけ最低重量が50kg増やされたのである。当然、NSXの持ち味である軽快な運動性にも大きな影響がおよぶ。速い車両には重いハンディを与えるという全日本GT選手権の理念に照らせば、NSXがそこまで成長を果たしたという証明だということにもなる。しかし、NSXには99年シーズンに念願のチャンピオンを獲得するという目標がある。そのためには、重いハンディを乗り越えてライバルたちと格闘し、打ち勝たねばならないのだ。開発陣は再び、困難な課題への挑戦を余儀なくされたのである。
|
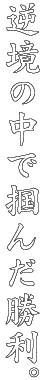 |

|NSX Pressの目次へ|NSX
Press Vol.23の目次へ|
NSX Press vol.23 1999年4月発行
|