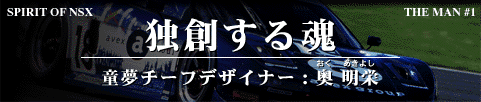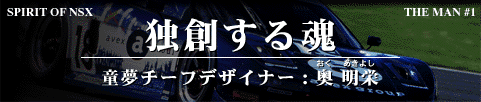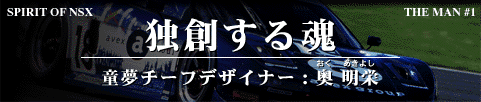
この頃、目標をF1参戦に定めてフォーミュラカーの開発に着手。そのシミュレーションとして全日本F3000に参戦しはじめるもまだ試行錯誤の連続。しかし不断の努力の末、'92年の第5戦で開眼。直前のテストで、空力実験と実戦との間に潜むダークマターを発見したと奥氏は言った。それまで、実験と実戦の間にはかみ合わない何かがあった。予想と結果の不統一。これではフロックは起こっても完全な勝利は望めない。しかし、奥氏はそれを見出した。「このデータは信じられて、このデータは良くても捨てなければならない」といった、マニュアル化できない独自の判断基準である。すぐさま第5戦は優勝。その2年後の'94年シーズンは年間3勝を果たしシリーズチャンピオンを獲得する。
このあとご存じの通りF1シャシーを開発。日本屈指のレーシングコンストラクターとして、さらに孤高の道に至る。'96年11月。そんなハイテンションの独創集団にNSXのホワイトボディが送り届けられた。奥氏曰く―――。
「NSXも他に例を見ない独創のマシン。そのメリットをさらに伸ばしていけばいいと考えました。ターボ勢を相手に、NAでどこまで行けるかという参戦スタンスも面白いじゃないですか」
具体的にいうと、NSXはもともと空力が良く、ミッドシップであるため重心にウエイトを集中させやすく、さらに低重心化を図りやすい。奥氏は、そこを徹底して伸ばした。コーナリングスピード追求。優れたドライバビリティの確保。これで闘うと。
また、手渡されたホワイトボディの重量はわずか170kg。軽い分、剛性アップの補強が充分に行える。それでも、あまりに軽くなり過ぎた。結局、レギュレーションの最低重量に合わせるため、120kgものウエイトを積んでいるという。
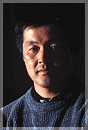 「どうも、つくりがF1感覚になってしまうんです。設計するからにはベターではなく、ベストをめざしてしまう。加減することができないんですね。手間やコストよりも、やはり性能で選んでしまう。もともと市販のNSX自体がそうですよね。こういうクルマをつくりたいという目標に向かって、非常に手をかけてつくっています。それに負けるわけにはいきません」 「どうも、つくりがF1感覚になってしまうんです。設計するからにはベターではなく、ベストをめざしてしまう。加減することができないんですね。手間やコストよりも、やはり性能で選んでしまう。もともと市販のNSX自体がそうですよね。こういうクルマをつくりたいという目標に向かって、非常に手をかけてつくっています。それに負けるわけにはいきません」
普通、クルマのホワイトボディを平らな床面に置くとガタつくという。溶接していくうちの小さな誤差が重なってわずかなゆがみが生じるからだ。しかしNSXは完全に平らだった。誤差が出ることを前提にシムを噛ませて溶接するなど、人の手で微妙に調節されていたのだ。
このことに奥氏はいたく感動。優れた素材をいかに料理するか、大いに腕を鳴らす。結果、全力投球。F1レベルの技術が導入され、NSXはまさに研ぎ澄まされたGTマシンとなった。
その立役者の奥氏は、マシンづくりと並行し、もう一足の草鞋を履くこととなる。フェードアウトした大学が彼を招聘。いま、初々しい学生の前で、「独自のモノづくりの歓び」を教えている。
|

|NSX Pressの目次へ|NSX
Press Vol.20の目次へ|
NSX Press vol.20は1997年9月発行です。
|