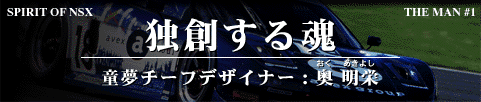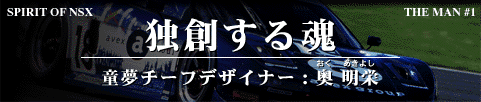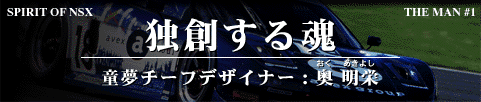
1979年。スーパーカーブームも終わりに近づく頃。京都、宝ケ池に見慣れないファクトリーが現れた。その名も童夢。ジュネーブショーに出品し話題を呼んだプロトタイプスポーツカー、あの「童夢・零」を生み出した会社である。
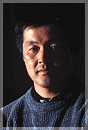 声変わりするかしないかの頃からスーパーカーが好きでたまらなかった奥
明栄氏の運命は、京都の通りがかりの場所に建った童夢の社屋を見上げたときに決定した。当時、同志社大学3回生。機械工学科に在籍。自動車部に所属しラリーをかじる。 声変わりするかしないかの頃からスーパーカーが好きでたまらなかった奥
明栄氏の運命は、京都の通りがかりの場所に建った童夢の社屋を見上げたときに決定した。当時、同志社大学3回生。機械工学科に在籍。自動車部に所属しラリーをかじる。
清潔感あふれるラガーマンを直感させる容姿に、熱き闘士を秘めた男はすぐさま行動した。かつてあこがれだったスーパーカーを自作するカロッツェリアが目の前に現れたのである。何の迷いがあろうか。一直線に童夢の門を叩いたのだ。
そのまま大学は休学、フェードアウト。その理由は至って簡単。童夢入社直後に“学生エンジニア”が手掛けたマシンは、ルマン・カー「童夢RL」。図面を引き、つくり上げたのはラジエーターまわりなど部分的なものだったが、自らが頭を悩ませつくり上げたマシンが眼前でレースを走るという、えもいわれぬ感動を知ってしまったからである。自分で書いた図面が教授に云々されるのではなく、すぐさまパーツになり、レーシングカーになることの歓び。全身の血をたぎらせたその歓びは、いまでも奥氏の胸に鮮烈に焼きついているという。
しかし、順風満帆の滑り出しというわけではなかった。ルマンに行き、レーシングカーというものはこうつくるものかと思い知らされたのである。欧州との歴史の違い。経験のなさ。世界最高のプロダクトカーレースの舞台上で、容赦なく打たれたのである。そして猛勉強。第2次オイルショックで状況は芳しくなかったが、彼らは独学で独自の“愛しきマシン”たちを製作しルマンなどに挑み続けた。
 その後、徐々にレース熱が盛り上がりはじめると、独自の技術力が評価されトヨタからグループCカーの製作を依頼される。ここでさまざまな成功と失敗をくり返し、レーシングカーづくりのノウハウを煮詰めていく。こうした活動と並行して、'85年に奥氏がはじめてチーフとなり開発したのが2輪の8耐マシン、ブラックバッファローである。ホンダエンジンを搭載するこのマシンは、無事完走を果たしたが上位を快走したというわけではなかった。ただし、2輪としてはそれまで常識になかったカーボンコンポジットのモノコックフレーム、空力を考えたフルカウル構造をとっていた。奥氏は2輪として世界初の独創的なマシンを生み出したことに感激。この時代はまだ、結果は二の次というのが正直なところだったのだ。しかし、それはほんの通過点。勝負はこれからだ。 その後、徐々にレース熱が盛り上がりはじめると、独自の技術力が評価されトヨタからグループCカーの製作を依頼される。ここでさまざまな成功と失敗をくり返し、レーシングカーづくりのノウハウを煮詰めていく。こうした活動と並行して、'85年に奥氏がはじめてチーフとなり開発したのが2輪の8耐マシン、ブラックバッファローである。ホンダエンジンを搭載するこのマシンは、無事完走を果たしたが上位を快走したというわけではなかった。ただし、2輪としてはそれまで常識になかったカーボンコンポジットのモノコックフレーム、空力を考えたフルカウル構造をとっていた。奥氏は2輪として世界初の独創的なマシンを生み出したことに感激。この時代はまだ、結果は二の次というのが正直なところだったのだ。しかし、それはほんの通過点。勝負はこれからだ。
そして1987年。三千院の程近く、比叡山の麓。高野川のほとりに本社を移転。念願の風洞実験室を建造。この風洞さえも自社製作。あくまでも独創のコンストラクター集団は、レーシングカー開発に欠かせない風洞を得て、さらにマシンづくりにのめり込んでいく。誰に教えを乞うのでもなく、奥氏は独学でレーシングカーの空力を勉強。さまざまな試行錯誤を繰り返しながらノウハウを構築していった。
|
| 次ページに続く |

|NSX Pressの目次へ|NSX
Press Vol.20の目次へ|
NSX Press vol.20は1997年9月発行です。
|