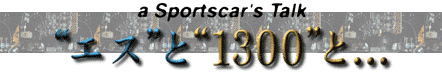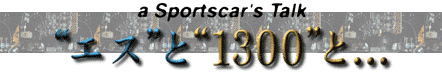1968年、メキシコオリンピック。スタジアムに囲まれたフィールドの片隅で、一人の男がショッキングなスタイルでバーをクリアした。背にしたアメリカの情熱のゼッケンを大地と対面させ、全身をひるがえし、大きく見事なアーチを描いたのだ。
それまでベリーロール一辺倒であった走り高跳びの常識をくつがえす、新しい風景が全世界に映しだされた。背面飛びの第一人者、ディック・フォスベリー。のちに“フィールドのアーチスト”と異名をとる。
その3年前、同じくメキシコの地で開かれた1965年のグランプリ。真紅のエンブレムをまとった純国産F-1マシンRA272、通称“日の丸ホンダ”がどのマシンよりも速くチェッカーフラッグを受けた。この年、世界各国のテレビの小さなスピーカーから、他のマシンとはまったく違う、突き抜けるような高音のエキゾーストノートが響いたのである。この音は、のちに“ホンダミュージック”と異名をとる。
フォスベリーは長年陸上でトラック競技を行い、好成績を納めながら、超一流選手として注目を集めるほどの存在ではなかった。しかし、選手としての命運も尽きるという頃、名もない大会で走り高跳びに参加。ぶっつけ本番、独自の工夫で背面もどきの跳躍をやってのけ、大会記録を記して優勝。この一つの挑戦と成功で彼は光った。メキシコオリンピックへの切符を手に入れたのだ。不屈の精神による革新が栄光をもたらした、一つの歴史である。
 4輪の世界でそれまでまったく注目されていなかったホンダが、独自のF-1マシンで、世界の舞台、それも頂点の舞台に躍りでた。戦後、世界へ日本の存在をアピールすることとなったホンダのこの挑戦も、革新の歴史の一つに数えられよう。革新、それがホンダの魅力なのである。
4輪の世界でそれまでまったく注目されていなかったホンダが、独自のF-1マシンで、世界の舞台、それも頂点の舞台に躍りでた。戦後、世界へ日本の存在をアピールすることとなったホンダのこの挑戦も、革新の歴史の一つに数えられよう。革新、それがホンダの魅力なのである。
今年で29年目を迎えるS600クーペのオーナー谷村憲造氏は、F-1で日本のイメージを革新したともいえるホンダの手によりつくり上げられた、独創かつ画期的な魅力に惹かれて“エス”を選んだ。
氏は、“エス”を愛するツインカムクラブの主宰者として広く知られる人物である。彼は、1台のスポーツカーを持ち続ける魅力について、「持つことに価値を感じているわけではありません。手放す理由がないからです」と、きっぱりといいきった。
それを裏づけるのは、彼がS600クーペを決してコレクションとして所有していないことだ。彼は大阪に在住しているのだが、いますぐそれで東京に行けといわれたら、イグニションを回しその場で高速道路の料金所へ向かえるという。
「山も好きなもんですから、“エス”で何度もスキーに行きました。ここから赤倉まで片道600kmです。6回は行きましたね。一度、宿の前に止めていたら完全に雪に埋まったことがありまして、他のクルマに踏まれるといけないからアンテナを伸ばしに行ったことがあります」
そして、彼は“エス”の魅力をこう語った。
「ほぼ30年たった今でも、何の苦もなくレブカウンターを振り切ります。1万1,500回転は回りますね。まったくのノーマルで、オーバーホールもしていません。そのときの音はまるでF-1なんですよ。ああ、RAの血が流れているな…と感じるんです。こんな感動を味わえるクルマがほかにあるでしょうか?
だから手放さずに乗っているんです」
次ページに続く |