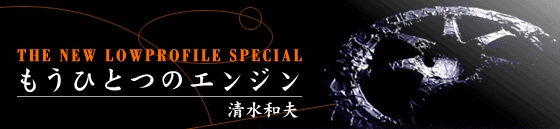
|
| |
もし、過去のレースすべてを、自由にタイヤを選択して闘ってこれたなら、もっと輝かしい戦績を残せただろう。「もし」という仮定条件をつければ、そう考えるドライバーは多いと思う。 もちろん、タイヤのサポートを受けたからこそ僕はレースを続けられたわけだし、サポートを受けたタイヤ自体自ら開発に関わっているわけだから責任の一端はある。そうした現実を嘆きたかったわけではない。ただ、タイヤの存在がそれほど重要であるということを言いたかったのだ。 よく、レースカーのポテンシャルの5割以上をタイヤが占めると言われるが、僕は、タイヤはもうひとつのエンジンと言えるほど重要なものだと考えている。レースでもロードゴーイングカーでもタイヤの性能を落とすことは、エンジンの性能を落とすぐらいの影響があるのだ。しかもタイヤは、命を載せている大切なもうひとつのエンジンなのだ。 だから、逆にタイヤの性能に支えられて勝つことだってある。 かつてラリーで闘っていた頃、タイヤの性能差で悪路のコーナリングに大きな違いが出ることが多かった。踏ん張りが効き、操舵感を確実に伝えてくれるタイヤは、面白いように速く走れる。そうでないタイヤを履いたクルマは、コーナリングのたびに不安と闘うことになる。 こんなこともあった。グループAのシビックを擁し、3度目のマカオに出かけたときだ。 決勝前日、ものすごい台風が上陸し、マカオ一帯大荒れの天気となった。翌日の決勝は危ういかと思われるほどの台風だったが、やがて小康状態となり、決勝当日は小雨が残る程度に回復した。しかし、水がはけきれないコースを走るために、全車ウェットタイヤを選択。1周6.117kmのフォーメーションラップがスタートした。 コースの途中、水平線まで見通せる小高い丘になるところがある。そこで、注意深く周囲を見渡すと、遠くの空が明るくなっていたのだ。僕は、晴れると直感した。フォーメーションラップが終わりに近づき、ピットレーンが見えると、迷わずステアリングを切った。全員がトラブルだと思っただろう。ちょうどピット正面に陣取っていたホンダの関係者は、愕然としたに違いない。 当然、クラス1位の予選グリッドは空席無効となり、僕は最後尾からのピットスタートになる。しかし、そのハンデよりも、スリックのアドバンテージを僕は選択したのだ。水は残っているが雨は止みかけている。スリックでどこまで走れるかテストデータはなかったが、何とかやれる自信はあった。 その予想は的中。1周もしないうちにもとの順位まで追い上げ、すぐにクラス2のBMW- M3を脅かすまでになった。たまらずM3陣営もドライを選択。レースは激戦となった。かなりハードなドライビングを強いられたが、結局僕は総合5位。もちろんクラス優勝を成し遂げた。 今度は、みんな僕の思わぬ好成績に愕然とすることになった。 こうしたタイヤのドラマは、レースシーンでは常識的な出来事で、この世界に生きる人は100年も前からタイヤの多大な重要性を承知している。しかしこれほどシビアであることが一般に広く認識されはじめたのは、最近のモータースポーツブーム以降かもしれない。 特に注目を集めているF-1は、タイヤのドラマを多く提供してくれた。フレッシュタイヤを履いたクルマと、タイヤ交換を目前に控えたクルマのスピード差や、猫の目のように変わる天候に合わせてのタイヤ交換合戦は、タイヤの性能差とコーナリング速度の関係、あるいは溝の有無によるドライとウェットの性能差をまざまざと見せつけてくれた。また、ほとんどのマシンがタイヤ交換するなかで、ノーチェンジで走りきるドライバーがいたりする。こうした、ドライビングテクニックとタイヤとの関係を描くシーンもあった。 スポーツカーオーナーなら、その辺りのことは周知の事実であろうが、一般に広くアピールしたことは、安全上意義があっただろう。今までまったく注意を払わなかった愛車のタイヤを見て、そのあまりの酷さに愕然として交換したオーナーや、コーナリングの際中にタイヤの状態に気を配るオーナーが増えたかもしれない。 |
| |
| |NSX Pressの目次へ|NSX
Press Vol.13の目次へ|
NSX Press vol.13 1994年3月発行 |