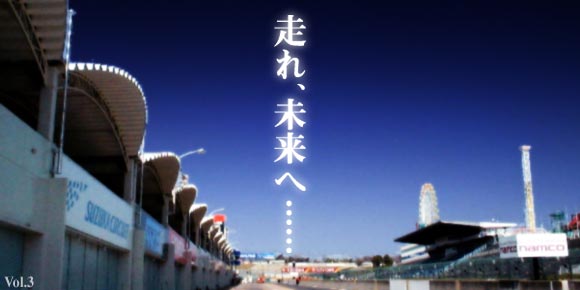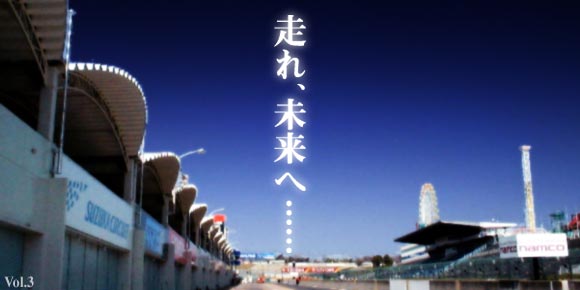|
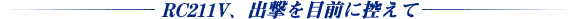 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
2002年3月19日、鈴鹿サーキット。すがすがしく晴れ渡った空の下に、RC211Vの痛快なエキゾーストノートが高々と轟いていた。4月7日の第1戦日本GPに向けたHRCのテストDay。バレンティーノ・ロッシと宇川
徹に託された2台のRC211Vは、快調にラップを重ね、テストメニューを順調にこなしていた。
「もうこの時期は、何かを直すとかの時期ではありません。目的は、タイヤのチョイスを中心とした最終的なセッティング。そして実戦的なデータ収集です」
本年度、HondaのMotoGPクラスを率いるHRCのチーム監督は、毅然とした表情で2台の走りを見つめていた。2名のライダーもすでに「開発段階」という雰囲気ではない。その顔は、まさにレースウィークそのものの緊張感にあふれている。雑誌やTV画面でお馴染みの明るくひょうきんなロッシは、そこにはいない。スタッフと真剣なやりとりを繰り返す彼の表情には、新たな時代の最先端に挑む厳しさが満ちている。
ストップウォッチには、次々と実戦を想定したタイムが刻まれていく。忙しくタイヤが付け替えられ、次々とサスペンションのセッティングがトライされる。ロッシは、ピットアウトすると本コースへの合流地点で一旦マシンを停め、スタートのタイミングをはかる練習を繰り返す。
本番20日前を切って、RC211Vとそのメンバーは、まさに実戦体制のまっただ中にあった。
|
|
 |
| スズカテストには、ロッシ&宇川それぞれの実際のチームスタッフが来日。実戦さながらの作業と入念なセッティングが精力的にすすめられた |
|
 |
|
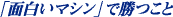 |
|
|
 |
|
「21世紀に初めて創るワークスマシンなんですから、そのコンセプトで10年は行けるモノにしたかった。いま研究所で考えられるコトの集大成となるマシンにしたかった」
スズカテストDayの前週、本田技研朝霞研究所に集まった開発メンバーから、こんなコメントがあった。その言葉は、順調な開発過程を裏付けるかのように、自信に満ちていた。
|
|
|
 |
|
「普通のマシンで勝つor負ける。面白いマシンで勝つor負ける。その四つの中でどれが一番良いか、それは面白いマシンで勝つことです。考えるのが面白いマシン、作るのが面白いマシン、走らせて面白いマシン、それで勝つ。一番つまらないのは、普通のマシンで負けるコト。ウチは、そんなのは絶対にイヤです」
確かにエンジンにも車体まわりにも、新しい発想と技術を存分に盛り込んだRC211Vは、スタート時点からはるかに「普通」を超えた存在だった。そして普通ではないだけに、心配の声がなかったわけではない。しかし…
「野茂もイチローも、充分に個性的だった。端から見れば随分と変わったフォームで、それを普通じゃないと言う人もいた。でも彼らの''個性''は、はるかに''普通''を超えて、めざましい活躍をしている」
RC211Vの第一の個性は、そのV型5気筒エンジンから発せられる圧倒的なパワーに集約される。さらに、そのエンジンの採用によって可能になった全体のコンパクトさの追求や、ハンドリングを究極まで突き詰めるパッケージングを可能にしたのも、V5の個性だった。
圧倒的なパワー、そのパワーを効率良く路面に伝える足周りと車体構成、そしてその出力特性ならではのレース展開の組み立てなど、「RC211Vならでは」…と呼べるレースこそが、RC211Vの個性であり、最大の武器にもなる。 「200数十馬力というパワーは、これをすべて使い切れるモノではないんです。それをいかに有効に使えるようにするか。それが重要な課題になります」
物理的には、軽い物体ほど「動かし易すく、停まらせ易い」ことになる。2ストロークマシンに比べて重量的に不利なRC211Vの、コーナーの突っ込みとコーナリングスピードを2ストロークマシンと同等まで引き上げ、有利な特性を持つ立ち上がりと加速性能でライバルを引き離す。
|
|
 |
| 考えるのが面白いマシン、作るのが面白いマシン、走らせて面白いマシン… つまりそれは、当初のコンセプトに基づいた「Hondaらしいマシン」そのものだった |
|
 |
|
そのためには、リアの外乱をフレームに伝えにくい、エンジンパワーを活かしきれる足周り=ユニットプロリンクサスペンションも大きな働きを担うことになる。
「ライダーにとっては、これまでのNSR500に比べて数十馬力パワーがあるわけです。つまり、同じ90度のスロットル開度でも''ハイスロットル''と同じなわけです。それを違和感なく、自在に''開けられる''マシンにしなくてはならない。いいえ、むしろ2ストロークよりも早くスロットルが開けられるマシンにしなくてはならない」
MotoGPに参戦するマシンの中で、おそらく最も大きなパワーを発揮するであろうRC211Vの、その個性とアドバンテージを活かしたパッケージへと結実させる作業…それが、最終段階に入ったテストの目的でもあった。
|
|
| これまでにないパワー、これまでにない特性、これまでにないライディングフィール、ライダーはRC211Vにゼロから馴染むことが要求された |
 |
 |
|
 |
|
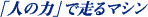 |
|
|
 |
|
「パワーがある、重量もある。タイヤにとっては非常に厳しいマシンになるのではないかと思っていました。ところが実際には、思ったよりタイヤに優しいマシンでした。タイヤに優しいということは、ライダーにも優しいマシンなんです」
タイヤサービスのメンバーが語るRC211V。それは、開発コンセプトを見事に具現化したものでもあった。
「人が扱う機械ですからね。レースディスタンス全体を通じてミスを犯しにくい、穏やかな、出しゃばらないマシンでなくてはいけない。機械が無理矢理人間を引っ張っていくような事になってはいけないんです。
疲れない、開けやすい、バトルが負担にならない。最終ラップまでライダーの力を存分に発揮出来るマシン。最終ラップまでライダーが''やる気''を保つことが出来て、それを発揮出来るマシンでなくてはならないんです」
|
|
|
 |
|
ライダーにも、好みの特性がある。ロッシは、2ストローク的な特性を好むと言う。立ち上がりのトラクション重視、ブレーキングの安定性、そして何よりも軽いハンドリング。その好みに振ったRC211Vが、ロッシに託された。一方、宇川は、もともと4ストロークが得意であり経験も豊富、自身の好みとRC211Vの相性に最初から違和感がなかったと言う。
2台の、それぞれのライダーの好みの部分を活かしたRC211Vは、順調にテストランを消化していく。仕上がりの好調さは、サインエリアでその走りを見守るチームスタッフの表情からも伺い知ることができる。
真新しいマシンに接する彼らの作業も、まったく不慣れを感じさせない域に入っている。機構や手順の理解は、グランプリで長年メカニックを務めてきた彼らにとって、すでに違和感のないものとなっている。
「この時期、ほんの小さな集中力やテンションの低下が、思わぬトラブルを生みます。同じ部品を組んでも、人間の小さなミスが大きなトラブルにつながることがある。
人が頑張っているから性能が維持出来るんです。人の力で性能を出しているんです。
人のパワーと精度…これがチーム力であり、総合戦闘力です」
いくら技術が進歩しようが、どんなにコンピュータがマシンに関わろうが、最後は「ひとの能力」でしか、マシンは走らない。
|
|
 |
| いつも通り、マシン横にしゃがみ右ステップをつかむポーズからライディングに入ったロッシ。真剣な表情はまさに臨戦態勢そのものといった雰囲気 |
 |
 |
| 宇川も、自信に満ちた表情で精力的にテストを消化。2日間のテストDayを通じて徹底した走り込みで各部のセッティングデータ集積に貢献 |
|
 |
|
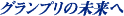 |
|
|
 |
|
「時代の大きな変わり目にこのマシンに関われたことは、多くのライダーの中でもとても幸せな事だったと思います。日本人ワークスライダーの中で、4ストロークマシンでMotoGPクラスに挑むのはボクだけですもんね。
この大きなチャンスを無駄にしないように、マシンの熟成に関して力になること、そしてMotoGPを戦うライダーとしても、しっかりとした成績を残したいです」
|
|
|
 |
|
宇川の目は、その重責にあって鋭い輝きに満ちている。
「基本は、すごく乗りやすいマシン。そのポテンシャルもすごく高いところにあると思う。後はその能力を存分に引き出してやること。それがボクらの仕事です」
ピット作業後、コースに飛び出して行く宇川は、毎回のようにフロントを高々と持ち上げてピットロードを加速していく。それはまさに「乗れていること」「馴染んでいること」を繰り返し確認するかのように、自信に満ちたライディングに見える。
頻繁にピットインを繰り返しながらセッティングの方向を探るロッシは、レースウィークに見せるあどけない表情からは想像も出来ない厳しい面もちでスタッフにコメントを発している。
|
|
 |
| 日本人ライダーとして、MotoGPに挑む唯一の4ストロークライダーとなる宇川。その肩にかかる責任に毅然とした表情でいどむ姿が印象的 |
|
 |
|
「初めてRC211Vに乗った時、ボクは2ストロークの方が面白いと思った。でも、このマシンが非常に高いポテンシャルを持っていることは充分にわかったんだ。
このスズカテストまでに、Hondaのスタッフはとても重要で大きな仕事を果たした。最初に乗った時から比べモノにならないほど、RC211Vは進化している。
でも、まだ100%だとは思わない。ボク自身もこのマシンを100%乗りこなしているとは言えない。でも、スズカのレースにはかなり高いレベルまで到達できると思っている。
そして、MotoGP最初の年を、最高の笑顔で終えられるよう、全力を尽くすよ!」
2年毎にマシンを乗り換え、2年毎に各クラスのタイトルを獲得してきたロッシにとっても、RC211Vへの“乗り換え”は、これまでにない大きな変革となる。しかしその高いポテンシャルが“天才ロッシ”のモチベーションをさらに高め、彼のより大きな飛躍のために既になくてはならない存在となっているのも確かだ。
菅生のシェイクダウンテストから、ほぼ1年。当時からは想像も出来ないほどの痛快なサウンドを残しながらストレートを駆け抜けて行くRC211Vは、いよいよその真価を本番のレースに問うことになる。
2002年4月7日、記念すべきMotoGP開幕戦。Hondaらしさを貫き、無限の夢を描いたRC211Vが、グランプリの未来に向かって、力強く加速しようとしている。 |
|
 |
| すでに、RC211Vによるレース展開を確実に想定しているロッシ。もちろん、初年度となるMotoGPクラスのタイトル争いを充分に意識している |
|
 |
 |