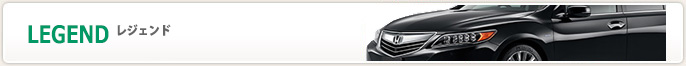夜明け前
- 4th PRELUDEさん (40代/静岡県)
- EURO L
2009年3月1日の投稿
ある期間、国内外を問わず基本的に1社で2種類以上のセダンの試乗を可能な限り実施した。
結果的に米国車以外の車は殆ど乗れた。米国車に乗れる機会が少ないこと自体、今日の不況の一因を見る思いである。少なくとも「米国が風邪をひけば、日本も風邪をひく時代」になっている。
違和感なく良い車と感じたのはFF駆動式の何台かであった。
こうしたことからHonda車の特徴は主に次のようになる。エンジンとエンジンルームの質の高いつくり/低重心化技術/環境性能の徹底追及/技術と効率と車との融合/人のための車つくり(他に3社か?)/安全性への配慮/計器類の視点移動の少なさ(例えばナビゲーションの視点移動の少なさが徹底されているのは他に独逸の1社だけである)/必要以上に大きい(重たい)タイヤは使用しない/Hondaの現行製品(2009.02.27現在)14種類の車(所有車含む)を運転・試乗した経験があるが、質が高い(他社では1社で4種類以上良いと思った製品は無い。平均2種以下。)
この20年来の車における技術で最も影響度、革命度が高いのは、VTEC機構であると思う。連続可変型バルブ・リフト量(吸気側)を搭載する車も出ているが、それらは部品数が増える、エンジン自体が高くなる(重心が高くなる)、ブレーキ用の真空倍力装置のため依然としてスロットル・バルブは必要であるし、それ以外にも弊害が見られる。
例えばエンジンブレーキを殆ど効かすことができず、フットブレーキへの依存度が高くなる。ロッカーアーム部の部品数が増え、機械的損失がかえって増える、など。結果的にボンネットが高くなり空気抵抗やデザイン面などで不利である。より良い技術は必要であるが、総合的にその技術が車の性質・性能に適合するか?良い点が増えるか?という視点や評価が抜けているのである。
Hondaは2005年発売の現行8代目CIVICで従来の技術を応用し、バルブ・リフト量を連続可変するのと同じ効果を得ており、それ以降の製品に必要に応じ適用している。
効率的な技術とは、必ずしも部品を増やすことではないし、新しいものとは限らない。以上のHondaの特徴に加え、車全体の造りこみの熟成度、搭乗者への配慮、その技術の高さでLEGENDは正に現在を走る伝説である。