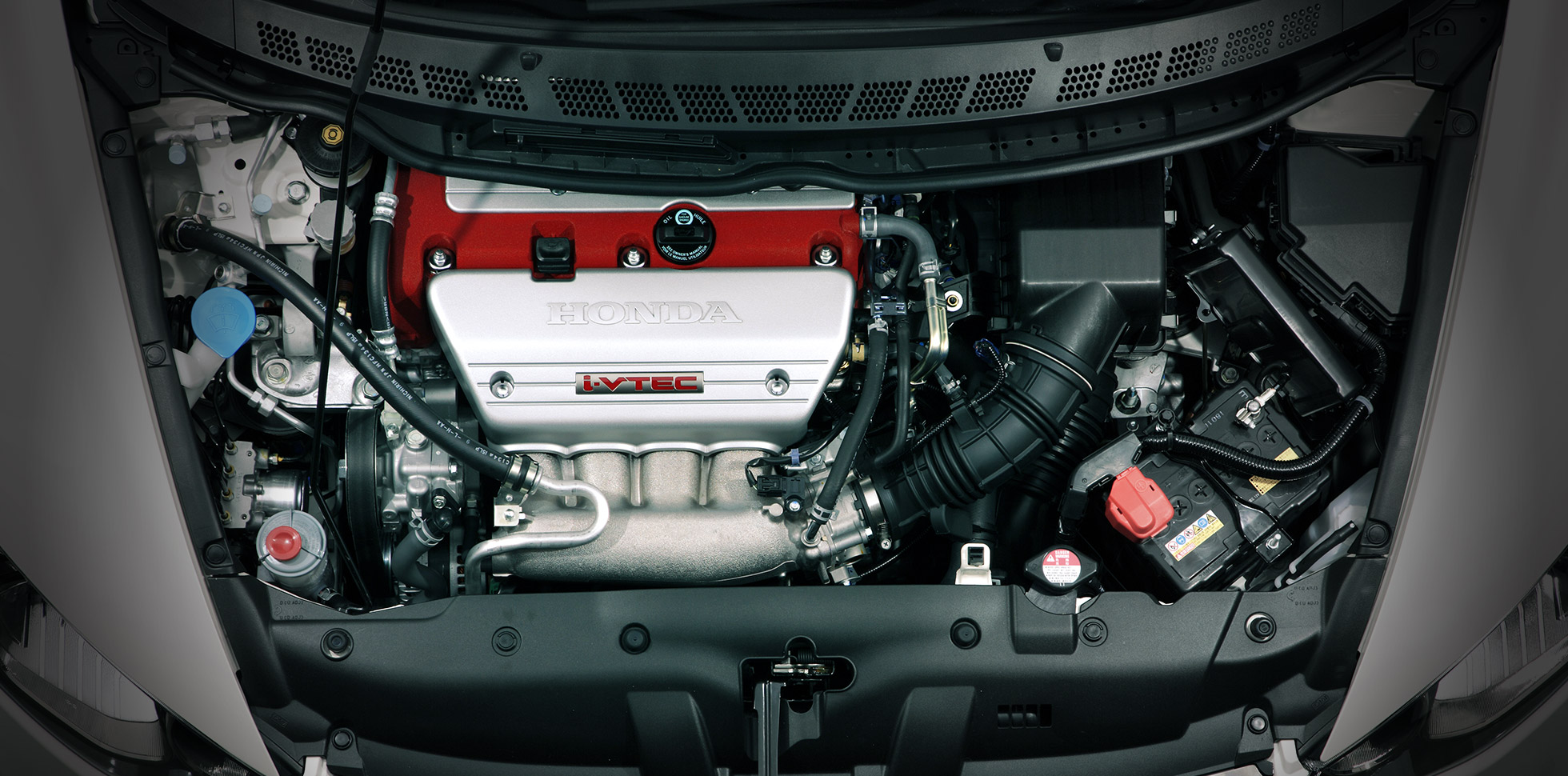
高回転用・低回転用という2種類のカムを使い分け、痛快なスポーツ性能と日常の扱いやすさや経済性を高次元に両立させる、Honda独創の可変バルブタイミング・リフト機構「VTEC」。歴代のVTECエンジンを振り返りながら、Hondaスポーツに共通するキャラクターに迫っていきます。今回は、1990年にデビューした初代NSXに搭載された「C30A」についてご紹介します。
スペック(1990 NSX)
| エンジン形式 | C30A |
|---|---|
| エンジン種類 | 水冷V型6気筒横置 |
| 弁機構 | DOHC ベルト駆動 吸気2 排気2 |
| 総排気量(cm³) | 2977 |
| 内径×行程(mm) | 90.0×78.0 |
| 圧縮比 | 10.2 |
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 最高出力(PS/rpm) | 280/7,300(5MT) |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 30.0/5,400 |
主な搭載車種
- 1990 NSX
「自然吸気の極限」を目指した3.0L V6 DOHC VTEC
レーシングドライバーなどの限られた人々だけでなく、オーナーとなったすべての人々が享受できる高性能──それこそが初代NSXの目指したもの。
パワーだけを追い求めればターボという選択肢も存在したが、当時のターボはドライバビリティに難があり、エンジン性能をフルに活かして走るためには「人間がマシンに合わせていく」というテクニックが要求されてしまう。特定の領域でしか性能を発揮できない、レーシングエンジンのような特性もまたしかり。
そうした「旧世代」のスーパースポーツからの決別を象徴するもののひとつが、NSXに搭載された、この3.0L V6 DOHC VTECエンジンである

世界一級のパフォーマンスを持ちながら、それを心の昂ぶりとともに小気味よく操ることができる。そんな人間の感覚に沿った究極のドライバビリティを実現するために、Hondaは自然吸気エンジンにこだわった。レイアウトは、エンジンそのものをコンパクトに設計できるV型6気筒を選択。そこに高回転用/低回転用のカムを切り替えることでレーシングエンジンに迫る高速性能と、実用域での力強さや扱いやすさを高次元で両立させるVTECを組み合わせ、誰もが、あらゆるシーンでパフォーマンスを引き出せる特性を目指したのである。
共鳴チャンバー容量切換えインテークマニホールドシステム
インテークマニホールドには、自然吸気エンジンの「共鳴効果」と「慣性効果」を利用してシリンダー内により多くの混合器を導入する新開発の「共鳴チャンバー容量切換えインテークマニホールドシステム」を採用。
低・中速域では、フラスコのような容器の入口にスピーカーの音を近づけると内部の空気が震え始めるという「共鳴」の原理をエンジンの吸入行程に利用してトルクアップを実現。
4,800rpm付近からはチャンバー内部にあるシャッターバルブを開くことで慣性効果を生み、高速域での出力アップも達成。VTECの「ハイカム」領域による吸気効率向上とあいまって、全域でのパフォーマンスアップを実現していた。

その後の進化
1997年には、ピストン摺動部に鋳込まれている鋳鉄ライナーをFRM(繊維強化金属)に材料置換することで、シリンダー間壁を10mmから7mmに縮小。ボアアップにより、排気量を3.2Lに拡大させている。これによって高回転域の気持ちよさを活かしながら、全域でトルクを向上させ、より力強く爽快なエンジンフィーリングを実現。1999年には環境性能を向上させた「HONDA LEV」仕様へと進化も果たしている。
2005年12月に生産を中止したあとも、SUPER GTでは「NSX-GT」が2009年まで参戦を継続。C32型エンジンをベースとしたエンジンが高い戦闘力を発揮し、そのポテンシャルをモータースポーツファンに印象づけた。

2009年最終戦のNSX-GT。ポール・トゥ・ウィンで有終の美を飾った。