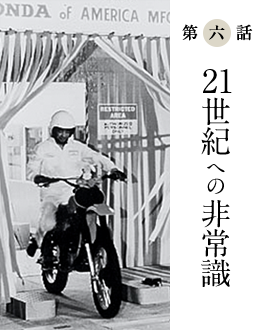ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


第三話 自立航法の旅
日が昇るには間があった。
まどろみを破り十数台のエンジン音が近づいてきた。
アメリカ第7軍に緊張が走った。
オーストリアとドイツ・バイエルン地方の国境地帯――深い森の影から次々にトラックが出現した。
めざめた太陽は容赦もなく、その廃車寸前の落剥をさらけだし、先頭車両の白い旗をまばゆく見せた。男が降りた。
「私はウェルナー・フォン・ブラウン。五〇〇人の科学者、数台分の部品、設計図の束と共に投降を希望する」
まどろみを破り十数台のエンジン音が近づいてきた。
アメリカ第7軍に緊張が走った。
オーストリアとドイツ・バイエルン地方の国境地帯――深い森の影から次々にトラックが出現した。
めざめた太陽は容赦もなく、その廃車寸前の落剥をさらけだし、先頭車両の白い旗をまばゆく見せた。男が降りた。
「私はウェルナー・フォン・ブラウン。五〇〇人の科学者、数台分の部品、設計図の束と共に投降を希望する」
――この瞬間アメリカの宇宙開発は始まった。彼らはロケットV2号の研究陣だったからである。
ドイツ敗戦直前、1945年5月3日であった。―――
翌1946年秋、静岡県浜松市山下町に、ある町工場が生まれた。
従業員は一二人。入口には「本田技術研究所」と看板がかかっていた。
戦後の混乱期、この会社がバイク製造にのりだそうと試みた1948年、大阪――後の世が団塊の世代と呼ぶ
新生児たちの中に、高橋常夫はいた。
この生粋の浪速っ子は、大阪大学工学部電子工学科へ進んだ。
――時の流れは人と企業の出会いをひそかに仕込んでいた。
1970年代初期、(株)本田技術研究所の和光センターの一室――
「あれ、高橋は?」
「あ、田上さん、奴は瞑想中かな」「え、また畳か。つ
この生粋の浪速っ子は、大阪大学工学部電子工学科へ進んだ。
――時の流れは人と企業の出会いをひそかに仕込んでいた。
1970年代初期、(株)本田技術研究所の和光センターの一室――
「あれ、高橋は?」
「あ、田上さん、奴は瞑想中かな」「え、また畳か。つ
かまえにゃ」
 田上勝利は飛び出した。畳とは近所にある畳の部屋だ。
田上勝利は飛び出した。畳とは近所にある畳の部屋だ。
会社外での発想に使う。発想に昼も夜もない。
時には居酒屋であったりした。そんな時代だった。
 田上勝利は飛び出した。畳とは近所にある畳の部屋だ。
田上勝利は飛び出した。畳とは近所にある畳の部屋だ。会社外での発想に使う。発想に昼も夜もない。
時には居酒屋であったりした。そんな時代だった。
「田上さんと高橋の研究って何」
「自動車にジャイロを使えないかというのさ」
「ん、ジャンボとか航空機の?」
「慣性航法装置のもとだな」
「確かアポロ計画でもさ」
「うん、元々ロケットの父と呼ばれるブラウン博士の研究から出た装置だ。
このおかげでアポロ11号は地球から三八万キロも離れた月面にピンポイント着陸できた」
「巨大科学の産物だな。第一、自動車に入るのか」
「自動車にジャイロを使えないかというのさ」
「ん、ジャンボとか航空機の?」
「慣性航法装置のもとだな」
「確かアポロ計画でもさ」
「うん、元々ロケットの父と呼ばれるブラウン博士の研究から出た装置だ。
このおかげでアポロ11号は地球から三八万キロも離れた月面にピンポイント着陸できた」
「巨大科学の産物だな。第一、自動車に入るのか」
「この前、田上さんが小型機用ジャイロをバラしたら、手より少し大きめの物が何と部品二〇〇点、全て超精密品の上に――」
「調整に何十時間か必要?ひゃあ、量産できない。そもそもジャイロを使う目的は?」
「不明、未知。それも研究だ」
――何を達成するかわからぬままの開発などあるのだろうか。
本田にはあるのだ。この時の田上と高橋がそうだった。
「・・でだ、クメセンのキーワードは『誘導』だ」「田
「調整に何十時間か必要?ひゃあ、量産できない。そもそもジャイロを使う目的は?」
「不明、未知。それも研究だ」
――何を達成するかわからぬままの開発などあるのだろうか。
本田にはあるのだ。この時の田上と高橋がそうだった。
「・・でだ、クメセンのキーワードは『誘導』だ」「田
上さん、その意味は」
「高橋、お前がそれを考えるんだ。やる気あるか」
「はい!」
高橋の大きな体から元気な声が出た。
「お前、電子工学出にみえんよ」
「探検部出身でもありますからね」―――高橋のような存在は異色だ。
クメセンこと、久米是志専務(後三代目社長)はじめ俗に言う機械屋がひしめく中で彼は遊軍である。
が、一見山男のようなこの野性の冒険児の内には、鬼が
「高橋、お前がそれを考えるんだ。やる気あるか」
「はい!」
高橋の大きな体から元気な声が出た。
「お前、電子工学出にみえんよ」
「探検部出身でもありますからね」―――高橋のような存在は異色だ。
クメセンこと、久米是志専務(後三代目社長)はじめ俗に言う機械屋がひしめく中で彼は遊軍である。
が、一見山男のようなこの野性の冒険児の内には、鬼が
棲んでいた。電子と機械、両工学の学際領域を究めたいという夢の鬼だ。
『誘導』という言葉ひとつで何ができるか。鬼は、しかし何かをそこに感じた。
諦めを知らない田上は自動車に向くジャイロを必死で世界に求めた。
原子核、光ファイバー、振動――そしてガスレートジャイロにぶつかった。
ガスの流れで基準線をつくり方向を感知するものだ。
「これだ、応用を考えろ」
『誘導』という言葉ひとつで何ができるか。鬼は、しかし何かをそこに感じた。
諦めを知らない田上は自動車に向くジャイロを必死で世界に求めた。
原子核、光ファイバー、振動――そしてガスレートジャイロにぶつかった。
ガスの流れで基準線をつくり方向を感知するものだ。
「これだ、応用を考えろ」
日曜日、高橋はゴロ寝と決めた。その年生まれた息子が這ってきた。
頬がゆるむ。生き物は動く、か。! 深層意識から何か急に浮上した。
そうだ。生き物は動く。
みな自分の位置を知っている。
渡り鳥はなぜ渡りができる。サケはなぜ川に帰れる。脳裡に、学生時代探検した沖永良部島の海中が浮かぶ。
あの魚たちでさえ・・ヒマワリさえ太陽を向く。
頬がゆるむ。生き物は動く、か。! 深層意識から何か急に浮上した。
そうだ。生き物は動く。
みな自分の位置を知っている。
渡り鳥はなぜ渡りができる。サケはなぜ川に帰れる。脳裡に、学生時代探検した沖永良部島の海中が浮かぶ。
あの魚たちでさえ・・ヒマワリさえ太陽を向く。
今や飛行機も船も慣性航法をもつ。自力で位置を知る。
自動車だけが知らないとは。
目的はできた。完全自立航法の実現だ。
技術は――まだない。ガスレートジャイロだけが手がかりだ。
先に理想が走り、後に技術を創る本田の気質が高橋の内なる夢の鬼の持久力とむすびついた。
1970年代初期はマイコン手作り時代だ。高橋は航法コンピュータ導入を確信したが、この頃に使えるほどの
自動車だけが知らないとは。
目的はできた。完全自立航法の実現だ。
技術は――まだない。ガスレートジャイロだけが手がかりだ。
先に理想が走り、後に技術を創る本田の気質が高橋の内なる夢の鬼の持久力とむすびついた。
1970年代初期はマイコン手作り時代だ。高橋は航法コンピュータ導入を確信したが、この頃に使えるほどの
マイクロプロセッサは存在していない。
えい、なくてもやるのだ。時代の方でついてくるさ。
未知への強烈な魅力だ。
全盛の電卓を幾つもバラしその半導体を使ったりした。
大問題はジャイロの精度だ。
自動車は直進でも実は絶えず微妙に左右にゆれている。かつ、くり返す。
微視的には真の直進はありえない。しかも信号停止などでじっとしていても出る微振動がある。時が立つほど加算され、誤差になる。
えい、なくてもやるのだ。時代の方でついてくるさ。
未知への強烈な魅力だ。
全盛の電卓を幾つもバラしその半導体を使ったりした。
大問題はジャイロの精度だ。
自動車は直進でも実は絶えず微妙に左右にゆれている。かつ、くり返す。
微視的には真の直進はありえない。しかも信号停止などでじっとしていても出る微振動がある。時が立つほど加算され、誤差になる。
壁を破ると、また壁の連続だ――。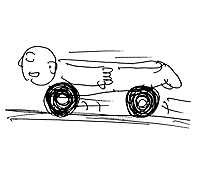
模擬実験してみる。芦ノ湖一周だ。
出発と到着が同じだから、誤差を判定しやすい。だが何度やっても軌跡は湖に飛びこんだ―――くそ! 一体どこがおかしいのか。
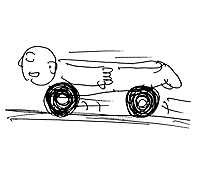
模擬実験してみる。芦ノ湖一周だ。
出発と到着が同じだから、誤差を判定しやすい。だが何度やっても軌跡は湖に飛びこんだ―――くそ! 一体どこがおかしいのか。
――「よう、どうだい」
ある朝、声が飛んだ。徹夜の眠気がふっ飛ぶ。久米専務だ。
「いや、どうもダメです」
「なにが、どれ」
久米は隣に座りこみメモを始めた。
「うん、ここはこう考えたらどうなんだ」
――こんな実験的研究をトップが共に考える――俺は――孤軍奮闘じゃない。
ある朝、声が飛んだ。徹夜の眠気がふっ飛ぶ。久米専務だ。
「いや、どうもダメです」
「なにが、どれ」
久米は隣に座りこみメモを始めた。
「うん、ここはこう考えたらどうなんだ」
――こんな実験的研究をトップが共に考える――俺は――孤軍奮闘じゃない。
三十代前の高橋の胸の奥で何かがふっきれていた。
開発に馬力がかかった――。
1982年、本田はナビゲーション・システム第一世代を発表、アコードのオプションに登場させた。
この時点で基本技術はすべて完成していた。機能的にはジャンボジェット等の慣性航法とおなじだ。
つまり、電波や地磁気に頼らない。外乱に影響されず、現在位置、方向、走行軌跡を知る。知らない道も迷わず、夜も安心できる。
開発に馬力がかかった――。
1982年、本田はナビゲーション・システム第一世代を発表、アコードのオプションに登場させた。
この時点で基本技術はすべて完成していた。機能的にはジャンボジェット等の慣性航法とおなじだ。
つまり、電波や地磁気に頼らない。外乱に影響されず、現在位置、方向、走行軌跡を知る。知らない道も迷わず、夜も安心できる。
この年以降、航法開発は急に盛んになり、地磁気や米国防総省のGPS衛星を利用するものが多かった。
が、これは受信を大前提にする。ビル群、地下道、トンネル等、地磁気や電波が届きにくい所はどうか。
航法の基準を、自動車の外にするか、内部にもつか。その違いは大きい。
高橋は、なぜ自立航法にこだわったのか。社外で時に力説した。
「情報化というが、自動車に本当に大切な情報って何です。自動車は移動体だ。なら、どんな時も場合も正確な
が、これは受信を大前提にする。ビル群、地下道、トンネル等、地磁気や電波が届きにくい所はどうか。
航法の基準を、自動車の外にするか、内部にもつか。その違いは大きい。
高橋は、なぜ自立航法にこだわったのか。社外で時に力説した。
「情報化というが、自動車に本当に大切な情報って何です。自動車は移動体だ。なら、どんな時も場合も正確な
自己位置の認知が第一ではないですか」
――自動車には心臓があり、脚があった。が、神経はなく、五感のない時代が続いた。
やがて自動車が真の生き物になるなら――動物は自分の位置を知るからこそ身を守ることもできる。ナビとは不安を解消する安全システムでもある。
1989年、本田ナビ・システム第二世代発表。位置誤差の補正力は更に増し、地図にない細道や新道を経由しても補正できる。
――自動車には心臓があり、脚があった。が、神経はなく、五感のない時代が続いた。
やがて自動車が真の生き物になるなら――動物は自分の位置を知るからこそ身を守ることもできる。ナビとは不安を解消する安全システムでもある。
1989年、本田ナビ・システム第二世代発表。位置誤差の補正力は更に増し、地図にない細道や新道を経由しても補正できる。
全てが極めて実用的になった。
今、高橋があの頃の久米の年齢になった。この秋、息子は十七歳だ。
今度は俺が「どうだ」と言う番か。旅は若い世代が継ぐのだ。(終)
今、高橋があの頃の久米の年齢になった。この秋、息子は十七歳だ。
今度は俺が「どうだ」と言う番か。旅は若い世代が継ぐのだ。(終)

 テクノロジー図鑑
テクノロジー図鑑