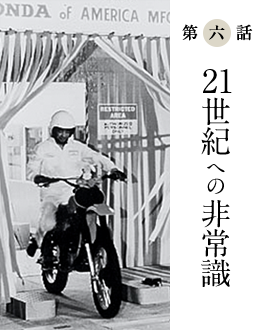ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


第四話 安全は、こころ
「えっ、両手が使えないのですか?それでも車が運転できるようにならないかと・・・」
吉村征之は驚きの目を刀川哲也に向けた。
「そうです、ぜひお願いしたい。サリドマイドのために両上肢障害です。
しかし、車に乗れれば、もっと自由に社会生活が広がります。」
刀川も、まっすぐに吉村を見た。
思わず視線を外した吉村の目は、ホンダ安全運転普及本部の壁をさまよう。
吉村征之は驚きの目を刀川哲也に向けた。
「そうです、ぜひお願いしたい。サリドマイドのために両上肢障害です。
しかし、車に乗れれば、もっと自由に社会生活が広がります。」
刀川も、まっすぐに吉村を見た。
思わず視線を外した吉村の目は、ホンダ安全運転普及本部の壁をさまよう。
安全運転のポスター。鈴鹿サーキットの交通教育センターのスケジュール表。
年が明けたばかりの1981年のカレンダー。
そういえば、今年は国連の国際障害者年だ─ 吉村は向き直った。
刀川はホンダ肥後の販売主任だが熊本市にある障害者だけのドライバーズクラブ『セーフティクラブ肥後』の事務局長である。
彼は訥訥として語る。
このクラブは3年前70人で発足したが、今では250
年が明けたばかりの1981年のカレンダー。
そういえば、今年は国連の国際障害者年だ─ 吉村は向き直った。
刀川はホンダ肥後の販売主任だが熊本市にある障害者だけのドライバーズクラブ『セーフティクラブ肥後』の事務局長である。
彼は訥訥として語る。
このクラブは3年前70人で発足したが、今では250
人にもなる。9割の会員が仕事を持つ。今年1月12日に『旅立とう、いま・こずえさん20才の青春』という特集のテレビ放映があった。その中で西ドイツ(当時)のサリドマイド障害者が足だけで運転する様子が紹介された。それを見た会員たちが夢をもった。同じ障害者の仲間のひとりに運転免許を、という夢である。
その人は白井(旧姓辻)典子さんといって、昨年全国で初めて公務員試験に合格し、熊本市役所に勤務している。
──吉村は目を開かれる思いがしていた。
その人は白井(旧姓辻)典子さんといって、昨年全国で初めて公務員試験に合格し、熊本市役所に勤務している。
──吉村は目を開かれる思いがしていた。
本部発足以来、安全の仕事に携わり10年が経つ。
安全とは結局、人の心に帰着すると思いだした頃だった。
ほどなくして吉村は、その白井さんからの手紙を受け取った。

安全とは結局、人の心に帰着すると思いだした頃だった。
ほどなくして吉村は、その白井さんからの手紙を受け取った。
──自分は生まれて以来、母の助けに支えられてきた。両手が使えない自分だが、運転できる方法はないか。いつも自分をおぶってくれた母を、今度は自分が後ろに乗せて、一度でいい、ドライブ旅行に連れて行ってあげたい。
そんな意味の文章が綿々と連ねてあった。この手紙、どうやって書いたのだろう。吉村は想像した。
どうやって? ── 足で書いたのだ!
なにか経験したことのない強烈な思いが吉村の全身を打った。
そんな意味の文章が綿々と連ねてあった。この手紙、どうやって書いたのだろう。吉村は想像した。
どうやって? ── 足で書いたのだ!
なにか経験したことのない強烈な思いが吉村の全身を打った。
リーン。隣の席の電話が鳴った。
同僚が出た。彼の目が暗くなる。吉村には、もう用件がわかった。
事故か、怪我か。クレームだ、またしても。
安全のセクションというと、あらゆるクレーム、要望がおしよせる。この交通社会では、人は不測の事態に出あうと、「安全」の看板を掲げたところへ、他に持っていきようのない思いをぶつけてくるのだ。
しかし、と吉村は思う。
安全というと、すぐに運転技術と人は言うが、そうじゃない。それだけではない。車を楽しく正しく使うというのは結局、自分を含め人を大切にするということなのだ。だが、この心がこの世でもっとも難しい。
吉村は頭をめぐらす。社会的弱者と呼ばれる、子供、高齢者、そして白井さんのような「身体障害者」の人たちに──
俺の安全の仕事が、人のための仕事なら、人はみな平等だと気づいてもらう仕事なら、こたえるべきだ。が、大問題がある。
吉村は頭をめぐらす。社会的弱者と呼ばれる、子供、高齢者、そして白井さんのような「身体障害者」の人たちに──
俺の安全の仕事が、人のための仕事なら、人はみな平等だと気づいてもらう仕事なら、こたえるべきだ。が、大問題がある。
吉村は同僚の広報部・松本健夫課長と相談した。
「足だけの運転操置は可能だ」
「が、法律では両上肢障害者の運転は不可だ」
「法が変わらぬ限り無意味か」
「困難な仕事だ。会社の了解もいる」
「そうだな、よし、行くか」
二人は役員室へ直談判に出かけた。
役員室は 即座に断下した。簡潔明瞭であった。
「いいことじゃないか、どこまでできるものかわからんが、やれるだけやってみろ」
「足だけの運転操置は可能だ」
「が、法律では両上肢障害者の運転は不可だ」
「法が変わらぬ限り無意味か」
「困難な仕事だ。会社の了解もいる」
「そうだな、よし、行くか」
二人は役員室へ直談判に出かけた。
役員室は 即座に断下した。簡潔明瞭であった。
「いいことじゃないか、どこまでできるものかわからんが、やれるだけやってみろ」
ふたりは奮い起った。直ちに特別予算が組まれた。有志を募った。
本田技術研究所から増井英夫主任研究員が、テック・プロダクション(ホンダ関連会社)から佐藤博主任が参加した。松本は社内、吉村は社外と、折衝の分担を決めた。
チームの仕事は調査から始まった。両上肢障害者の運転補助装置の開発は欧米ではどうなっているのか。
「2タイプの装置があるらしいな」
「ハンドル操作を足の前後運動で行うか、円運動で行
本田技術研究所から増井英夫主任研究員が、テック・プロダクション(ホンダ関連会社)から佐藤博主任が参加した。松本は社内、吉村は社外と、折衝の分担を決めた。
チームの仕事は調査から始まった。両上肢障害者の運転補助装置の開発は欧米ではどうなっているのか。
「2タイプの装置があるらしいな」
「ハンドル操作を足の前後運動で行うか、円運動で行
うかだ」
「どっちが人間工学的にスムーズなんだ」──
昼夜を徹して内外の専門書、研究論文、データを調べていった。
医学的見地から判断を仰ごうと、増井は熊本機能病院の米満院長を訪ねた。
「人間の足は回転させるより、前後に動かしたほうが動きが正確だし、無理がありませんね」── 刀川の話にあった、テレビ放送でも紹介されたフランツシステムだ、と増井は直感した。
「どっちが人間工学的にスムーズなんだ」──
昼夜を徹して内外の専門書、研究論文、データを調べていった。
医学的見地から判断を仰ごうと、増井は熊本機能病院の米満院長を訪ねた。
「人間の足は回転させるより、前後に動かしたほうが動きが正確だし、無理がありませんね」── 刀川の話にあった、テレビ放送でも紹介されたフランツシステムだ、と増井は直感した。
増井、佐藤は直ちに西ドイツへ飛んだ。
チームが発足し1ケ月と経たない3月23日、フランクフルト空港に降り立った二人は、休む間もなくアウトバーンを疾走し、開発者フランツ氏を訪ねた。
二人はすぐに彼自身が両上肢障害者と知った。
40代半ばの理知的な人物だった。20歳の時、仕事中事故に遭遇したという。が、自らこの構想を生み、開発に9年、改良に15年を費やしていた。
二人はシステムの指導を2週間受け、またフランツ氏の勤務先で装置製造元でもあるBBC社(ブラウンボベリ
チームが発足し1ケ月と経たない3月23日、フランクフルト空港に降り立った二人は、休む間もなくアウトバーンを疾走し、開発者フランツ氏を訪ねた。
二人はすぐに彼自身が両上肢障害者と知った。
40代半ばの理知的な人物だった。20歳の時、仕事中事故に遭遇したという。が、自らこの構想を生み、開発に9年、改良に15年を費やしていた。
二人はシステムの指導を2週間受け、またフランツ氏の勤務先で装置製造元でもあるBBC社(ブラウンボベリ
ー社・スイスの重電気メーカー)の技術援助を取りつけた。
しかし懸念がひとつあった。
心臓部のステアリングギア・ユニット(足の前後運動でステアリングを回転させる装置)は、

しかし懸念がひとつあった。
心臓部のステアリングギア・ユニット(足の前後運動でステアリングを回転させる装置)は、
当然ながら特許である。── これはコストが増える、かといって、別の装置開発には時間がかかる、金もいる。
困った。
だが、最後の日、フランツ氏は思いもかけないことを申し出た。
「ヘル・マスイ、ヘル・サトウ、もうお教えすることはない。ユニットは原価で進呈します。特許料は結構です。はるか日本の私の仲間のために─」
二人は同じ技術者として、彼の気持ちが痛いほどわかっ
困った。
だが、最後の日、フランツ氏は思いもかけないことを申し出た。
「ヘル・マスイ、ヘル・サトウ、もうお教えすることはない。ユニットは原価で進呈します。特許料は結構です。はるか日本の私の仲間のために─」
二人は同じ技術者として、彼の気持ちが痛いほどわかっ
た。
いつまでも頭を上げない二人に彼は少し面食らった。──
この間、東京では吉村が東奔西走していた。
どうすれば両上肢障害者が運転できる法的条件が整うのか。アドバイスを求め、あらゆる関係官庁を訪ねた。
「その車がないと判断不可能だ、できた上で考えよう」これが回答だった。
車の完成を待つほかない。二人は4月7日帰国した。
4月15日ユニットが到着、すぐに改造を始めた。花嵐
いつまでも頭を上げない二人に彼は少し面食らった。──
この間、東京では吉村が東奔西走していた。
どうすれば両上肢障害者が運転できる法的条件が整うのか。アドバイスを求め、あらゆる関係官庁を訪ねた。
「その車がないと判断不可能だ、できた上で考えよう」これが回答だった。
車の完成を待つほかない。二人は4月7日帰国した。
4月15日ユニットが到着、すぐに改造を始めた。花嵐
に気づくゆとりもなく、研究所の多方面のメンバーが昼も夜もなく超特急作業に邁進した。
本来左ハンドル用のシステムのため、改造に多々工夫が必要だ。スペース、重量増、剛性など新しい問題も丹念に解決して、第1号車完成に漕ぎ着けた。
5月23日、埼玉県のホンダ交通教育センター。
上京した白井(旧姓辻)典子さんは、佐藤の導きで車に乗った。
30分ほど訓練し高速コースに出た。
往復するうち、時速60kmで走っていた。
本来左ハンドル用のシステムのため、改造に多々工夫が必要だ。スペース、重量増、剛性など新しい問題も丹念に解決して、第1号車完成に漕ぎ着けた。
5月23日、埼玉県のホンダ交通教育センター。
上京した白井(旧姓辻)典子さんは、佐藤の導きで車に乗った。
30分ほど訓練し高速コースに出た。
往復するうち、時速60kmで走っていた。
「あっ、動いた」
典子さんの第一声だった。
吉村には声だけがわかった。目が潤んで見えなかったのだ。
しかし、この時、吉村達の苦闘は始まったばかりだった。
6月、東京霞ケ関官庁街。
梅雨空のもと、連日、吉村は第1号車の説明に回った。
公道を走れる車ではないのでトレーラーで運ぶ。
典子さんの第一声だった。
吉村には声だけがわかった。目が潤んで見えなかったのだ。
しかし、この時、吉村達の苦闘は始まったばかりだった。
6月、東京霞ケ関官庁街。
梅雨空のもと、連日、吉村は第1号車の説明に回った。
公道を走れる車ではないのでトレーラーで運ぶ。
──どうかこの車のシステム、機能を理解してほしい。法改正を考えてほしい。このままでは両上肢障害者は日本では運転できない。──
吉村は大きく2つの指摘を受けた。
ひとつは、操作性の問題。
もうひとつは、足だけの運転で心配される緊急時対応など、安全性検証の問題。さらに様々な面から、積極的な暖かいアドバイスを受けた。
検討すべきことは山ほど出てきた。ひとつ、またひとつ。
吉村は大きく2つの指摘を受けた。
ひとつは、操作性の問題。
もうひとつは、足だけの運転で心配される緊急時対応など、安全性検証の問題。さらに様々な面から、積極的な暖かいアドバイスを受けた。
検討すべきことは山ほど出てきた。ひとつ、またひとつ。
粘り強く消してゆく作業が続く。
運転に必要な部分はハードの改良で対応していった。しかし、運転に直接関係しない部分では、吉村が深く同意した白井(旧姓辻)典子さんの考えがあった。
──全て自動化すれば楽かもしれません。でも、それはただ高価で機能的に自己完結する車です。むしろ周りの方の手を借りて機能を補ってもらうことで、障害者がいろいろな人とコミュニケートできる。そんな開かれた車にすることが、平等ということでは──。
こたえてゆくための様々な実際の走行テストが不可欠に
運転に必要な部分はハードの改良で対応していった。しかし、運転に直接関係しない部分では、吉村が深く同意した白井(旧姓辻)典子さんの考えがあった。
──全て自動化すれば楽かもしれません。でも、それはただ高価で機能的に自己完結する車です。むしろ周りの方の手を借りて機能を補ってもらうことで、障害者がいろいろな人とコミュニケートできる。そんな開かれた車にすることが、平等ということでは──。
こたえてゆくための様々な実際の走行テストが不可欠に
なってきた。
かといって、たびたび典子さんが上京するのも難しい。
吉村と松本は官庁、本社、研究所を日夜走り回って汗だくになり、一方では手続き上の膨大な書類に忙殺され、焦燥の色が濃くなっていった。
その矢先突然朗報が飛び込んできた。あのフランツ氏が、夏休みを利用して来日するというのである。
8月下旬、吉村と松本はフランツ夫妻と東京、京都、熊本を回った。
かといって、たびたび典子さんが上京するのも難しい。
吉村と松本は官庁、本社、研究所を日夜走り回って汗だくになり、一方では手続き上の膨大な書類に忙殺され、焦燥の色が濃くなっていった。
その矢先突然朗報が飛び込んできた。あのフランツ氏が、夏休みを利用して来日するというのである。
8月下旬、吉村と松本はフランツ夫妻と東京、京都、熊本を回った。
行政諸官庁、身体障害者団体の目の前で、1号車に乗ったフランツ氏は見事な運転技術を見せた。
自分のサングラスを後輪の後ろに置かせ、急坂で発進するような技まで披露した。それは両手が不自由でも運転はなんら問題のないことの、生

自分のサングラスを後輪の後ろに置かせ、急坂で発進するような技まで披露した。それは両手が不自由でも運転はなんら問題のないことの、生
きた証明であった。
彼は諸官庁に、西ドイツでの法的認定の経緯も説明した。関係者の心が動き出した。── 吉村は一陣の涼風を確かに感じた。
9月、指摘を全て反映した2号車、3号車改造に全力で取り組んだ。わずか1ケ月で完成させ、社内走行実験を繰り返した。
11月13日、ついに国会で「足で運転する車について」の質疑が行われた。
続く4日間、府中の運転免許試験場で、技能試験官の走
彼は諸官庁に、西ドイツでの法的認定の経緯も説明した。関係者の心が動き出した。── 吉村は一陣の涼風を確かに感じた。
9月、指摘を全て反映した2号車、3号車改造に全力で取り組んだ。わずか1ケ月で完成させ、社内走行実験を繰り返した。
11月13日、ついに国会で「足で運転する車について」の質疑が行われた。
続く4日間、府中の運転免許試験場で、技能試験官の走
行テストが実施された。
同月23日、待ちに待った道路交通法施行令一部改正が発表された。──
吉村は心の底から深い息をついた。これで両手が不自由な人にも運転免許証が交付される。
年が明けてすぐ、ホンダはシビック改造申請を東京陸運局に提出。
前後してなお様々な走行テストが行われ、4月19日認可、同月30日に熊本陸運局でナンバー登録。交付ナンバーは1982だった。
同月23日、待ちに待った道路交通法施行令一部改正が発表された。──
吉村は心の底から深い息をついた。これで両手が不自由な人にも運転免許証が交付される。
年が明けてすぐ、ホンダはシビック改造申請を東京陸運局に提出。
前後してなお様々な走行テストが行われ、4月19日認可、同月30日に熊本陸運局でナンバー登録。交付ナンバーは1982だった。
官報に法改正の詳細が発表され、一字一句に吉村は熱いものがこみあげてくるのを感じないではいられなかった。
7月16日、典子さんは筆記、実技とも1回で合格した。それは、あの刀川との猛特訓の成果だった。
以来11年、ホンダ・フランツシステムの車は、23台が世に送り出された。
こうした車は地道に継続することに意義があるのではないだろうか。
7月16日、典子さんは筆記、実技とも1回で合格した。それは、あの刀川との猛特訓の成果だった。
以来11年、ホンダ・フランツシステムの車は、23台が世に送り出された。
こうした車は地道に継続することに意義があるのではないだろうか。
1993年3月15日、典子さんに新装置を備えた2台目が、ホンダ・クリオ熊本から納車された。
──伝え聞いた吉村は、20年にわたる安全の仕事のひとコマひとコマをあらためて思い出した。
本当に沢山の人が協力してくれた。
もう一度一人一人に会って、ありがとうと言いたい。人に優しい人の心から安全は生まれてくる。
典子さんが颯爽と車を駆る姿が思い浮かんだ。 (終)
──伝え聞いた吉村は、20年にわたる安全の仕事のひとコマひとコマをあらためて思い出した。
本当に沢山の人が協力してくれた。
もう一度一人一人に会って、ありがとうと言いたい。人に優しい人の心から安全は生まれてくる。
典子さんが颯爽と車を駆る姿が思い浮かんだ。 (終)

 運転補助装置
運転補助装置