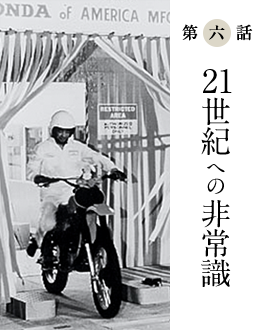ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


第八話 夢見るハイブリッド
1991年8月、ひとりの巨人がこの世を去った。
本田宗一郎。ホンダを一代で世界企業に築き上げ、米国自動車協会の殿堂入りも果たした男の訃報は、世間に大きな衝撃を与えたが、しかしその葬儀は、あまりにひっそりとしたものだった。
「私のせいで交通渋滞ができてはいけない・・・」それが、彼の遺志だった。モノ創りにかける情熱だけがクローズアップされがちなこの男は、じつはもうひとつのDNAを残していた。「企業は社会のためにある」という確固としたポリシーだ。そして、奇しくも同じ年、そ
本田宗一郎。ホンダを一代で世界企業に築き上げ、米国自動車協会の殿堂入りも果たした男の訃報は、世間に大きな衝撃を与えたが、しかしその葬儀は、あまりにひっそりとしたものだった。
「私のせいで交通渋滞ができてはいけない・・・」それが、彼の遺志だった。モノ創りにかける情熱だけがクローズアップされがちなこの男は、じつはもうひとつのDNAを残していた。「企業は社会のためにある」という確固としたポリシーだ。そして、奇しくも同じ年、そ
のDNAを開花させるための一つの出会いが、ホンダの栃木研究所であった。
「土岐ちゃん、いるかね」「土岐さんはもう帰りまし・・・えっ」深夜に残業をしていた山本善夫は、背後の声に振り向いて、びっくりした。「ふ、藤村さん」
藤村章。アコード、シビックとホンダの基幹車種のエンジンを一貫して開発し、カーオブザイヤーもなんども獲っているこの男は、山本にとって、いやホンダの若いエンジニア全員にとって、憧れの存在だった。山本はこの藤村の下で、しばらくシビックの開発に携わったあ
「土岐ちゃん、いるかね」「土岐さんはもう帰りまし・・・えっ」深夜に残業をしていた山本善夫は、背後の声に振り向いて、びっくりした。「ふ、藤村さん」
藤村章。アコード、シビックとホンダの基幹車種のエンジンを一貫して開発し、カーオブザイヤーもなんども獲っているこの男は、山本にとって、いやホンダの若いエンジニア全員にとって、憧れの存在だった。山本はこの藤村の下で、しばらくシビックの開発に携わったあ
と、ホンダの、いや地球の未来を左右する大仕事に挑むことになる。 「・・・えっ、次世代のモーター付エンジンですか??」
「・・・えっ、次世代のモーター付エンジンですか??」
1995年、栃木から和光の研究所に異動した山本は、自分
 「・・・えっ、次世代のモーター付エンジンですか??」
「・・・えっ、次世代のモーター付エンジンですか??」1995年、栃木から和光の研究所に異動した山本は、自分
に与えられたミッションを聞いて、とまどった。もともと、子どもの頃から大のF1好き。エンジンの開発をやりたくてホンダに入社し、実際にF1チームのスタッフも経験してきた山本にとって、クルマ創りは「より速く、より楽しく」がモットーだ。正直、「燃費」や「環境」というコトバを耳にしても、ピンとこなかった。
「川本社長の肝入りのプロジェクトだからな。たのむぞ」上司にポンと肩を叩かれて、ハッとする。まわりを見渡すと、藤村をはじめエース級のエンジニアたちが、
「川本社長の肝入りのプロジェクトだからな。たのむぞ」上司にポンと肩を叩かれて、ハッとする。まわりを見渡すと、藤村をはじめエース級のエンジニアたちが、
うろうろしている。V6エンジンを刷新した福尾幸一、アルミボディのエキスパート斉藤政昭・・・つねにクルマに夢を求めてきた会社の、このミッションへの意気込みを感じるに十分な布陣だった。
もともとホンダと環境は、縁が深い。70年代に米国でホンダの名を不動にしたシビックのCVCCエンジンは、当時クリアするのは不可能と言われた米国の排ガス規制法(マスキー法)を、世界のどの自動車メーカーよりも先にクリアした。90年代はEV(電気自動車)の開発にも着手。ソーラーカーレースにも参戦し、なんど
もともとホンダと環境は、縁が深い。70年代に米国でホンダの名を不動にしたシビックのCVCCエンジンは、当時クリアするのは不可能と言われた米国の排ガス規制法(マスキー法)を、世界のどの自動車メーカーよりも先にクリアした。90年代はEV(電気自動車)の開発にも着手。ソーラーカーレースにも参戦し、なんど
も優勝している。のちにハイブリッドと呼ばれるこの技術も、そんなホンダイズムの延長上にあった。
ひと口にハイブリッドといっても、異なるシステムがいくつもあった。大きくは、エンジンをメインにするか、電気をメインにするか。たんなる低燃費を志向するのであれば、電気自動車をめざすのが手っとり早い。しかし藤村と山本に流れるホンダのDNAが、それを許さなかった。「ボクらが作っているのは、単なる移動手段では決してないはずだ・・・」
来る日も来る日も、研究とテストが繰り返され、激し
ひと口にハイブリッドといっても、異なるシステムがいくつもあった。大きくは、エンジンをメインにするか、電気をメインにするか。たんなる低燃費を志向するのであれば、電気自動車をめざすのが手っとり早い。しかし藤村と山本に流れるホンダのDNAが、それを許さなかった。「ボクらが作っているのは、単なる移動手段では決してないはずだ・・・」
来る日も来る日も、研究とテストが繰り返され、激し
い議論が交わされた。本人たちはマジメに議論していても、はたから見ればただの喧嘩だ。議論はときに、居酒屋に場所を移すこともあった。「ハイブリッドといえども、走りの楽しさを忘れないのが、ホンダなんだよ。クルマは、ロマンなんだよ」藤村の熱い想いが、山本の胸にずっしりと響いた。
やがて、ホンダのハイブリッドがとるべき道が、明確な輪郭を見せ始める。そのシステムは、IMA(インテグレーテッド・モーター・アシスト)名づけられた。日本メーカー初のハイブリッドカーの実現まで、あともう
やがて、ホンダのハイブリッドがとるべき道が、明確な輪郭を見せ始める。そのシステムは、IMA(インテグレーテッド・モーター・アシスト)名づけられた。日本メーカー初のハイブリッドカーの実現まで、あともう
少しだ。搭載する車種も、その発売時期も決まっていくまさにそのとき、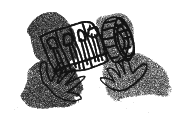 信じられない出来事が起きた。
信じられない出来事が起きた。
1997年3月の薄寒い朝に、山本は先輩からの電話で叩き起こされる。「おい、新聞を見たか」山本は、眠い目をこすりながら、朝刊を開く。「ええーっ」
<トヨタ、ハイブリッド技術を発表。世界初の量産化へ>
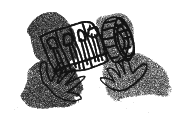 信じられない出来事が起きた。
信じられない出来事が起きた。1997年3月の薄寒い朝に、山本は先輩からの電話で叩き起こされる。「おい、新聞を見たか」山本は、眠い目をこすりながら、朝刊を開く。「ええーっ」
<トヨタ、ハイブリッド技術を発表。世界初の量産化へ>
パシッ。山本はおもわず新聞をテーブルに叩きつけた。
その日、藤村と山本のまわりは、プリウスの話題で持ちきりだった。「まさか、トヨタがこれほど進んでいるとは・・・寝耳に水だな」「あっちのシステムのほうが、賢そうに見えるけど、どうなんだろ・・・」
プリウスが採用したシステムは、エンジン以外に2つのモーターを積んで、一方を動力源とし、他方をバッテリー充電用として使うと<パワースプリット方式>だ。それに対してホンダのIMAは、コンパクトなモーター一つを、エンジンの補助動力として使
その日、藤村と山本のまわりは、プリウスの話題で持ちきりだった。「まさか、トヨタがこれほど進んでいるとは・・・寝耳に水だな」「あっちのシステムのほうが、賢そうに見えるけど、どうなんだろ・・・」
プリウスが採用したシステムは、エンジン以外に2つのモーターを積んで、一方を動力源とし、他方をバッテリー充電用として使うと<パワースプリット方式>だ。それに対してホンダのIMAは、コンパクトなモーター一つを、エンジンの補助動力として使
う、<パラレル方式>と呼ばれるものだ。
どちらの方式にも良さがあったが、世の中はトヨタの方式を、ハイブリッドの本流と見なし始めていた。ホンダ社内からも、焦りの声が聞こえてきたが、藤村に迷いはなかった。「これは、クルマとはどういうものか、という哲学の違いだ。IMAは作りがシンプルだから、軽いので、燃費も走りも両立できる。シンプルだから、既存のクルマにはめやすく、普及させやすい。いまあるクルマの楽しさを次の世代にも体験させたい、そう思ったら、IMAしかない・・・」
どちらの方式にも良さがあったが、世の中はトヨタの方式を、ハイブリッドの本流と見なし始めていた。ホンダ社内からも、焦りの声が聞こえてきたが、藤村に迷いはなかった。「これは、クルマとはどういうものか、という哲学の違いだ。IMAは作りがシンプルだから、軽いので、燃費も走りも両立できる。シンプルだから、既存のクルマにはめやすく、普及させやすい。いまあるクルマの楽しさを次の世代にも体験させたい、そう思ったら、IMAしかない・・・」
プリウスは、日本で先行発売した。ならば、ホンダは米国と欧州でトヨタの先手を打とう。一刻も早い米国発売にむけて、懸命の開発作業が続いた。
「目に見えて動くものしか、信じない」という習性がしみこんだエンジニアにとって、目に見えない電気は厄介な存在だった。「まったく、エンジンの開発で困ったことがあると、どこからともなく誰かやってきてアドバイスしてくれるんだけど、電気となるとみんな逃げていくんだからなあ・・・」そうぼやく山本自身が、なかなか電気というものに慣れなかった。実験車両に「高電圧
「目に見えて動くものしか、信じない」という習性がしみこんだエンジニアにとって、目に見えない電気は厄介な存在だった。「まったく、エンジンの開発で困ったことがあると、どこからともなく誰かやってきてアドバイスしてくれるんだけど、電気となるとみんな逃げていくんだからなあ・・・」そうぼやく山本自身が、なかなか電気というものに慣れなかった。実験車両に「高電圧
注意」という表示が貼ってあると、ついビビッてしまう。初期の水没テストは、カエルに頼ったりもした。
とまどいは、開発を手伝う電気会社にもあった。電気が本職の彼らにとって、クルマの世界は勝手が違った。なにしろ、摂氏100度以上の高温からマイナス40度以下の極低温までの環境に対応しなければならない。それも、10年以上の使用に耐えなければいけない。クルマに求められる基準は、彼らの想像を超えていた。
しかし皮肉なことに、このような電気ゆえのとまどいに直面しているうち、山本のIMAに対する自信は、
とまどいは、開発を手伝う電気会社にもあった。電気が本職の彼らにとって、クルマの世界は勝手が違った。なにしろ、摂氏100度以上の高温からマイナス40度以下の極低温までの環境に対応しなければならない。それも、10年以上の使用に耐えなければいけない。クルマに求められる基準は、彼らの想像を超えていた。
しかし皮肉なことに、このような電気ゆえのとまどいに直面しているうち、山本のIMAに対する自信は、
かえって揺るぎのないものになっていた。
「どんなに電気の安全を究めても、電気というものに不安を感じる人はいるだろう。その点、IMAは電気よりもエンジンのほうの割合が大きいから、みんな飛びつきやすいはずだ・・・」
そして、ホンダ初のハイブリッド車「インサイト」の完成車を、栃木のテストコースで試す日がきた。あれほど声を荒げて議論ばかりしていた藤村と山本は、発進と同時に声を失う。それほど、走りは爽快だった。電気でスムーズに発進する。エンジンでその走りを持続する。
「どんなに電気の安全を究めても、電気というものに不安を感じる人はいるだろう。その点、IMAは電気よりもエンジンのほうの割合が大きいから、みんな飛びつきやすいはずだ・・・」
そして、ホンダ初のハイブリッド車「インサイト」の完成車を、栃木のテストコースで試す日がきた。あれほど声を荒げて議論ばかりしていた藤村と山本は、発進と同時に声を失う。それほど、走りは爽快だった。電気でスムーズに発進する。エンジンでその走りを持続する。
アタマで描いた通りの乗り味を実際に体験するのは、エンジニア冥利に尽きるものだった。「クルマはやっぱ、ひらひらと走らないとね」エンジンの本流を歩んできた藤村は、インサイトで改めてクルマとはどうあるべきかを実感した。
1999年11月、初代インサイトが日本と米国でデビュー。その驚異の低燃費と未来的なデザインは、多くのドライバーたちの憧れをかきたてた。そして、2001年12月、初代シビックハイブリッド発売。ホンダのハイブリッド技術は、一気に普及することにな
1999年11月、初代インサイトが日本と米国でデビュー。その驚異の低燃費と未来的なデザインは、多くのドライバーたちの憧れをかきたてた。そして、2001年12月、初代シビックハイブリッド発売。ホンダのハイブリッド技術は、一気に普及することにな
る。
「いやね、うちの子供が生意気に、クルマは環境だって言ってるんですよ。僕らのころは、カッコイイとか速いとか、そんな感じだったのにねえ・・・」いつもの居酒屋で、山本はビールジョッキを片手に、藤村にぼやく。「いいじゃないの。環境だろうが、速さだろうが、みんながクルマにロマンを持ってくれるってことが、大切なんだよ・・・」藤村が答えた。
企業は社会のためにある、そう言い遺してこの世を去った創業者のDNAは、時代の要請とハイブリッド(混成)しながら、進化していくのだ。 (終)
「いやね、うちの子供が生意気に、クルマは環境だって言ってるんですよ。僕らのころは、カッコイイとか速いとか、そんな感じだったのにねえ・・・」いつもの居酒屋で、山本はビールジョッキを片手に、藤村にぼやく。「いいじゃないの。環境だろうが、速さだろうが、みんながクルマにロマンを持ってくれるってことが、大切なんだよ・・・」藤村が答えた。
企業は社会のためにある、そう言い遺してこの世を去った創業者のDNAは、時代の要請とハイブリッド(混成)しながら、進化していくのだ。 (終)

 Sport Hybrid
Sport Hybrid