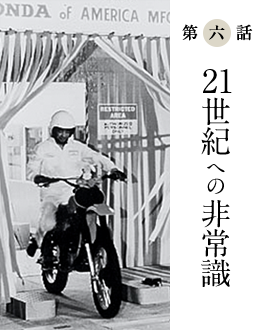ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


第七話 砂に埋まった夢
その日も、新井正吉は砂浜に立っていた。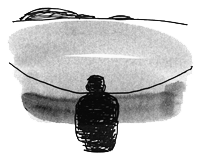
この数年間、会社よりも、ひょっとしたら家よりも、砂浜にいることが多いかもしれない。新井はすり減ったゴム長靴で砂を踏みしめると、そっとつぶやいた。
雨は乾いたみたいだな・・・よし始めよう」
そして、海岸沿いの道路に
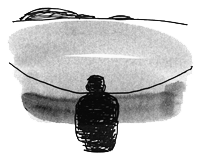
この数年間、会社よりも、ひょっとしたら家よりも、砂浜にいることが多いかもしれない。新井はすり減ったゴム長靴で砂を踏みしめると、そっとつぶやいた。
雨は乾いたみたいだな・・・よし始めよう」
そして、海岸沿いの道路に
停めた10tトレーラーに戻り、仲間たちに声をかけると、荷台からゴツい風体の4輪バギーをおろした。
ATV、All Terrain Vehicle。日本語に訳すと「全地形走行車」である。アメリカではレジャー用としてかなりポピュラーであるが、日本では一部で業務用に使われている以外は、ほとんど普及していない。このATVの新しい使い道を模索するのが、新井に課せられたミッションだった。
「えっ、日本もですか・・・」あれは、2000年の
ATV、All Terrain Vehicle。日本語に訳すと「全地形走行車」である。アメリカではレジャー用としてかなりポピュラーであるが、日本では一部で業務用に使われている以外は、ほとんど普及していない。このATVの新しい使い道を模索するのが、新井に課せられたミッションだった。
「えっ、日本もですか・・・」あれは、2000年の
末だった。当時、朝霞の研究所で北米向けATVの開発に取り組んでいた新井は、社長の篠崎に呼ばれた。
「そうだ。商品企画室が日本での販路の開拓に取り組んでいるんだけど、行き詰まってるみたいなんだ。ちょっと見てやってくれないか」
篠崎の話をきいてすぐ、新井の心にひとつの光景がよぎった。出張の合間に地方のビーチを歩いたときにまのあたりにした、ゴミの山。ATVは、アメリカでは砂丘などを駆るのに使われている。ビーチのゴミ集め用のATVを開発すれば、自治体相手のビジネスになるかも
「そうだ。商品企画室が日本での販路の開拓に取り組んでいるんだけど、行き詰まってるみたいなんだ。ちょっと見てやってくれないか」
篠崎の話をきいてすぐ、新井の心にひとつの光景がよぎった。出張の合間に地方のビーチを歩いたときにまのあたりにした、ゴミの山。ATVは、アメリカでは砂丘などを駆るのに使われている。ビーチのゴミ集め用のATVを開発すれば、自治体相手のビジネスになるかも
しれない。しかも、子供たちにきれいな砂浜を残すこともできる!
しばらくは北米チームにいながら顔を出すという、2足のわらじが3年ほど続いた。が、ある日、新井は思いつめた表情の日本チームのメンバーに呼び出される。
「先日の役員会議で、プロジェクトの見直しを命じられました・・・でもボクらはどうしても続けたいんです。新井さんがリーダーを引き受けてくれたら、役員は続行を許してくれるはずです。お願いします!」
定年まであと4年ちょっと。普通の会社人生なら、こ
しばらくは北米チームにいながら顔を出すという、2足のわらじが3年ほど続いた。が、ある日、新井は思いつめた表情の日本チームのメンバーに呼び出される。
「先日の役員会議で、プロジェクトの見直しを命じられました・・・でもボクらはどうしても続けたいんです。新井さんがリーダーを引き受けてくれたら、役員は続行を許してくれるはずです。お願いします!」
定年まであと4年ちょっと。普通の会社人生なら、こ
れまでやってきたことの総仕上げに入ろうかというステージである。そんなときに、海のものとも山のものともしれぬ、新しいプロジェクト。新井の中を流れるホンダDNAが、騒いだ。「よし、やろう」
かつては大所帯だったプロジェクトチームは5名に縮小されたが、そのぶん情熱の密度は濃くなった。議論をするうちに、ひとつの像が浮かぶ。4輪車の後ろに熊手のような装置をつけてゴミをかき集めるという代物。試作品をつくる通称“板金屋”に一日になんども通ってはパイプを切ったりつないだりした。
かつては大所帯だったプロジェクトチームは5名に縮小されたが、そのぶん情熱の密度は濃くなった。議論をするうちに、ひとつの像が浮かぶ。4輪車の後ろに熊手のような装置をつけてゴミをかき集めるという代物。試作品をつくる通称“板金屋”に一日になんども通ってはパイプを切ったりつないだりした。
ようやく熊手のような装置ができ上がると、 実際に海岸に行って試してみる。ペットボトルからちり紙まで、大きさも形状も様々なものを砂浜に埋めては、その上を走らせてみた。やってみると、熊手だけでは、大きなゴミをすくったあとに出てくる小さなゴミを、集めることができないことが分かる。いろいろ考えた末に、熊手の後ろに網をつけることにした。熊手ですくった砂が網に飛ばさ
実際に海岸に行って試してみる。ペットボトルからちり紙まで、大きさも形状も様々なものを砂浜に埋めては、その上を走らせてみた。やってみると、熊手だけでは、大きなゴミをすくったあとに出てくる小さなゴミを、集めることができないことが分かる。いろいろ考えた末に、熊手の後ろに網をつけることにした。熊手ですくった砂が網に飛ばさ
 実際に海岸に行って試してみる。ペットボトルからちり紙まで、大きさも形状も様々なものを砂浜に埋めては、その上を走らせてみた。やってみると、熊手だけでは、大きなゴミをすくったあとに出てくる小さなゴミを、集めることができないことが分かる。いろいろ考えた末に、熊手の後ろに網をつけることにした。熊手ですくった砂が網に飛ばさ
実際に海岸に行って試してみる。ペットボトルからちり紙まで、大きさも形状も様々なものを砂浜に埋めては、その上を走らせてみた。やってみると、熊手だけでは、大きなゴミをすくったあとに出てくる小さなゴミを、集めることができないことが分かる。いろいろ考えた末に、熊手の後ろに網をつけることにした。熊手ですくった砂が網に飛ばされ、大きなゴミは熊手に、小さなゴミは網に引っ掛かる、という仕組みだ。
ちょっと雨がふると、ボタついた砂が網目に引っ掛かり仕事にならない。そんなときは、乾くまで気長に待つしかなかった。
「うまく網に掛からないのは、網の問題なのか、熊手の問題なのか・・・」夜になると、浜で魚を焼いたり酒を飲んだりしながら、熱い議論を交わす男たちの姿があった。
一方その頃、会社はプロジェクトの新しい道を模索し
ちょっと雨がふると、ボタついた砂が網目に引っ掛かり仕事にならない。そんなときは、乾くまで気長に待つしかなかった。
「うまく網に掛からないのは、網の問題なのか、熊手の問題なのか・・・」夜になると、浜で魚を焼いたり酒を飲んだりしながら、熱い議論を交わす男たちの姿があった。
一方その頃、会社はプロジェクトの新しい道を模索し
ていた。ATVを使ったビーチクリーンを、ビジネスではなく、ホンダの新しい社会貢献にしようという試み。この新しい使命によって、新井たちの奮闘は、予想もしない広がりを見せることになる。
2005年12月。市村裕子は、千葉の成東海岸に立っていた。
沖合いから吹いてくる冷たい風が、ほおに当たっても、緊張で顔の火照りを感じている市村には、むしろ心地よかった。
2005年12月。市村裕子は、千葉の成東海岸に立っていた。
沖合いから吹いてくる冷たい風が、ほおに当たっても、緊張で顔の火照りを感じている市村には、むしろ心地よかった。
社会活動推進室、通称「社活」は1998年に創設された。CSR、企業の社会的責任ということが声高に叫ばれるずっと前のことであった。市村はこの組織に5ヶ月前に配属されたばかりだった。砂漠に木を植えたり、子供たちの創造力を育んだりと、これまで社活が取り組んできたことは、どれもホンダらしいものだった。けれども、そういった活動を知れば知るほど、市村の心にある思いがよぎった。
「ホンダイズムといえば、モノづくりへの飽くなき情熱である。だったら、ホンダが作るモノをとおして、社会
「ホンダイズムといえば、モノづくりへの飽くなき情熱である。だったら、ホンダが作るモノをとおして、社会
に貢献する道はないだろうか・・・」
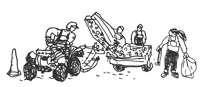 そして、市村はATVを使用したビーチクリーナーを開発している新井正吉のことを知る。さっそく会いにいくと、いかにも職人然とした佇まいの新井は、ぶっきらぼうに言った。「まあ、とりあえず見に来てくださいよ・・・」
そして、市村はATVを使用したビーチクリーナーを開発している新井正吉のことを知る。さっそく会いにいくと、いかにも職人然とした佇まいの新井は、ぶっきらぼうに言った。「まあ、とりあえず見に来てくださいよ・・・」
10tトラックの中から出てきたバギーは、想像したよりもシンプルな造りだ。が、砂浜の上でいざ走り出すと、後ろにつ
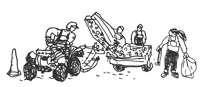 そして、市村はATVを使用したビーチクリーナーを開発している新井正吉のことを知る。さっそく会いにいくと、いかにも職人然とした佇まいの新井は、ぶっきらぼうに言った。「まあ、とりあえず見に来てくださいよ・・・」
そして、市村はATVを使用したビーチクリーナーを開発している新井正吉のことを知る。さっそく会いにいくと、いかにも職人然とした佇まいの新井は、ぶっきらぼうに言った。「まあ、とりあえず見に来てくださいよ・・・」10tトラックの中から出てきたバギーは、想像したよりもシンプルな造りだ。が、砂浜の上でいざ走り出すと、後ろにつ
けた熊手で軽快に砂を舞い上げながら、器用にゴミを網に落としていく。市村があっけにとられて見ていると、新井が少年のような笑みを浮かべて話しかけてきた。「わざわざ来て、乗らないっていうのはないでしょう・・・」実際にバギーに乗ってみると、思ったよりスピードを感じる。起伏に体を揺すられながら、砂を舞い上げるシャーという音が、耳に心地よく響く。最初に砂浜に立ったときの漠然とした不安は、成功への確信へと変わった。「これは、いける! 」
翌2006年3月、東京・青山のホンダ本社で開かれた
翌2006年3月、東京・青山のホンダ本社で開かれた
経営会議で、市村は居並ぶ役員たちを前に、足がすくみそうになった。配属されて8ヶ月の市村に、役員プレゼンという大役をまかせる。それが、ホンダだった。
「いろいろお話しする前に、まず見てください・・・」バギーの実験風景、新井たちの奮闘ぶりをビデオで流す。そして、本題を切り出した。「みなさま、ホンダらしい社会貢献活動って、なんでしょうか・・・」プレゼンは成功。まずはやってみよう、と。役員にもまた、ホンダの血が流れているのだ。
最初の活動場所は、神奈川県の片瀬海岸。事故でもあ
「いろいろお話しする前に、まず見てください・・・」バギーの実験風景、新井たちの奮闘ぶりをビデオで流す。そして、本題を切り出した。「みなさま、ホンダらしい社会貢献活動って、なんでしょうか・・・」プレゼンは成功。まずはやってみよう、と。役員にもまた、ホンダの血が流れているのだ。
最初の活動場所は、神奈川県の片瀬海岸。事故でもあ
ろうものなら、新井たちがこの5年あまり注いできた情熱が、無駄になってしまう。市村は、藤沢市役所や地元の観光協会と、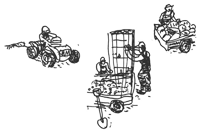 なんども打合せを行った。それだけでは収まらず、実際に現場に足をはこんで、頭の中でなんどもシミュレーションをした。「ここにトラックを停めて、バギーを出す。砂浜までのアプローチはこのルートだとして・・・あ、ボランティアの人た
なんども打合せを行った。それだけでは収まらず、実際に現場に足をはこんで、頭の中でなんどもシミュレーションをした。「ここにトラックを停めて、バギーを出す。砂浜までのアプローチはこのルートだとして・・・あ、ボランティアの人た
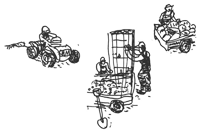 なんども打合せを行った。それだけでは収まらず、実際に現場に足をはこんで、頭の中でなんどもシミュレーションをした。「ここにトラックを停めて、バギーを出す。砂浜までのアプローチはこのルートだとして・・・あ、ボランティアの人た
なんども打合せを行った。それだけでは収まらず、実際に現場に足をはこんで、頭の中でなんどもシミュレーションをした。「ここにトラックを停めて、バギーを出す。砂浜までのアプローチはこのルートだとして・・・あ、ボランティアの人たちが大勢くるから、トイレのことも考えないと・・・」のめりこむと止まらない気質は、市村も新井も同じだった。
そうして迎えた当日。曇り空の下だったが、市村たちの熱気が伝わったのか、もう終了というときになって雨がパラついた。集めたゴミは40Lゴミ袋で21袋分にもなった。「ホンダさん、またお願いします」「いつもは子供を裸足で歩かせないけど、明日はそうしてみます」そんな声をかけられるたび、市村の中にある疲れも、ビーチクリーンのように取り除かれていった。
そうして迎えた当日。曇り空の下だったが、市村たちの熱気が伝わったのか、もう終了というときになって雨がパラついた。集めたゴミは40Lゴミ袋で21袋分にもなった。「ホンダさん、またお願いします」「いつもは子供を裸足で歩かせないけど、明日はそうしてみます」そんな声をかけられるたび、市村の中にある疲れも、ビーチクリーンのように取り除かれていった。
2008年2月。市村のところに新井が定年退職の挨拶にきた。「もちろん、これからも協力してくれますよね?」
ビーチクリーン活動は、全国に広がっていた。海外拠点から引き合いも来るようになった。地元の人たち、大人も子供も巻き込んで、大きな活動にしていきたい。可能性は、星の数ほど埋まっているのだ。市村の問いかけに、新井は笑ってこう答えた。
「もちろんです。生涯、ホンダの人間ですから」 (終)
ビーチクリーン活動は、全国に広がっていた。海外拠点から引き合いも来るようになった。地元の人たち、大人も子供も巻き込んで、大きな活動にしていきたい。可能性は、星の数ほど埋まっているのだ。市村の問いかけに、新井は笑ってこう答えた。
「もちろんです。生涯、ホンダの人間ですから」 (終)

 ビーチクリーン活動
ビーチクリーン活動