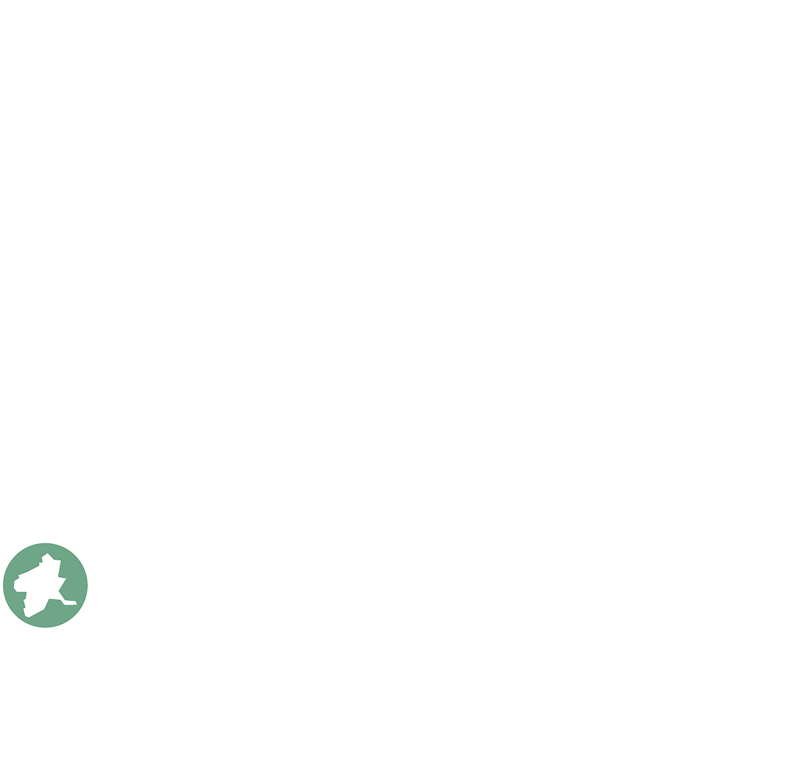日本に全部で8つある「海なし県」出身で、子供の頃から川釣りに親しんで来た加藤るみさんが、そのすべての県に出かけ、その場所ならではの魚たちを追い求める旅に出発! 時にはその道のエキスパートに助言も仰ぎながら、ジャンルもフィールドも全く違う数々の釣りに、体当たりでチャレンジしていきます。一人のアングラーとしての成長もめざすこの旅。全8県の水辺を釣り尽くした時、彼女が見つける〝新しい景色〟とは?
ウキ釣りの最高峰! 野ベラの釣りに山上湖で挑む
〜山梨のヘラブナ釣り編~

第4回は、山梨県でヘラブナをねらいます。ヘラブナは大正期から釣り用の魚として関西で放流されるようになり、やがて東日本にも人気と釣り場が広がりました。今回はそれらの中でも「特に一尾の価値が高い」とされる山上湖での野釣りに挑戦! 周囲に広がる雄大な景色に癒されつつ、エサ付けからウキの動きの観察まで、手も頭も常にフル回転の釣りにチャレンジします!
元祖日本のゲームフィッシュと真剣勝負!
こんにちは、加藤るみです。「海なし県」全8県をめぐって川釣りを制覇するこの旅も、いよいよ第4回。山上湖でヘラブナの野釣りに挑戦です。
ヘラブナはひし形の立派な体躯を持ち、引きも力強いことから「釣りを楽しむための魚」として各地に放流されてきました。一方で、フナの仲間の中でも、音や気配に敏感で警戒心が高く、さらに植物プランクトンをエサにするという独特の生態から、釣りは一筋縄ではいきません。魚を寄せるための練りエサはねらった水深(タナ)で上手く溶けるように微妙な加減がキモ。さらに長いサオでの振り込み、ウキの動きから水中のようすを理解する判断力など、ビギナーには難しさの連続! そんな高いハードルを乗り越えつつ、山上湖という最高のロケーションで、立派な「野ベラ」を釣り上げます!
【今回のチャレンジ】
山上湖の野性味あふれるヘラブナを、
ボートからの繊細なウキ釣りでキャッチ!


日本で釣りの対象魚として長い歴史があるヘラブナ。調べてみると、山梨県の富士五湖は東日本の中でもいち早くヘラブナ釣りの人気フィールドとなった歴史があり、さらに野釣りが楽しめる貴重な場所だそう。いわゆる管理池(ヘラブナの専用釣り堀)を飛び越えて、いきなり野釣りは無謀かな?とも思いましたが、頼れる先生にレッスンしていただけることになり、思い切ってチャレンジすることにしました。





最初の練りエサ作りから
システマチックな釣りに驚く




ヘラブナ釣りを開始して、何より驚いたのがその緻密さ。適当は絶対にNG! たとえば練りエサは必ず計量カップでレシピ通りに作ります。さらに練りエサをハリに付ける際の形や圧力でも水中でのばらけ具合が変わり、それらを常にコントロールしながら釣りをします。先生いわく「ヘラブナ釣りは一に慣れ、二に慣れ」とのことですが、失敗を繰り返していく中で、その言葉の意味がじわじわと理解できてきました。

そしてウキの動き。魚がエサを食べたらスパッとウキが沈む、という基本は他の釣りと同じなのですが、ヘラブナ釣りではそれ以外にもたくさんの情報をウキから得ます。

ヘラブナ釣りの仕掛けは、上から順に、ウキ、オモリ、ハリス、ハリ(そこにエサが付く)が並んでいるので、仕掛けを振り込んで着水したウキ、始めはしばらく水面に倒れていて、その後、オモリまでがなじむと立ち上がります。次に練りエサの付いたハリまでがなじむと少しずつ沈んで行くのですが、ほどなくエサが徐々に水中で溶けていくので、今度は逆に少しずつ上がってきます。この一連の動きが「なじみ」ですが、慣れない私は仕掛けがしっかりなじむ前に、だいたい途中のどこかで練りエサがハリから取れてしまう……。すると釣りにならず、「こんなに難しいの!」と心の中で静かに叫びまくりでした。



- ※走行中は安全のため、シートベルトをお締めください。
- ※安全のため、走行の際は後方視界をしっかり確保してください。
- ※このコンテンツは、2025年9月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。