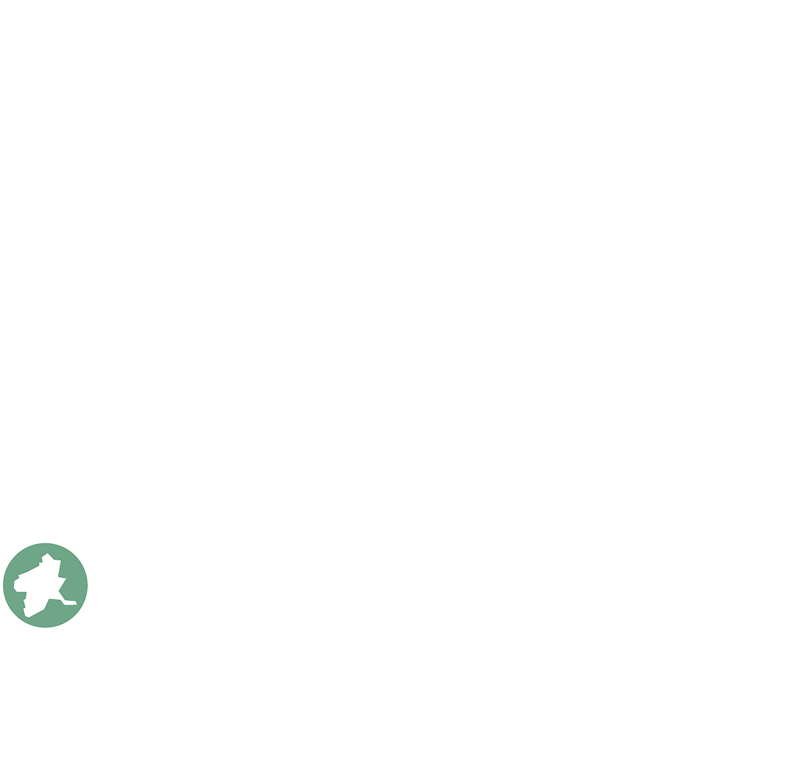日本に全部で8つある「海なし県」出身で、子供の頃から川釣りに親しんで来た加藤るみさんが、そのすべての県に出かけ、その場所ならではの魚たちを追い求める旅に出発! 時にはその道のエキスパートに助言も仰ぎながら、ジャンルもフィールドも全く違う数々の釣りに、体当たりでチャレンジしていきます。一人のアングラーとしての成長もめざすこの旅。全8県の水辺を釣り尽くした時、彼女が見つける〝新しい景色〟とは?
身長の6倍!? 驚きの長ザオでねらう清流の女王!
〜岐阜のアユ釣り編~

第3回は、岐阜県の山あいを流れる清流でアユをねらいます。アユは日本の清流に生息する魚。また、川で生まれて一度海に下り、再び川に戻って来てからは、川の石に生える藻類を主食にするという、とてもユニークな生態を持っています。そんなアユを釣るために生まれた技が「友釣り」。数ある川釣りの中でも難易度はおそらく最高レベル。唯一無二といわれる釣りに挑みます!
日本の夏の川の女王!
こんにちは、加藤るみです。日本の“海なし県”全8県をめぐって、各地の川釣りにチャレンジするこの旅。今回の目的地は、私の故郷・岐阜県です。狙うのは、まさに「日本の夏の川といえばこの魚」――アユ! 夏の岐阜はアユ一色。川ではアユ料理を食べさせるお店が賑わい、大勢のアユの友釣りファンがサオをだすようになります。
友釣りは、生きたオトリを操り、川に泳ぐアユをハリに掛けてキャッチするまでのすべてのプロセスが川釣りの中でも難易度マックスですが、私もイチから挑戦するのは初めて。ならば今しかない! シーズン真っただ中の故郷・岐阜の川で、自分の手で“清流の女王”を釣り上げてみせます!
【今回のチャレンジ】
泳がせて、掛けて、キャッチ!
友釣りの技を覚えて美味しいアユを食べる










野アユは元気なオトリには攻撃してくるのですが、泳ぎが不自然だと見向きもしないのだとか。だから「まずはオトリを元気に泳がせることが大前提。それができ、掛かった野アユをキャッチして、次はその掛かった野アユを元気なオトリとして使えるようになったら、驚くほど釣れる。それがアユの友釣りですよ」と先生。うーん、道のりは長い!






- ※走行中は安全のため、シートベルトをお締めください。
- ※安全のため、走行の際は後方視界をしっかり確保してください。
- ※このコンテンツは、2025年8月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。