
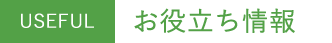 お役立ち情報 May.26.2023
お役立ち情報 May.26.2023 知っておこう!犬のストレス
原因とストレスサイン、対策のコツ
犬が見せるストレスサインには、生理的反応と行動的反応があり、それぞれに急性的反応と慢性的反応があります。これらの反応が過剰になると病気や異常行動を引き起こします。そのため、ストレスを受けにくくしたり、和らげたりするストレス対策のコツが大切です。犬がどのようなことでストレスを感じるのか、どのようなストレスサインを見せるのか、ストレス対策のコツを詳しくご紹介します。
ストレスとは?

ストレスとは、動物の心身に変化をもたらす刺激(ストレッサー)と、その刺激によって起こる反応(ストレス反応)の総称です。つまり、ストレス反応は犬が環境の変化に適応するために備わっているとても重要な反応です。一般的に「ストレス」というと「悪いもの」と思われますが、本当は悪いものばかりではありません。
例えば、愛犬を今まで連れて行ったことのない公園に連れて行くこともストレスの一種です。多くの犬は、新しい公園の環境から「良い刺激」を受けるはずです。
ストレスについて考える時に大切なことは、心身に悪影響を及ぼすようなストレッサーを避け、ストレス反応をできるだけ軽減・緩和してあげることです。
ストレスの原因

犬にとって心身への悪影響につながるストレッサーになる可能性があるものは、たくさんあります。代表的なものは次の通りです。
新奇刺激(新しく経験する物事)
- 経験したことがない物事は、多かれ少なかれ犬に緊張・不安・恐怖を引き起こします。愛犬に憶病・神経質という特徴がある場合は、特に気をつけてあげたいです。普通は経験を繰り返すことで慣れますが、犬のペースに合わせて経験させましょう。
行動の制限
- 動きを制限されることは、犬にとって心身の苦痛になる場合があります。狭いクレートやサークルに長時間入れる、リードで長時間つなぐ、ケアのための保定などです。意外かもしれませんが長時間抱き続けることもストレスになる場合があります。
環境刺激の不足や不快な生活環境
- おもちゃが入っていないサークルなどは、犬がひとり遊びや探索・探査をする機会に乏しい退屈な環境です。また、不快な物音がする、人や動物の気配がして落ち着かない、不衛生(悪臭がするなど)な状態などは犬にとって不快で安心できない環境です。このような環境での生活は犬の心身に悪影響を与えます。
飼い主さんとのコミュニケーションの不足や不具合
- 長時間の留守番、飼い主さんと遊ぶ機会の不足、飼い主さんの不機嫌な態度・攻撃的な態度、犬に理解できない飼い主さんの関わり方(下手なコミュニケーション)などは、犬にとって心理的な苦痛になる場合があります。
身体の痛み
- 体罰、事故、傷病などによる身体の痛みは、犬の心身に明確な苦痛を与えます。体罰など痛みを伴う経験は、たった一度であっても強い恐怖を学習することがあるため要注意です。
学習された嫌悪刺激
- 犬が不快な経験と結び付けて学習した刺激は、すべて犬にとって心理的な苦痛になります。例えば、爪を切って出血した痛みと結び付いた爪切り道具、叩かれる痛みと結び付いた飼い主さんの手、いつも無理やり詰め込まれて動物病院に連れていかれることと結び付いたクレートなどです。不快な経験と結び付けば、食べ物ですら嫌な刺激になる場合があります。
その他、暑い・寒いなどの気候、破裂・爆発音(雷や花火の音など)や金属音、飢えや渇きなども心身に悪影響を与える場合があります。
知っておこう!犬のストレスサイン

ストレス反応には、生理的反応と行動的反応があり、それぞれに急性的反応と慢性的反応があります。
また、犬がストレスの原因に対して「予測できない」、「対処できない」、「脅威に感じる」という場合に、ストレス反応は強くなります。つまり、ストレスが軽度か重度かということは、犬自身の感じ方によって左右されます。
生理的ストレス反応

ストレスを受けると、それに応答して犬の身体の中ではホルモンや神経伝達物質の分泌量が変化します。難しい話はさておき、観察できる生理的ストレス反応には次のようなものがあります。
急性的反応
- ●瞳孔の拡張
- ●肉球からの発汗
- ●ハァハァとあえぐ呼吸(パンティング):呼吸数の増加
心拍数の増加、血圧の上昇とも関連 - ●立毛
- など
慢性的反応
- ●元気の消失や食欲の低下、下痢、皮膚・被毛のハリ・ツヤの悪化など様々な体調不良
胃腸の潰瘍や副腎皮質の肥大などの体内での病変が原因(酷いと死に至る) - ●感染症の発症
リンパ腺や胸腺の委縮による免疫機能の低下が原因 - など
行動的ストレス反応

犬は行動することでストレスに対処しようとします。主な行動的ストレス反応には次のようなものがあります。なお、犬が不快である時の基本的なボディランゲージの特徴は、耳を後方に倒す、伏し目がちになる(または目を大きく見開く)、相手と視線を外す、眉間が寄る、頭や尾が下がる、姿勢が低くなる、などです。
正常な初期反応
- ●威嚇・攻撃
- 犬は痛みや恐怖をもたらす対象に攻撃的に立ち向かうことで対処しようとすることがあります。吠える、唸る、咬みつく、などの行動です。
- ●逃避・回避
- 犬は不快な物事を避けたり、逃げたりすることで対処しようとすることがあります。走り去る、間合いを取る(近寄らない)、身体をくねらせるなどして暴れる、肢を引っ込める、身体を反らす・背ける、などの行動です。
- ●硬直化
- 犬は部屋の隅などでうずくまり、動かずに不快な物事をやり過ごそうとすることがあります。
- など
急性的反応
ストレスに対して比較的急性的に起こる行動として葛藤行動があります。葛藤行動には主に次のような行動があります。いずれもストレスに関係なくても起こる行動です。基本的には普段よりも頻繁に、または長い時間、その行動をしているとストレス反応の可能性があります。
- ●身体を掻く・噛む・舐める
- 掻く場合は耳や首の辺り、噛む・舐める場合は肉球を含む肢先や尾などが対象になることが多いです。
- ●身震い
- 身体についた水を飛ばすときのように、身体をブルブルと振ります。頭だけ振ることもあります。
- ●あくび
- ●鼻先を舐める
- ●地面や床などを嗅ぐ・舐める
- ●柵やリードなどを噛む
- など
慢性的反応
ストレスに対して慢性的に起こる行動として異常行動があります。異常行動には主に次のような行動があります。いずれも正常な犬には起こりません。
- ●常同行動
- 同じ行動を規則的に繰り返している場合には、常同行動の可能性があります。
- ・同じ場所を行ったり来たりする
- ・自分の尾を追いかけ続ける
- ・毛や皮膚を噛んだり、舐め続けたりする
- ・一点をじっと見つめて吠え続ける
- など
- 毛や皮膚を噛んだり、舐めたりし続けることで、脱毛・皮膚炎・出血・肉の噛み千切りなどが起こる場合があるので、とくに注意が必要です。
- ●多食多飲
- ストレスを原因として過剰に食べたり、飲んだりすることがあります。
- ●異嗜(いし)や食糞
- ストレスを原因として、食べ物ではないものを積極的に食べてしまうことがあります。消化できない異物を飲み込んだ場合には、死に至ることもあります。
- ●恐怖症や不安症
- 学習によって小さな刺激でも強い恐怖や不安を引き起こすことがあります。パニック状態になり、失禁・脱糞・奇声などを伴うこともあります。
- など
これらのストレス反応の多くは、ストレスを受けた場面だけの特別な反応ではありません。愛犬の状況・状態を見ながら、本当にストレスから起こっている反応かどうか判断しましょう。
ストレス対策のコツ

ストレス反応は本来自分を守るための反応ですが、過剰になると病気や異常行動を引き起こします。そうならないように、愛犬のストレスをなくしてあげたいと思うかもしれませんが、現実的にはストレスのまったくない生活を提供することは不可能です。そこで大切になるストレス対策のコツとして次のようなものがあります。
心身の悪影響になるようなストレスはできるだけ減らす
ストレス対策のコツ
- ●衛生的で快適な生活空間を整えましょう。何より大切なことは愛犬が安眠できる環境づくりです。準備した環境が犬にとってお気に入りの場所になるように教えてあげることも重要です。
- ●愛犬とは穏やかに接しましょう。しつけだからといって、叩いたり、怒鳴ったり、などして犬に恐怖や不安を与えることは望ましくありません。
- ●十分なコミュニケーションと運動の機会を設けましょう。ただし、愛犬の状態に合わせましょう。例えば、べったりされることを好まない犬を長時間なでまわしてはいけません。また、外の環境を怖がる犬を無理やり散歩に連れ出すこともいけません。
- ●ブラッシングやシャンプーなど何事も無理やり行うことは避けましょう。少しずつでも慣れさせることが大切です。
- ●新しい人や犬と出会う時は、愛犬のペースでコミュニケーションできるようにしましょう。新しい場所に行く時も、愛犬のペースで行動できるようにしましょう。
- ●既に愛犬が怖がったり、不安がったりするもので、生活上避けられるものは、避けてあげることもよいでしょう(とくに高齢犬の場合)。
- など
ストレスを和らげる、ストレスからの回復を早める
ストレスを和らげるコツ
- ●愛犬との信頼関係ができていれば、飼い主さんが一緒に居ることでストレスを和らげることができます。
- ●嫌なことをする前に美味しいものを食べさせて愛犬の気分を上げることでストレスを和らげることができます。あるいは、嫌なことが終わった後に美味しいものを食べさせることでストレスからの回復を早めることができます。犬が喜ぶことであれば、遊びやノーズワークなどでもOKです。
- ●ストレスを受けたあとに、安心できる環境で十分に休息をさせることで、ストレスからの回復を早めることができます。
- ●ストレスを受ける前に不安や恐怖を和らげる作用のあるサプリメントを使うこともできます。
- など
愛犬のストレス耐性そのものを高める
ストレス耐性の高め方
- ●まだ子犬であれば十分に社会化をすることでストレス耐性を高めることができます。
- ●成犬でも苦手な物事を克服するトレーニングをすることで、少しずつでもストレス耐性を高めることができます。
- ●犬の生活環境や生活習慣を整えて心身の安定性を高めると、ストレス耐性を高めることができます。
- ●ノーズワークで犬をポジティブ思考にできる可能性があります。
- など
最も根本的で重要なことは、
「愛犬のことをよく観察して、
よく知ること」です
愛犬をよく観察して、よく知ることができれば、愛犬からのサインを見逃さず、悪いストレスから守ってあげることができるでしょう。

愛玩動物看護師/修士 [ 動物応用科学 ]( ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 伴侶動物行動管理学研究室 講師 )
麻布大学大学院 獣医学研究科 動物応用科学専攻 博士前期課程修了
人と動物の生活が豊かになるように、主に犬猫の動物行動学について教育研究に取り組んでいる。その他、動物病院にて問題行動の修正やしつけ相談、ペット用品開発の監修やアドバイスなどに携わる。共著に『知りたい!考えてみたい!どうぶつとの暮らし』(駿河台出版社)。
※このコンテンツは、2023年5月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。