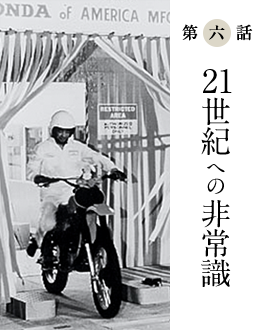ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


第五話 未来へのコース
バシャ!という水音とともに、十二尺ほどもある竿がぎゅーんとしなる。
「きたぞ―――」
イワナ、北海道のこの地方では、オショロコマと呼ばれる。
堀越寛は、昨夜見つめつづけた等高線図を頭の中に再現しながら、釣り上げた銀色の生き物を川にもどす。
そう、今回の沢登りは、オショロコマだけが目的ではないのだ。
いや、前回もそうだった。前々回も・・これからも、
「きたぞ―――」
イワナ、北海道のこの地方では、オショロコマと呼ばれる。
堀越寛は、昨夜見つめつづけた等高線図を頭の中に再現しながら、釣り上げた銀色の生き物を川にもどす。
そう、今回の沢登りは、オショロコマだけが目的ではないのだ。
いや、前回もそうだった。前々回も・・これからも、
あと何度、こうした渓谷や原野への単独行をくりかえすことになるのだろうか。
「空港からのアクセスは可も不可もない。よしとするか。
気候的には、このへんは申し分ないが・・」
堀越は、森の向こうに彼の夢が見えかくれするのを想い描いた。
「全体に勾配が少々きつ過ぎるかもしれない」
―――水中からの一瞬の合図を見逃さなかった野性の眼が、あたりを再び見回していた。
「空港からのアクセスは可も不可もない。よしとするか。
気候的には、このへんは申し分ないが・・」
堀越は、森の向こうに彼の夢が見えかくれするのを想い描いた。
「全体に勾配が少々きつ過ぎるかもしれない」
―――水中からの一瞬の合図を見逃さなかった野性の眼が、あたりを再び見回していた。
がっしりとした体躯、浅黒い肌、豪快な笑い声。
ヒグマを思わせる外見の堀越寛が、(株)本田技術研究所の緻密な分析力を要求されるテスト・エンジニアだとは中々見えない。
しかし、入社二年目にして突然車体テストに配属された彼は、以来、持ち前の勘の鋭さとバイタリティで文字通り体から学んできた。
頭脳と肉体でクルマの問題点を発見する、根っからのテスト屋だ。
そんな彼には、完全過ぎるクルマは没個性でつまらない
ヒグマを思わせる外見の堀越寛が、(株)本田技術研究所の緻密な分析力を要求されるテスト・エンジニアだとは中々見えない。
しかし、入社二年目にして突然車体テストに配属された彼は、以来、持ち前の勘の鋭さとバイタリティで文字通り体から学んできた。
頭脳と肉体でクルマの問題点を発見する、根っからのテスト屋だ。
そんな彼には、完全過ぎるクルマは没個性でつまらない
という評論など、吠えたくなるものだった。
 「なるほど誰でも乗れてただ優しいなら、単に完全なだけだ。個性は感じない。
「なるほど誰でも乗れてただ優しいなら、単に完全なだけだ。個性は感じない。
が、逆に一部の人だけが乗りこなせるのが真の個性なのか、それならクルマの楽しさは限られた人のもので終り
 「なるほど誰でも乗れてただ優しいなら、単に完全なだけだ。個性は感じない。
「なるほど誰でも乗れてただ優しいなら、単に完全なだけだ。個性は感じない。が、逆に一部の人だけが乗りこなせるのが真の個性なのか、それならクルマの楽しさは限られた人のもので終り
だ。
誰でも走れる基本性能を徹底して鍛え、安全で、しかも技量に応じ、要求に答え、潜在力を出すクルマ。
要は基本があり、思いきり個性を出せるクルマを俺は作りたいのだ!」
それはホンダの十五年で育っていた彼の哲学だった。が、と彼は思う。
そんなクルマは道を知らずしてはできまい。理想のコースが必要だ。
テストのため北海道を訪れるたびに、暇をみつけては
誰でも走れる基本性能を徹底して鍛え、安全で、しかも技量に応じ、要求に答え、潜在力を出すクルマ。
要は基本があり、思いきり個性を出せるクルマを俺は作りたいのだ!」
それはホンダの十五年で育っていた彼の哲学だった。が、と彼は思う。
そんなクルマは道を知らずしてはできまい。理想のコースが必要だ。
テストのため北海道を訪れるたびに、暇をみつけては
山野を歩き回った。
もちろん、新コース建設はまだ会社の方針になっていない。
しかも、堀越にはエンジニアとしてやるべき業務が、山ほどあった。
プライベートな時間、ときには趣味の釣りを兼ねての用地さがしであった。
それでも堀越は頓着しない。好きでやっているから、が口癖だった。
しかし、どこまでも自分流を貫くこの男は、運命までも
もちろん、新コース建設はまだ会社の方針になっていない。
しかも、堀越にはエンジニアとしてやるべき業務が、山ほどあった。
プライベートな時間、ときには趣味の釣りを兼ねての用地さがしであった。
それでも堀越は頓着しない。好きでやっているから、が口癖だった。
しかし、どこまでも自分流を貫くこの男は、運命までも
自分の流れにひきずりこんでしまった。
一九八六年に入って、他社が北海道に巨大なテストコースを建設した。
しかも、ホンダの寒冷地コースの、目と鼻の先にである。
「とうとう完成したか」
「相当すごいらしい」―――
そんな会話が、同僚たちの間で交わされるようになった。
おりしも、栃木の研究所から川本信彦副社長(現本田技
一九八六年に入って、他社が北海道に巨大なテストコースを建設した。
しかも、ホンダの寒冷地コースの、目と鼻の先にである。
「とうとう完成したか」
「相当すごいらしい」―――
そんな会話が、同僚たちの間で交わされるようになった。
おりしも、栃木の研究所から川本信彦副社長(現本田技
研社長)がテスト立ち会いにやって来る。堀越はこの機を逃すことなく直訴した。
「世界の道で、誰もがもっと楽しく運転できるクルマを作るには、このコースじゃ狭すぎます。栃木のコースも少し平坦です。
新しい時代のコースをぜひ!」堀越の内なる炎をさがすかのように、彼の目をのぞきこんでいた川本は、やがてぽつりと言った。
「よし、場所、真剣に探してみようか。いい所があったら作るぞ。」
「世界の道で、誰もがもっと楽しく運転できるクルマを作るには、このコースじゃ狭すぎます。栃木のコースも少し平坦です。
新しい時代のコースをぜひ!」堀越の内なる炎をさがすかのように、彼の目をのぞきこんでいた川本は、やがてぽつりと言った。
「よし、場所、真剣に探してみようか。いい所があったら作るぞ。」
――― いまだに目に見えない大きな獲物が針に掛ったのを堀越は感じた。
この日を境に堀越の片手間仕事は、全社の期待を背負った大テーマとなってゆくのだった。
「今週は帯広あたりへ―― 」
堀越が差し出す出張伝票に、直属の上司は黙ってサインする。
プロジェクトの大ボス、鈴木久雄取締役(現ホンダ・R&D・ノース・アメリカ副社長)の配慮で自由に動き
この日を境に堀越の片手間仕事は、全社の期待を背負った大テーマとなってゆくのだった。
「今週は帯広あたりへ―― 」
堀越が差し出す出張伝票に、直属の上司は黙ってサインする。
プロジェクトの大ボス、鈴木久雄取締役(現ホンダ・R&D・ノース・アメリカ副社長)の配慮で自由に動き
回れた。
栃木の研究所から北海道へ年二十回のペースで通った。
現場には独自に作成したチェックリストを持参する。気温、積雪量、地形等々項目の抽出にあたっては、各方面の先輩から助言を仰いだ。
「霧の量を推定するには――― 」
「近くの大河や湖からの距離を調べるんだ。それからな、堀越、本格的なワインディングを作るんなら、適度な高低差があるかどうかも重要だぞ。」
一五〇もの候補地を、吹雪の日々も短い夏もひとり歩き
栃木の研究所から北海道へ年二十回のペースで通った。
現場には独自に作成したチェックリストを持参する。気温、積雪量、地形等々項目の抽出にあたっては、各方面の先輩から助言を仰いだ。
「霧の量を推定するには――― 」
「近くの大河や湖からの距離を調べるんだ。それからな、堀越、本格的なワインディングを作るんなら、適度な高低差があるかどうかも重要だぞ。」
一五〇もの候補地を、吹雪の日々も短い夏もひとり歩き
回った。
理想の地に出会えたのはダンボール箱にあふれる報告書を作成した後であった。その日、鼻の頭に汗を浮かべて林の中を歩いていると、頭上で鳥が羽ばたいた。
―――鷹だ。
堀越は美しい飛翔に息を呑んだ。鷹は昔から吉兆と言われる。
リストにつけた点数も高い。堀越の腹は決まった。「上川郡、鷹栖町か―――」
地元の人達もホンダを好意の目で迎えてくれた。川本に
理想の地に出会えたのはダンボール箱にあふれる報告書を作成した後であった。その日、鼻の頭に汗を浮かべて林の中を歩いていると、頭上で鳥が羽ばたいた。
―――鷹だ。
堀越は美しい飛翔に息を呑んだ。鷹は昔から吉兆と言われる。
リストにつけた点数も高い。堀越の腹は決まった。「上川郡、鷹栖町か―――」
地元の人達もホンダを好意の目で迎えてくれた。川本に
直訴したあの日から二年の歳月をかけ、夢はようやく水面から顔を見せたのであった。
次はコースのレイアウトだ。堀越は息をつく間もなく鈴木に呼ばれた。
「堀越、ドイツを見ておかなくていいのか。」
「ニュルですか。」
ニュルブルクリンク、世界で最も過酷なテストコースのひとつである。
NSXもそこでテスト走行して開発をやり直すことにな
次はコースのレイアウトだ。堀越は息をつく間もなく鈴木に呼ばれた。
「堀越、ドイツを見ておかなくていいのか。」
「ニュルですか。」
ニュルブルクリンク、世界で最も過酷なテストコースのひとつである。
NSXもそこでテスト走行して開発をやり直すことにな
ったほどだ。
堀越には格好の教材だ。
 「わかりました、この目で確かめてきます。」
「わかりました、この目で確かめてきます。」
―― 空港を降り立った堀越は、その足でニュルへ向かった。
コースを一通り見ると膝を叩いて大笑いし
堀越には格好の教材だ。
 「わかりました、この目で確かめてきます。」
「わかりました、この目で確かめてきます。」―― 空港を降り立った堀越は、その足でニュルへ向かった。
コースを一通り見ると膝を叩いて大笑いし
た。
「なんだ、路面の荒れたただの古い道だったのか!」
カーブが多く舗装の手入れも悪い山道、それがニュルだ。
ゆっくり走る分には何の変哲もない路面だが、高速で飛ばすと魔の道に変貌する。
そんなコースが、クルマの基本性能を鍛えてくれる。
日常の生活で威力を発揮するクルマだ。個性も備わる。
帰国した堀越は、玩具を手にした子供のように連日レイ
「なんだ、路面の荒れたただの古い道だったのか!」
カーブが多く舗装の手入れも悪い山道、それがニュルだ。
ゆっくり走る分には何の変哲もない路面だが、高速で飛ばすと魔の道に変貌する。
そんなコースが、クルマの基本性能を鍛えてくれる。
日常の生活で威力を発揮するクルマだ。個性も備わる。
帰国した堀越は、玩具を手にした子供のように連日レイ
アウトに没頭した。
クルマの弱点を暴いてくれる多彩な仕掛けを絞り出す。
複合カーブの前半と後半でμ(摩擦係数)を若干変えることでクルマがスピンしやすい構造にする、コーナーの手前のフルブレーキングの進入地点にさらに小さなコブをしつらえる、といった具合である。
また、山はなるべく削らない設計を心がけ、伐らざるをえない木は移植して大事に育てることにした。
一九九〇年、レイアウト完成、工事に入る。
クルマの弱点を暴いてくれる多彩な仕掛けを絞り出す。
複合カーブの前半と後半でμ(摩擦係数)を若干変えることでクルマがスピンしやすい構造にする、コーナーの手前のフルブレーキングの進入地点にさらに小さなコブをしつらえる、といった具合である。
また、山はなるべく削らない設計を心がけ、伐らざるをえない木は移植して大事に育てることにした。
一九九〇年、レイアウト完成、工事に入る。
時には堀越自ら土を盛ったり削ったりして路面の微妙な形状を作り上げた。
そして一九九三年九月、ワインディング・コース完成の日を迎えた。
「メッキをはがすと金無垢だった、そんなクルマが俺たちの理想だ―――」
鈴木の後を継いだ橋本健取締役の言葉を思い出しながら、堀越は数ヵ月ぶりに釣り糸をたれていた。
鷹栖が総合的なテストコースとしての完成を迎える一九
そして一九九三年九月、ワインディング・コース完成の日を迎えた。
「メッキをはがすと金無垢だった、そんなクルマが俺たちの理想だ―――」
鈴木の後を継いだ橋本健取締役の言葉を思い出しながら、堀越は数ヵ月ぶりに釣り糸をたれていた。
鷹栖が総合的なテストコースとしての完成を迎える一九