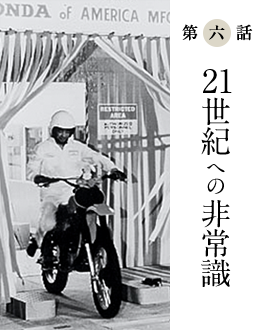ノンフィクション小説本田技研

- 第一話 安全への創造
- 第二話 完全燃焼への夢
- 第三話 自立航法の旅
- 第四話 安全は、こころ
- 第五話 未来へのコース
- 第六話 21世紀への非常識
- 第七話 砂に埋まった夢
- 第八話 夢見るハイブリッド
- ノンフィクション小説本田技研TOPへ


第六話 21世紀への非常識
「ああっ、駄目だ! 停まってしまう。くそ、走れ! 登れ!」
大薗耕平は、全速力で駆け出した。帽子が風に飛ぶ。髪が乱れに乱れる。丈高い草木に両手が傷だらけだ。が、大薗は気づかない。たった今、テストコースの坂道で急停止した後、登れなくなった2輪試作車CX400のことしか頭になかった。全身から、汗が散る。鼻水さえ出てくる始末だ。
テストライダーは降車していた。ヘルメットも外しか
大薗耕平は、全速力で駆け出した。帽子が風に飛ぶ。髪が乱れに乱れる。丈高い草木に両手が傷だらけだ。が、大薗は気づかない。たった今、テストコースの坂道で急停止した後、登れなくなった2輪試作車CX400のことしか頭になかった。全身から、汗が散る。鼻水さえ出てくる始末だ。
テストライダーは降車していた。ヘルメットも外しか
けている。これ以上試験走行できないという意味だ。「大薗さん! こいつは発進できないぜ!あんたのCVTってこんなものか」──なにか言い返したかった。しかし現実に停まったものに、どんな言葉があるだろう。首筋に冷たい汗を感じた。後からスタッフが駆け寄ってくる。なにか言ってる。耳に入らない。
CVT、それは連続可変レシオ・トランスミッション。と言っても、一般にはわかりにくい。つまり無段変速機構である。昔から変速機の、理想型とされてきたも
CVT、それは連続可変レシオ・トランスミッション。と言っても、一般にはわかりにくい。つまり無段変速機構である。昔から変速機の、理想型とされてきたも
のだ。理想と言うだけあって、当時だれも完全に近いものは創りだしてはいなかった。だれも…いや、たぶん世界にひとりだけこの可能性を秘めた男がいた。大薗はCVTの夢に憑かれていたのである。
その夜、スタッフ達は研究所に帰った。反省会だ。これからのことを色々議論し合う。だれかがビールを持ちだした。硬苦しい会ではない。が、車で帰れない。泊り込むぞ、との意思表示なのだ。──大薗は少し離れた席でビールを飲み干した。苦い。ただ、ほろ苦い。ここま
その夜、スタッフ達は研究所に帰った。反省会だ。これからのことを色々議論し合う。だれかがビールを持ちだした。硬苦しい会ではない。が、車で帰れない。泊り込むぞ、との意思表示なのだ。──大薗は少し離れた席でビールを飲み干した。苦い。ただ、ほろ苦い。ここま
で何年かかったろう。
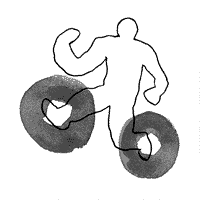 それは1978年のことだった。この年に大薗は(株)本田技術研究所に、入社した。いわゆる新卒採用ではない。途中入社である。それまでは、生産設備の会社にいて、本田に入った時は30代
それは1978年のことだった。この年に大薗は(株)本田技術研究所に、入社した。いわゆる新卒採用ではない。途中入社である。それまでは、生産設備の会社にいて、本田に入った時は30代
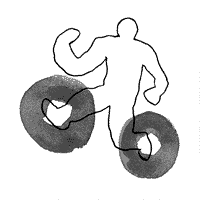 それは1978年のことだった。この年に大薗は(株)本田技術研究所に、入社した。いわゆる新卒採用ではない。途中入社である。それまでは、生産設備の会社にいて、本田に入った時は30代
それは1978年のことだった。この年に大薗は(株)本田技術研究所に、入社した。いわゆる新卒採用ではない。途中入社である。それまでは、生産設備の会社にいて、本田に入った時は30代になっていた。この時代は第2次オイルショクが世界を襲っていた。山口百恵は全盛期をむかえ、ウォークマンが流行し、NECはPC-8001を発表して日本のパソコン時代の黎明期が過ぎようとしていた。───
そしてこの年、本田はオハイオ州に巨大な2輪車工場をオープンした。
その2輪車用クラッチの開発から大薗の仕事は始まったのである。やがてある専門誌で古くからあるオランダのCVTメーカー、ヴァンドーネ社の金属ベルト式のも
そしてこの年、本田はオハイオ州に巨大な2輪車工場をオープンした。
その2輪車用クラッチの開発から大薗の仕事は始まったのである。やがてある専門誌で古くからあるオランダのCVTメーカー、ヴァンドーネ社の金属ベルト式のも
のの記事をみつけた。無論それは理想の性能には、ほど遠い。
だが、その存在が大薗を魅了した。(無段変速…切り替えるのではなく連続的な変速…常に最適の変速比を自動的に得れば…エンジンの出力特性をロスなくフルに伝達できる。理論的な変速ショックはゼロ、走りの能力は飛躍的になり、しかも…燃費向上を図れる)──大薗は確信した。やりたい。この理想型を理想通りに実現してみたい。まだ、世にない。だから、好きだ。好きなことをやりたい。それに本田が先々必ず使う技術になるだろ
だが、その存在が大薗を魅了した。(無段変速…切り替えるのではなく連続的な変速…常に最適の変速比を自動的に得れば…エンジンの出力特性をロスなくフルに伝達できる。理論的な変速ショックはゼロ、走りの能力は飛躍的になり、しかも…燃費向上を図れる)──大薗は確信した。やりたい。この理想型を理想通りに実現してみたい。まだ、世にない。だから、好きだ。好きなことをやりたい。それに本田が先々必ず使う技術になるだろ
う。世の中は必ず省資源技術を求めるだろう。小手先ではなくパワープラントという核心から低燃費を──俺の仕事だ。希望を出し2年後、認められてとりかかりまた2年、試作が完成した。(が、今日は失敗した。しかし、いつかは4輪にのせるまで進ませたい。自動変速をこえる革新にきっとなる。そのためには、あらゆる常識を破ることになりそうだ…)
そのいつかの日が12年後とは夢にも思っていなかった。
坂道停止事件は、大薗の身にしみこんだ。時代を画す
そのいつかの日が12年後とは夢にも思っていなかった。
坂道停止事件は、大薗の身にしみこんだ。時代を画す
るCVT、無段自動変速機構は、なまじっかのことではできない。教科書など、ない。
全力をあげて改良にとりくんだ。だが道は厳しい。道どころか巨大な崖に思えた。登る術がない。状況もわるい。大薗のいる朝霞研究所は、2輪が専門だ。2輪の純粋派はギアシフトを主張する。ギアを使わないCVTなぞ問題外と声が立つ。大薗の研究は金を使う、人も使う、設備も使う。やめろという空気を肌身に感じた。ある時、所長川本信彦(現本田技研社長)の来社を聞きつけた。チャンスだ! 人を介して、直接面談に及んだ。
全力をあげて改良にとりくんだ。だが道は厳しい。道どころか巨大な崖に思えた。登る術がない。状況もわるい。大薗のいる朝霞研究所は、2輪が専門だ。2輪の純粋派はギアシフトを主張する。ギアを使わないCVTなぞ問題外と声が立つ。大薗の研究は金を使う、人も使う、設備も使う。やめろという空気を肌身に感じた。ある時、所長川本信彦(現本田技研社長)の来社を聞きつけた。チャンスだ! 人を介して、直接面談に及んだ。
ここぞとCVTの長所を力説した。川本は仰天した。研究にでなく人に、である。(ふふ、こんな非常識な奴がまだいたか。それに…CVTか、なるほど)
実は若き日の川本はCVT搭載車を走らせる助っ人をやったことがある。
ブラバム・ホンダF2のエンジンを設計し、欧州に滞在中、ブラバムに頼まれてのことであった。しかし、この時の大薗は、まだそれを知らない。
なぜか熱意は通り研究継続はできた。1年、2年は矢のように過ぎ去る。
実は若き日の川本はCVT搭載車を走らせる助っ人をやったことがある。
ブラバム・ホンダF2のエンジンを設計し、欧州に滞在中、ブラバムに頼まれてのことであった。しかし、この時の大薗は、まだそれを知らない。
なぜか熱意は通り研究継続はできた。1年、2年は矢のように過ぎ去る。
3年、恐れていた事態がきた。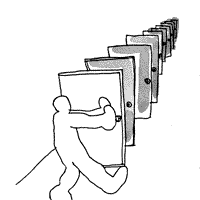 このCVTを採用する2輪車企画が開発中止に至ったのだ。市場ニーズがないとの理由だった。万事休した。
このCVTを採用する2輪車企画が開発中止に至ったのだ。市場ニーズがないとの理由だった。万事休した。
30代のほぼ全てを費やした研究が日の目を見ず、闇に消える──人は真に絶望した時、涙など出ない。た
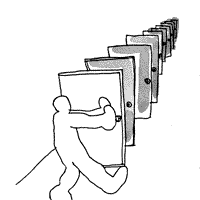 このCVTを採用する2輪車企画が開発中止に至ったのだ。市場ニーズがないとの理由だった。万事休した。
このCVTを採用する2輪車企画が開発中止に至ったのだ。市場ニーズがないとの理由だった。万事休した。30代のほぼ全てを費やした研究が日の目を見ず、闇に消える──人は真に絶望した時、涙など出ない。た
だ乾くだけである。大薗は幾つかの特許出願をし、研究終了宣言を出した。心は決めていた。(この会社、辞めよう)
出身畑の生産技術を専門とする関連会社がある。そこへ、と連夜思い屈していた矢先、不意を突いて辞令が下った。和光研究所へ異動せよ。(なに?和光)そこは4輪研究開発の本拠だ。(そうだ、いずれ辞めるとしてもその前に俺の研究を4輪の連中に伝えよう! むざむざと中断は自分への裏切りだ!)
大薗は迷いを捨て1987年和光へ移った。別の開発に
出身畑の生産技術を専門とする関連会社がある。そこへ、と連夜思い屈していた矢先、不意を突いて辞令が下った。和光研究所へ異動せよ。(なに?和光)そこは4輪研究開発の本拠だ。(そうだ、いずれ辞めるとしてもその前に俺の研究を4輪の連中に伝えよう! むざむざと中断は自分への裏切りだ!)
大薗は迷いを捨て1987年和光へ移った。別の開発に
携わりながら3年が過ぎる内に遂に協力者が現れた。軽自動車用CVT開発チームにいた青木隆である。
「と…云うわけで、発進クラッチはドリブン側に配置しないといけない」
「それは大薗さん、従来の無段変速と全く違うね。常識外れだ、だが──」
「そう、発進は極めてスムーズになる。つまり…」──その仕組みはこうである。変速ギアは使わない。2つのプーリーを使う。エンジンのパワーが入る方をドライブ・プーリーという。これが入力側だ。駆動輪へ出る方
「と…云うわけで、発進クラッチはドリブン側に配置しないといけない」
「それは大薗さん、従来の無段変速と全く違うね。常識外れだ、だが──」
「そう、発進は極めてスムーズになる。つまり…」──その仕組みはこうである。変速ギアは使わない。2つのプーリーを使う。エンジンのパワーが入る方をドライブ・プーリーという。これが入力側だ。駆動輪へ出る方
を、ドリブン・プーリーという。出力側だ。2つのプーリーの溝幅は、アクセル開度や車速などの条件により自在に変化する。と、2つのプーリをつなぐ金属ベルトの伝達ピッチ径も変化する。こうして得る変速比は連続的となり、つまり無段階変化になる。逆に言うと2つのプーリーは常に回転しないと変速できない。従来のドライブ側へのクラッチ配置では、急停車などで、クラッチが切れると変速できず、発進にもたつくわけである。「これなら停車時もプーリーは回転している、すぐに発進できる、安全な上に変速自在」「エンジンの最もおい
しい所を最も無駄なく引き出す」「全く新世代のATじゃないか! 技術の困難も山だが、燃費も走りも可能性が山ほどだ!」次代へのブレークスルーという山を2人は登り始めていた
「その通り!俺はこれを100馬力、5人乗り、車重1トンでと思ってる」
「私も軽自動車用では壁を感じてた。制約が多すぎる。でも、そのクラスでなら油圧制御をフルに電子制御で、できるな」── 普通のATもそうだが制御は油圧、つまり流体を扱う非常に難しいメカニズムである。
「その通り!俺はこれを100馬力、5人乗り、車重1トンでと思ってる」
「私も軽自動車用では壁を感じてた。制約が多すぎる。でも、そのクラスでなら油圧制御をフルに電子制御で、できるな」── 普通のATもそうだが制御は油圧、つまり流体を扱う非常に難しいメカニズムである。
──「全体に、うーむ、できるかな」「できるということにしよう」「よし! 」大薗と青木は意気投合した。1989年の末、機会はきた。次世代パワーユニット提案が全社的に求められたのだ。2人は他のチームもまとめ、新CVT開発を要素技術採用も含め提唱した。できるわけがない、否わからん、粉糾した。遂に2人ができると言うのだ、やらせろ、になった。これが本田である。
現物もなく紙上のことのみ、やりたい一心のみの提唱は翌年半ば、正式の開発開始に至った。約10年をかけ大
現物もなく紙上のことのみ、やりたい一心のみの提唱は翌年半ば、正式の開発開始に至った。約10年をかけ大
薗は漕ぎ着けたのである。だが、始めてみると怒濤のように問題続出した。クラッチは10秒で焼ける。金属ベルトは切れる、市販の電磁弁は低性能で自己開発せざるを得ない、枚挙にいとま無き有様だ。
しかし、それは革新技術の宿命であった。問題が出るほど大薗も青木も燃えた。若い技術者達も挑戦に興奮し献身した。徹底的な実用テストを重ねに重ね過剰なまでの性能、信頼性を実現した。完全燃焼のエンジニアは限界を知らない。「車種はシビックだな」「140カ国の人が乗る」「燃費向上が地球に効く」「と、なると」
しかし、それは革新技術の宿命であった。問題が出るほど大薗も青木も燃えた。若い技術者達も挑戦に興奮し献身した。徹底的な実用テストを重ねに重ね過剰なまでの性能、信頼性を実現した。完全燃焼のエンジニアは限界を知らない。「車種はシビックだな」「140カ国の人が乗る」「燃費向上が地球に効く」「と、なると」
 「伊藤さんに頼もう」──伊藤博之、3代目ら歴代のシビック開発総責任者は新CVTテスト車から降りるなり言った。
「伊藤さんに頼もう」──伊藤博之、3代目ら歴代のシビック開発総責任者は新CVTテスト車から降りるなり言った。「開発中の3ステージVTECエンジンと組み合わせよう、高出力対応で低燃費。次代へ
の進歩を見せるんだ」「高出力とは?」「130馬力だ」「ええっ! 」全面的開発をさらに要する、時間も金も…伊藤は微笑んだ。「僕は入社以来、初代シビックから、ずっとかかわってきた。その僕が、シビックにいくら使ったと思う」「?千億とかですか」「兆に近い」「…兆!?」ふだんは冷静な青木が一瞬、あっけにとられた。大薗も熱くなっていた。「二人供、いいか、とことんやってかまわない、それで世の中少しは素敵に変われば最高じゃないか」二人は勇み立った。「それと、経済走行、バランスのいい走行、抜群のスポーツ走行、3
つ切り替えモードをつけて。新CVTを乗る人にわかりやすく。これはシビックのメイン車種に搭載する」──メイン!
大薗の頭は沸騰した。何の実績もない全くの新技術を! 冒険だ! 「そうしないと一気に普及しない。いいか、次代シビックにのせられないと新CVTはないぞ! 」二人は余人の想像も及ばぬ超スパート作業へ走った。VTECリーダー藤村章は二人に合流した。なんと藤村は低、中、高回転3ステージで、高出力・低燃費が両立できる、できると社内宣言し、それから開発、実現して
大薗の頭は沸騰した。何の実績もない全くの新技術を! 冒険だ! 「そうしないと一気に普及しない。いいか、次代シビックにのせられないと新CVTはないぞ! 」二人は余人の想像も及ばぬ超スパート作業へ走った。VTECリーダー藤村章は二人に合流した。なんと藤村は低、中、高回転3ステージで、高出力・低燃費が両立できる、できると社内宣言し、それから開発、実現して
いた。そこでは設計の梶原が工学常識を覆し、燃焼の三浦が手造りの吸気ポートで希薄燃焼の定説を過去のものにしていた。なんだ、皆、俺と同じだ! 常識は関係ない!もう、やるまでだ。…1995年秋、6代目シビック搭載の新CVTは、「ホンダマルチマチック」として世に出た。大薗は最終テストでの川本の言葉を覚えている。「おい、諦めずやってよかったな!」
「ネバー・ギブアップですよ」それは次代への全エンジニアの内心の声かも知れなかった。 (終)
「ネバー・ギブアップですよ」それは次代への全エンジニアの内心の声かも知れなかった。 (終)

 エンジニア・トーク CVT
エンジニア・トーク CVT